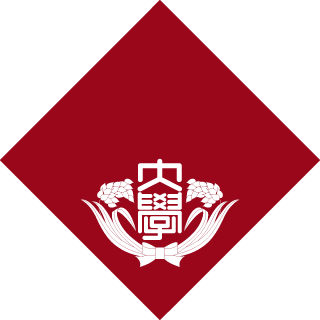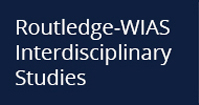- 森稔幸(Toshiyuki Mori)助教(2011年10月当時)
種を超えた受精機構の存在
性をもつ生物は、父方と母方から遺伝情報を受け継ぎ、次の世代をつくります。私たちヒトでは、精子や卵が遺伝情報の運び手となります。精子や卵は、「減数分裂」という特殊な細胞分裂を経てできる細胞で、DNAの量は普通の細胞の半分です。精子と卵が出合う「受精」により、次の世代が生まれます。ほかの動物や植物にも、精子と卵にあたるものがあり、受精により生殖が行われます。
これまでの研究成果から、生物の間には、種を超えた共通の受精機構があると考えられるようになってきました。本当に共通の受精機構があるかどうか、そして、その受精機構がどのようなものかを明らかにすることが、私の研究テーマです。
精細胞だけで働く遺伝子
私は学部の卒業研究から10年以上、植物を使って生殖機構を研究しています。
被子植物の生殖については、小学校で「雌しべに花粉がつくと実ができる」と習ったと思います。もう少し詳しく説明すると、雄しべの先端の葯(やく)の中で、減数分裂により花粉小胞子ができ、さらに細胞分裂をして、雄原細胞と栄養細胞からなる花粉ができます(図1)。そして、雄原細胞はさらに分裂をして、 2つの精細胞ができ、成熟した花粉になります。
花粉が雌しべの先につくと、花粉から「花粉管」という細い管が胚珠まで伸び、その管の中を2個の精細胞が移動して、一方は卵細胞と、もう一方は中央細胞と受精します。受精した卵細胞は、次世代の植物になる「胚」に、中央細胞は、発芽に必要な養分を供給する「胚乳」になります。胚と胚乳のセットが植物の種子となるわけです。

図1.植物の生殖行程。雄しべの葯の中で、花粉の元となる花粉母細胞が減数分裂をして花粉小胞子になる。続く細胞分裂により、雄原細胞と栄養細胞ができ、雄原細胞はさらに分裂して2つの精細胞になる。こうしてできた花粉は、雌しべにつくと花粉管を伸ばし、2つの精細胞は、卵細胞と中央細胞とそれぞれ受精する。
研究を始めた当初、私はテッポウユリを用いて、受精に必要な遺伝子の探索を行っていました。テッポウユリを使ったのは、花粉が巨大で実験材料として扱いやすいうえ、雄原細胞が花粉から大量に単離できる技術が開発されていたからです。生物体を構成する細胞は、すべて同じDNAをもっており、生命活動に必要な遺伝情報が含まれていますが、細胞によって使われる遺伝子は異なります。花粉の生殖細胞(雄原細胞、精細胞)だけで働く遺伝子を見つけることができれば、この遺伝子の働きをもとに、受精機構を明らかにできるはずです。そこで、花粉の雄原細胞を含む4種類の細胞で、働く遺伝子産物を比較したところ、雄原細胞のみで多く発現している遺伝子を見つけることに成功しました。これをGCS1(GENERATIVE CELL SPECIFIC 1:雄原細胞特異的遺伝子)と名付けました。 GCS1が本当に花粉の生殖細胞で働いているかどうかを調べるために、今度はシロイヌナズナを使って、緑色に光るタンパク質GFPの遺伝子をGCS1遺伝子につないで発現させました。すると、シロイヌナズナの花粉の中の精細胞が緑色に光る様子が観察され、GCS1が同細胞で働いていることをちゃんと確認することができました。GCS1が受精に働いている可能性が、ますます高まってきたわけです。
植物配偶子融合の決定因子を世界で初めて発見
そこで、GCS1の機能を明らかにするために、GCS1遺伝子が働かなくなったシロイヌナズナ変異株を調べてみることにしました。GCS1ヘテロ接合変異株(花粉の半数がGCS1変異を持つ株)は、全ての花粉において花粉管が伸長し2つの精細胞が移動するところまで正常でしたが、受粉後の雌しべは野生株に比べて約半数量しか種子ができないことがわかりました。さらに、野生株との掛け合わせ実験をしたところ、種子数が半減する原因は雄側(花粉側)にあるということが明らかになりました。半数量の種子形成はGCS1ヘテロ接合変異株花粉の半数を占める野生型花粉の受精によるものと思われます。従って、種になれなかった胚珠は、残りの半数のGCS1変異花粉の仕業と予想できるわけです。
では、どうして種子ができにくくなるのでしょう。つぎに赤く光るタンパク質で標識したGCS1変異精細胞の挙動を追跡したところ、胚珠の中で精細胞は、卵細胞の外側で締め出されている様子が確認できました(図2)。GCS1変異精細胞は卵細胞にくっつくことはできますが、融合することはできません。つまり、GCS1は、精細胞と卵細胞の融合に必要なタンパク質分子だということがわかったのです。
GCS1のアミノ酸配列と生化学的な解析から、GCS1は細胞膜に存在するタンパク質ということがわかっています。おそらく、GCS1は精細胞の表面で発現し、卵細胞側にはGCS1を迎え入れるような分子があり、精細胞と卵細胞との間に何らかのコミュニケーションがあって、融合が成立するのではないかと考えられます。この機構については、今後の研究で明らかにしたいと思っています。

図2.緑色に光っているのは卵細胞で、赤く光っている小さな2つの丸い物体がGCS1変異精細胞。GCS1変異精細胞は卵細胞の外側で締め出され、融合できない。
マラリアを撲滅できる?
GCS1はマラリア原虫にも存在することがわかっています。マラリア原虫においてGCS1の働きを調べてみると、GCS1遺伝子を壊したマラリア原虫の精子は、卵細胞に入り込めず、受精ができなくなることがわかりました。面白いことに、マラリア原虫のGCS1も、シロイヌナズナと同じように雄側の配偶子で機能して、受精を制御していたのです。
この発見を利用して、現在、マラリアを撲滅するためのワクチン開発の共同研究をしています。患者1人を治す方法ではありませんが、理想的に機能すれば、生態系からマラリア原虫を撲滅できる可能性もあります。
GCS1は、植物やマラリア原虫以外にも、粘菌や藻類、最近では腔腸動物や海綿動物でも存在することがわかっています(図3)。GCS1を基盤とした受精機構の全容を解明できれば、生物に共通の受精機構が明らかになるかもしれません。今後の研究で、受精機構に関わるGCS1以外の分子も明らかにしていきたいと思っています。
取材・構成:秦 千里
協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School