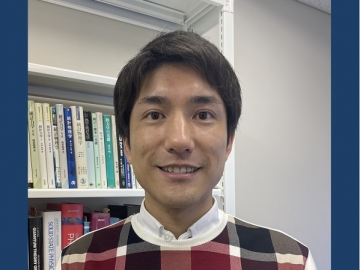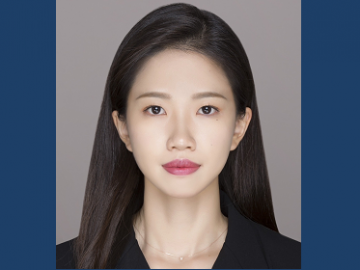- 中條美和(Miwa Nakajo) 助教(2014年5月当時)
国会ごっこから政治学者へ
私は政治学を専攻しています。研究者を志したきっかけは定かではありませんが、実は小学生の頃から国会が好きで、友達と国会ごっこをしたり、憲法を作ったり、ぬいぐるみを使って共和国を作ったりして遊んでいました。
もともと政治学の中では「有権者の投票行動」に興味がありましたが、投票行動の研究はこれまで数多く分析されていたのと、限られた機会である投票よりも、日常的な「政治に対する信頼」の方が分析しがいがあるのではないかと考え、現在のテーマを選びました。「政治への信頼がなければ政府は成り立たない」というのは言うまでもありませんが、「政治への信頼」は政府と市民の間をうまくいかせる潤滑油のようなものなので、この研究はとても重要です。
「政治への信頼」が何によって決定されるのかという大きな問題に対して、過去の研究では「政府に対する期待や評価」と「市民の社会参加」によって決まるとされています。ただし、「市民の社会参加」が「政治への信頼」を決定するという関係は、マクロレベルでは多くの研究者が証明していますが、ミクロレベルでは証拠が得られていません。マクロレベルとミクロレベルで分析結果が異なるのはなぜなのか?私はこの疑問を解明することにしました。
地方政治に注目して、疑問を解く
私はテキサス大学に留学していたこともあり、「アメリカの連邦制」に注目しました。理由としては、「政治への信頼」についての過去の研究が「国政への信頼」についてばかりだったので、「地方政治に対する信頼」はどうなっているのだろうか、実は定義がはっきりしていなくて、「国政への信頼」に「地方政治への信頼」も含まれているのではないかと思ったこと。それから、そもそも「市民の社会参加」は、地域社会で行われているということから、市や町といった「地方政治」に注目すべきではないかと考えました。こうして私は「市民の社会参加」と「国政への信頼」「地方政治への信頼」の3つを同時に分析することにしました。
過去の研究では、ミクロレベルでは「市民の社会参加」が「地方政治への信頼」へ影響を与えていて、「地方政治への信頼」と「国政への信頼」は相関性が高いことがわかっています。これらを考慮し、私はマクロレベルにおいて「市民の社会参加」は「地方政治への信頼」を経由して「国政への信頼」に影響を与えているのではないかという仮説を立てました。

図1:マクロレベルにおける「市民の社会参加」「地方政治への信頼」「国政への信頼」の関係の仮説図。矢印方向に影響を与える。
苦労して集めたデータで仮説を検証
データとして1972年から2008年までの様々な世論調査を集めました。「市民の社会参加」については、例えば「教会に行っているか?」「地域のコミュニティーのミーティングに参加しているか?」「ボランティア活動に参加しているか?」といった質問の答えを集め、国政や地方政治への「信頼」については、「あなたはどのくらい政府を信頼しているか?」「政府は不正をしていると思うか?」「自分の参加は意味があると思うか?」といった質問の答えを集めました。様々な質問の答えを統計的に処理して、「市民の社会参加」「国政への信頼」「地方政府への信頼」のそれぞれについて、年ごとに値を得ました。それが下のグラフです。
このグラフの3つの変数の間の関係を分析するために、複数の変数を分析できるVAR(VECTOR AUTO REGRESSION;ベクトル自己回帰分析)という方法を用いました。実はこの分析手法を勉強することと、データを集めるのに一番苦労しました。

図2: VARによる「国政への信頼」「地方政治への信頼」「市民の社会参加」の時系列データ。2001年の後、「国への信頼」が急激に高くなっているのは2001年の同時多発テロの影響と考えられる。また、全体に「地方政治への信頼」の方が、「国政への信頼」よりも高くなっている。
そして、このグラフから2つの値を取り出し、インパルス応答関数(過去のAに衝撃を与えた際に現在のBがどのくらい動くかを見るもの)を用いて、互いに与える影響を分析します。例えば「国政への信頼」から「市民の社会参加」への影響を調べる場合、ある年度の「国政への信頼」と次の年度の「市民の社会参加」の値を取り出して分析します。「国政への信頼」が高かった翌年の「市民の社会参加」が高くなっていれば、影響を与えているということになります。このような分析を4年後まで行って、統計誤差を超える影響が見られるかどうかを調べました。
少し意外な検証結果
分析の結果、「市民の社会参加」「国政への信頼」「地方政治への信頼」の関係は以下のようになりました。

図3: 結果として得られた「市民の社会参加」「国政への信頼」「地方政治への信頼」の関係図。「市民の社会参加」が「地方政治への信頼」に影響を与え、「国政への信頼」が「市民の社会参加」へ影響を与え、「国政への信頼」と「地方政治への信頼」は、互いに影響を与えている。
「市民の社会参加」から「地方政治への信頼」へは影響がありましたが、「地方政治への信頼」から「市民の社会参加」へは影響はありませんでした。そして「地方政治への信頼」と「国政への信頼」はお互いに影響していることがわかりました。このことから「市民の社会参加」は「地方政治への信頼」を経由して「国政への信頼」に影響を与えるという仮説が実証されました。
しかし、「国政への信頼」から「市民の社会参加」への影響が認められ、これは過去の研究と逆の結果になっているため、これについては他のデータや方法を用いてより精査する必要があります。
インターネットの普及が地方の意味を薄れさせる
民主主義の基本は政治に対する信頼から成り立っていますが、この研究を進めていくと、いかにして政治が安定していくかという道筋がわかると思います。今までアメリカのデータを分析してきたので、今後は日本のデータも分析してみたいと思っています。
また最近、インターネットなどの普及で「地方」の意味が薄れてきて、「地方政治」がなくてもいいという人もいるかもしれません。例えば、千葉や埼玉から東京に通っている人だと、地方政治の意識がないまま政治に参加しています。私は「市民の社会活動は地域に基づいている」という前提で「地方政治」に注目し、分析しましたが、今後は前提から再考する必要が出てくるかもしれません。
取材・構成:山崎景子
協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School