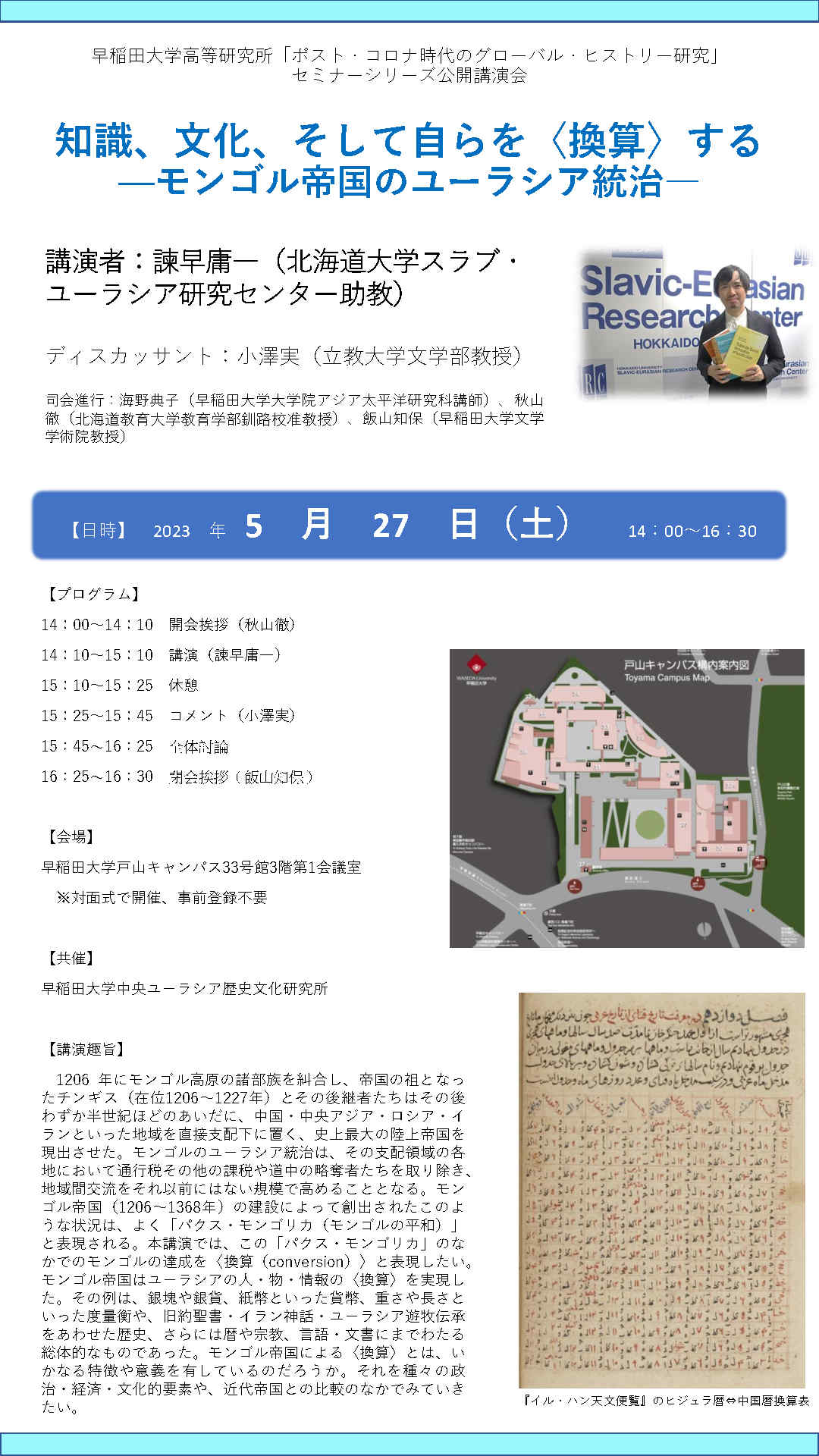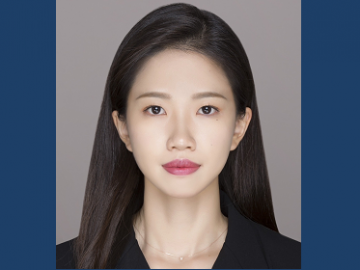高等研究所セミナーシリーズ
【ポスト・コロナ時代のグローバル・ヒストリー研究】公開講演会:
「知識、文化、そして自らを〈換算〉する——モンゴル帝国のユーラシア統治」(5/27)
趣旨
1206 年にモンゴル高原の諸部族を糾合し、帝国の祖となったチンギス(在位1206~1227年)とその後継者たちはその後わずか半世紀ほどのあいだに、中国・中央アジア・ロシア・イランといった地域を直接支配下に置く、史上最大の陸上帝国を現出させた。モンゴルのユーラシア統治は、その支配領域の各地において通行税その他の課税や道中の略奪者たちを取り除き、地域間交流をそれ以前にはない規模で高めることとなる。モンゴル帝国(1206~1368年)の建設によって創出されたこのような状況は、よく「パクス・モンゴリカ(モンゴルの平和)」と表現される。本講演では、この「パクス・モンゴリカ」のなかでのモンゴルの達成を〈換算(conversion)〉と表現したい。モンゴル帝国はユーラシアの人・物・情報の〈換算〉を実現した。その例は、銀塊や銀貨、紙幣といった貨幣、重さや長さといった度量衡や、旧約聖書・イラン神話・ユーラシア遊牧伝承をあわせた歴史、さらには暦や宗教、言語・文書にまでわたる総体的なものであった。モンゴル帝国による〈換算〉とは、いかなる特徴や意義を有しているのだろうか。それを種々の政治・経済・文化的要素や、近代帝国との比較のなかでみていきたい。
登壇者
講演者:
諫早庸一(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター 助教)
東京大学総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程単位取得退学。論文博士(東京大学、学術、2015年9月)。専門は前近代ユーラシア史、科学史、モンゴル帝国史。特に文化接触や環境史の観点から、モンゴル帝国(1206~1368年)をアフロ・ユーラシア規模で捉えることを志向している。ヘブライ大学ERCプロジェクト「モンゴル帝国期ユーラシアにおける移動・帝国・文化接触」のポスドク・フェロー及び日本学術振興会特別研究員(立教大学)を経て、現在、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター助教。主要業績として、以下の「モンゴル帝国期ユーラシアにおける天文対話」三部作を手掛ける。1) “Fu Mengzhi: “The Sage of Cathay” in Mongol Iran and Astral Sciences along the Silk Roads” in M. Biran et al. (eds.), Along the Silk Roads in Mongol Eurasia (Berkeley: University of California Press, 2020), 2) “Geometrizing Chinese Astronomy? The View from a Diagram in the Kashf al-ḥaqāʾiq by al-Nīsābūrī (d. ca. 1330)” in B. Mak & E. Huntington (eds.), Overlapping Cosmologies in Asia (Leiden: Brill, 2022), and 3) “Islamicate Astral Sciences in Eastern Eurasia during the Mongol-Yuan Dynasty (1271–1368)” in S. Brentjes (ed.), Routledge Handbook on Science in the Islamicate World (London: Routledge, 2022)。環境史研究では、日本学術振興会科学研究費助成事業(基盤研究B)「「14世紀の危機」についての文理協働研究」を研究代表者として推進中。
ディスカッサント:
小澤実(立教大学文学部 教授)
西洋中世史・北欧史・史学史専攻。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。日本学術振興会特別研究員(DC1)、コペンハーゲン大学歴史研究所研究員、名古屋大学グローバルCOE研究員を経て、2011年立教大学文学部准教授、2018年より同教授。2018年から19年にかけてオックスフォード大学グローバルヒストリー・センター研究員。北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同研究員。共編著に、Ozawa, T. M. Smith, and G. Strack (ed.), Communicating Papal Authority in the Middle Ages (London: Routledge, 2023)、小澤・佐藤雄基編『史学科の比較史:歴史学の制度化と近代日本』(勉誠出版、2022)、長谷川修一・小澤編『歴史学者と読む高校世界史:教科書記述の舞台裏』(勁草書房、2018)、小澤編『近代日本の偽史言説:歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー』(勉誠出版、2017)、小澤・長縄宣博編『北西ユーラシアの歴史空間:前近代ロシアと周辺世界』(北海道大学出版会、2016)、小澤・中丸禎子・高橋美野梨編『アイスランド・グリーンランド・北極を知るための65章』(明石書店、2016)など。
日 時
2023年5月27日(土)14:00~16:30
会場
早稲田大学戸山キャンパス 33号館 3階 第1会議室
プログラム
14:00~14:10 開会挨拶(秋山徹)
14:10~15:10 講演:
「知識、文化、そして自らを〈換算〉する——モンゴル帝国のユーラシア統治」(諫早庸一)
15:10~15:25 休憩
15:25~15:45 コメント(小澤実)
15:45~16:25 全体討論
16:25~16:30 閉会挨拶(飯山知保)
司 会 / 挨 拶
海野典子( 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 講師)
秋山徹(北海道教育大学教育学部釧路校 准教授)
飯山知保(早稲田大学文学学術院 教授)
対 象
大学院生、教員、一般
主 催
早稲田大学 高等研究所
共催
早稲田大学中央ユーラシア歴史文化研究所
申込み
事前登録不要
ポスター