「より良い主張は、組織力と信頼関係から」
法学部 3年 中花田 武秀(なかはなだ・たけひで)

戸山キャンパス 学生会館にあるサークルの部室にて
公認サークル「国際法研究会」に所属し、国内外の模擬裁判大会で優秀な成績を収めてきた中花田さん。世界最大の国際法模擬裁判大会とされる「Jessup」の国内予選で優勝し、2024年4月にワシントンD.C.で開かれた世界大会に出場する他、宇宙法について議論を交わすマンフレッド・ラクス宇宙法模擬裁判大会アジア・太平洋予選に日本チームの一員として参加するなど目覚ましい活躍を続けています。そんな中花田さんに、法律に興味を持ったきっかけや模擬裁判大会で印象的だったこと、今後の展望などについて聞きました。
――早稲田大学の法学部に進学した理由と、模擬裁判大会に出場したきっかけについて教えてください。
高校生の頃から国際機関で働くことに興味があったんです。どういう形で自分が関わることができるのか模索していたときに、興味を引かれたのが法律という切り口でした。国際社会において秩序のある暮らしやすい社会を維持する上で、法律によるルールメイキングが重要な役割を果たしていると感じ、それらを深く学ぶために法学部への進学を決意しました。
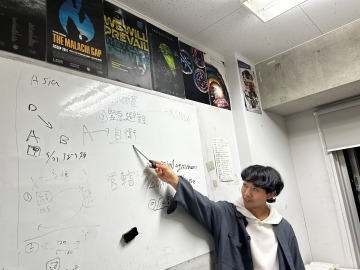
部室にて模擬裁判のテーマについて論を深める様子。サークル員同士で活発な議論が行われる
入学後は、サークル活動でも学びを深めたいと考え、「国際法研究会」に入会しました。先輩たちがチーム一丸となって模擬裁判大会に挑み、勝利を掴み取る姿に感動を覚えて、私も積極的に関わりたいと思うようになりました。
――模擬裁判大会の具体的な内容や、その醍醐味について教えてください。
国際法の模擬裁判とは、主権国家間の争いを題材に、原告・被告それぞれの主張を考え、その主張の論理性や説得力、弁論のパフォーマンス性の評価により勝敗がつくチーム競技です。模擬裁判当日までの流れとしては、まず大会ごとに設定されるテーマについてチームのメンバーで綿密な調査を重ね、自分たちの主張をメモリアルと呼ばれる書面にまとめて事前に提出します。大会当日はチームの代表である弁論者が、メモリアルをもとに大会本部側の裁判官役に主張を展開し、裁判官役からの質問にも応じます。私が出場してきた大会はこの答弁が全て英語で行われるため、語学力も鍛えられていきます。私は模擬裁判の準備期間には週6、7回部室に行くなどとにかくのめり込んでいましたね。
模擬裁判大会の面白いところは、「裁判官役とのキャッチボール」です。どれだけ事前に議論して対策をしていても、裁判官役からの予期せぬ質問によってその場での思考の応用が求められることが多々生じます。この対応が難しくもあり、醍醐味でもあると感じています。また、前提となる法律の解釈だけでなく、テーマに対する当該主権国家の政治的価値観を含めた主張の軸を確立した上で、それに対する自分なりの意見も求められるところにもやりがいを感じます。
――1番印象に残っている出来事は何ですか。

京都で行われたJessup2024国内予選で優勝したときの1枚。前列中央が中花田さん
世界最大の国際法模擬裁判大会とされる「Jessup」に弁論者として2年連続出場し、チームを国内優勝に導いた経験ですね。この大会で弁論者に選ばれるのは、約20名のチームメイトの中からたったの4名。光栄であるとともに、プレッシャーも相当なものです。
1年生ながら立候補して弁論者を務めた初めての大会では、自分の実力のなさを痛烈に感じ悔しい思いをしました。チームメイトである先輩方のおかげで国内優勝は果たしたものの、進出したワシントンD.C.での世界大会の結果は135チーム中124位と振るわず、自分の知識不足や英語での対応力が足を引っ張ってしまったと後悔しました。
そこから一念発起し、さまざまなテーマの法律の勉強に励んだり、チームメイトに裁判官役を頼んで答弁の実践練習を重ねたりとひたすら努力しました。特に英語に関してはメモリアルを丸暗記するのではなく、要点を押さえて自分の言葉で表現できるように工夫しました。そのかいあって2年目の2024年大会の答弁では、前年に比べて柔軟に思考し素早く的確に答えることができたように思います。無事国内優勝を成し遂げた後、世界大会で143チーム中54位に食い込む健闘を見せられたのは自分にとって貴重な経験となりました。
――2023年6月に開催されたマンフレッド・ラクス宇宙法模擬裁判大会アジア・太平洋予選には、サークルを代表して日本代表チームに参加していますね。

大会中の弁論の様子。裁判官役を前にしたときの緊張はひとしお
気の知れたサークルのメンバーで出場する「Jessup」とは異なり、マンフレッド・ラクス宇宙法模擬裁判大会は他大学の代表とチームを組んで計5名で挑戦しました。例えば、京都大学の代表とは基本的に大会当日までオンラインでのやりとりだったので、コミュニケーションの取り方に苦労しましたね。
また、通常の国際法模擬裁判大会と大きく違うところは、今現在の課題ではなく、主には近い将来に起こり得る課題について議論するというところです。今回の大会のテーマは「Case Concerning Laser Activities and the Use of Anti-Satellite Weapons in Outer Space (宇宙空間におけるレーザー活動および対衛星兵器の使用に関する事件)」。具体的には「A国の衛星が誤作動を起こし、B国の衛星に損害を加える可能性がある場合、B国は武力を行使して自国の衛星を守る権利があるか」というように、宇宙空間における活動に地球上の国際法が適用できるかについて議論しました。
近未来にこのような事態が起こったときに、どう解決していくかを事前に法的に考え議論していくことが目的です。そのため、主張を考えるにあたってはこれまでの事例だけでなく、専門外の先進科学の知識を今まで以上に調べ、さまざまなパターンの主張を想像するのが難しかったですね。でも、ここでもリサーチで頼りになるメンバーがいたり、逆に自分は論をまとめる役割を積極的に担ったりと、おのおのの強みを生かして準備ができたと思っています。
この大会では、国際法の運用において、国家や国際社会の利益という様々な対立構造を正確に捉える必要性を再確認でき、また全ての利益に配慮したルールメイキングを慎重に行う重要性を実感しました。
――それぞれの大会出場を通して学んだことを教えてください。
法的、論理的な思考や英語の運用の仕方を学ぶことができ、2年間でこれらの力は飛躍的に向上しました。そして、模擬裁判大会を通してさまざまな国の人たちと法的な議論ができたことは、すごく貴重な経験でした。例えば中国やインドの弁論者は、大会の場でも表現力がすごく豊かで、説得力があったんです。論理的な面では自分たちも負けていなかったと思いますが、それを伝える力や伝え方の重要性を学びましたね。
国際大会では模擬裁判以外に懇親の機会が設けられます。世界のエリートたちがそういう場でははっちゃけてダンスするなど、日本にいたら気付かない国民性の違いに触れることができたのは、とても良い経験だったと思います。

世界大会の後には自国の伝統衣装を着て国際交流をするプログラム「ナショナルドレスパーティー」が行われる。写真はインドネシアチームとの交流の様子。左から2番目が中花田さん
また、模擬裁判では、チーム全体のコミュニケーションが大事なのだと学びました。入会したての初心者が知識の面などで気後れする気持ちは分かりますが、初心者の意見こそ必要な視点になる場合もあるので、学年や上下関係を気にせず率直な意見を言い合える環境を自分から作っていきたいですね。良い議論をするためにはまず信頼関係を築くことが何より大事だと感じたので、次は先輩として積極的に組織力の向上に努めたいです。

世界大会が行われたワシントンD.C.の連邦議事堂前でチームメイトと。左端が中花田さん
――今後の展望について教えてください。
チームを指揮し、世界大会における日本代表のさらなる活躍に貢献したいです。個人としては法学部の「3年次早期卒業制度」を利用して卒業し、海外の大学院に進学したいと思っています。進学後は国際機関で働きたいという将来の夢をかなえるために、模擬裁判で培った経験をベースに、英語を使って国際法や人権法に対してアカデミックに学びを深めて行きたいです。
第876回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
文化構想学部 4年 田邊 紗彩
【プロフィール】
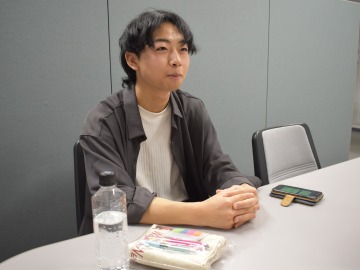
取材中の様子
東京都出身。都立南多摩中等教育学校卒業。お気に入りのワセメシは家系ラーメンの「違う家」。高校時代は和太鼓部に所属し、佐賀県総文祭(全国大会)でチーム優勝した経験も。








