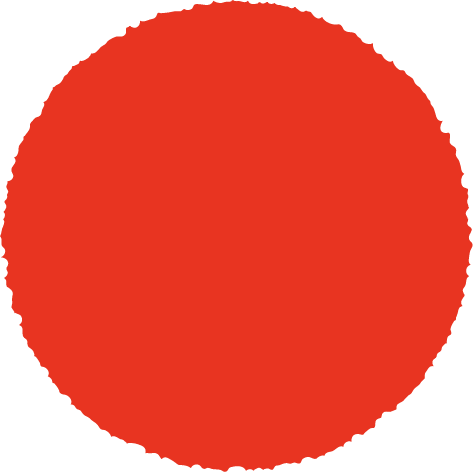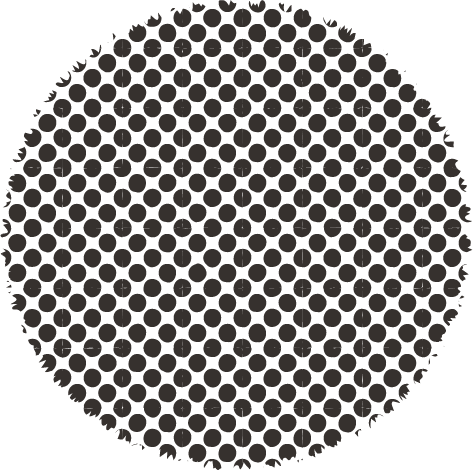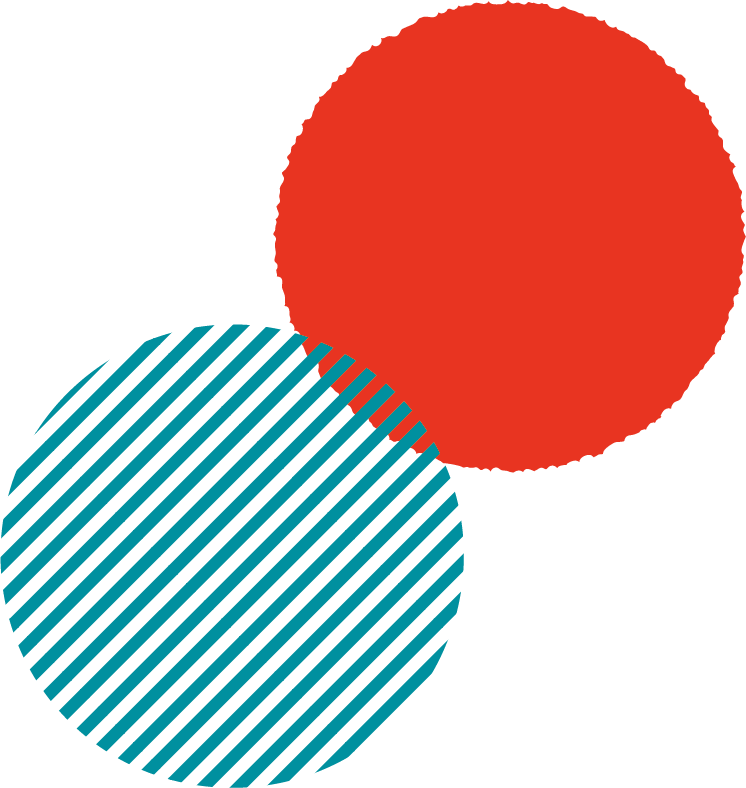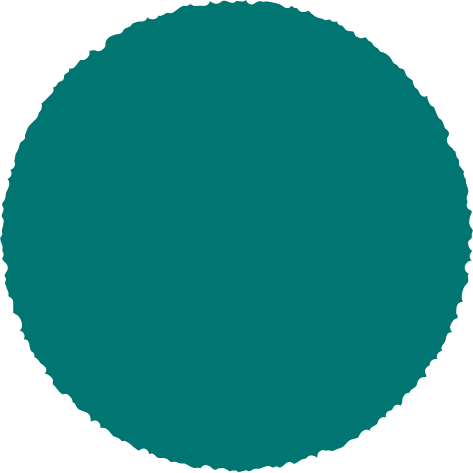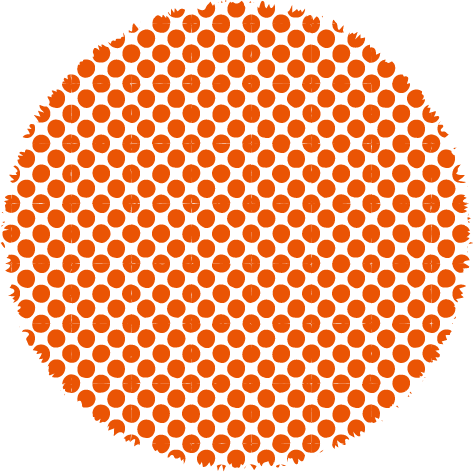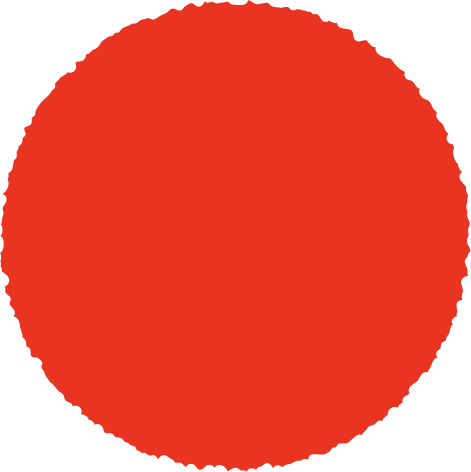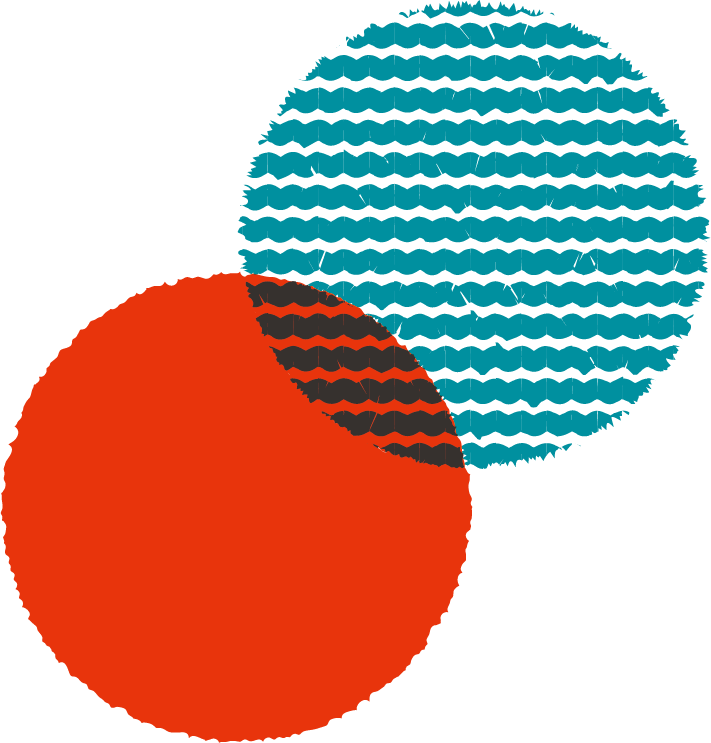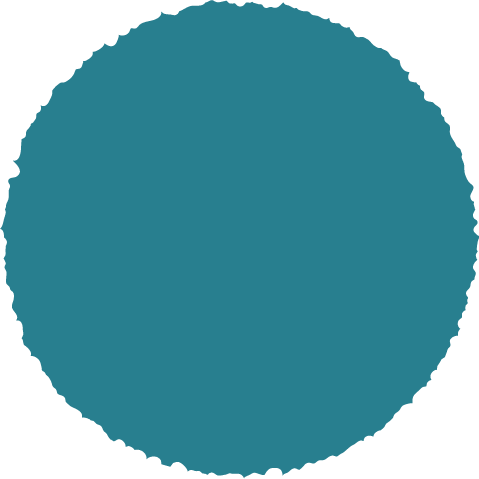味噌(みそ)、醤油(しょうゆ)、酒など、私たちの食生活には欠かせない発酵食品に対して、近年、注目が集まっています。小倉ヒラクさん(2007年、第一文学部卒)は、そんな発酵の世界を紹介する「発酵デザイナー」として活躍し、先日初の著書となる『発酵文化人類学』(木楽舎)を出版したばかり。そんなヒラクさんが、学生のころから憧れ続けているノンフィクション作家の高野秀行さん(1992年、第一文学部卒)は、大学時代には探検部に所属し、30年余りにわたってアフリカ、東南アジア、イスラム諸国など、世界各地の辺境の地を巡ってきた人物です。そして、高野さんもまた、発酵の魅力に取りつかれ、アジア各国の納豆を取材した『謎のアジア納豆』(新潮社)を上梓しています。 世界を旅する二人がハマってしまった、見えない微生物によって生み出される「発酵」という世界。いったい、そこにはどんな魅力が隠されているのでしょう? お話を伺っていくと、そこには食文化だけでなく「社会」や「生き方」、さらには「人間」を考える上での貴重なヒントが眠っていました。

- ヒラク
- 今日は、お会いできて本当に光栄です! 大学生のときに『アヘン王国潜入記』(集英社文庫)を読んで、「ヤバすぎる!!」と感じて以来、『謎の独立国家ソマリランド』(本の雑誌社)も読んだし、『謎のアジア納豆』にもハマりました。特に20代のころはよく旅をしていたので、高野さんの本ばかり読んでいたんです。
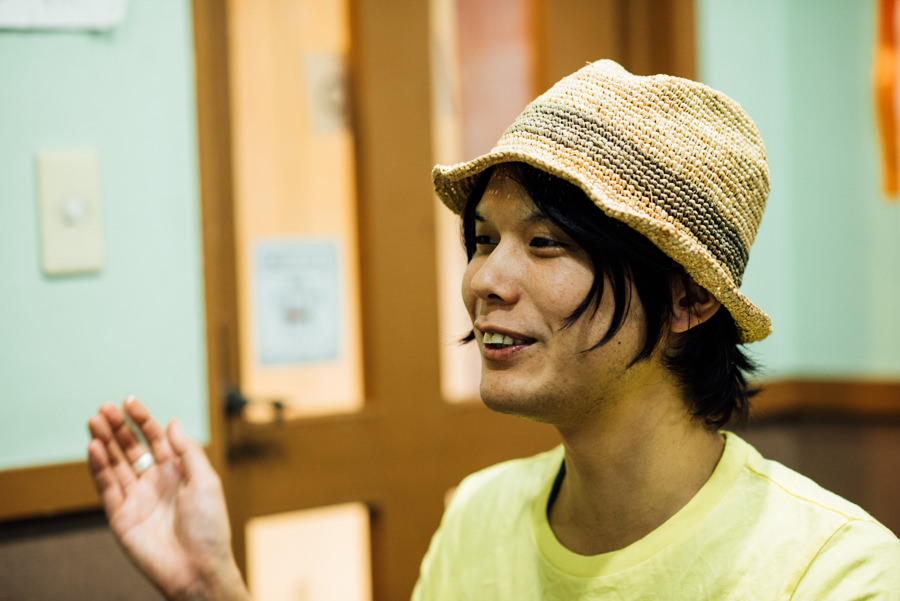
10年来の大ファンなんですね!
- 高野
- ヒラクさんの『発酵文化人類学』も、とても面白かった。歴史に残る本ではないかと思います。ただ半分くらい酒のことが書いてあるから、読んでいると飲みたくなってくる(笑)。
- ヒラク
- 日本において、発酵の神髄は酒にあるんですよ。
- 高野
- どの国に行っても一番商品価値が高い発酵食品は酒ですよね。だから、一番気合いを入れて作るし、民族の美意識が一番反映される。一方で、僕が追いかけてきた納豆のような発酵食品の地位は低い(笑)。

- 名古屋大学でアジアの発酵食品を研究しているある先生は、酒の調査に行くと何も教えてくれないのに、納豆の調査に行くとみんな喜んで見せてくれる、と苦笑して いました。
生活に身近な納豆は、隠す価値もないというイメージなのでしょうね。
- 高野
- 現地の人も喜んで教えてくれるから、実は取材はすごく楽なんですよね(笑)。ところで、素晴らしい発酵食品に出会うと「もったいない」という感じがしてこない?
- ヒラク
- 分かります!
- 高野
- 辺境の地や田舎に足を運び、一般には知られていない発酵食品があると、「これが知られていないなんて、もったいない!」という気持ちが湧いてくる。工場ではなく、家庭の中で細々と作られている納豆がめちゃくちゃうまいのに、ほとんどの人はそれを知らないんです。
- ヒラク
- 現地の人も発酵食品にはそんなに価値を置いていないから、「これはすごく面白い」「すごくおいしい」と言うとびっくりされることがよくあります。自分たちにとっては当たり前で古臭い食べ物なのに、外から来た人が褒めてくれるなんて、彼らにしたら謎なんでしょうね。

高田馬場「ノング インレイ」でシャン族(ミャンマー)の発酵料理を食べながら
- 高野
- 取材に行くと「何でウチに来るの? もっとおいしいものがあるのに」と言われます。現地の人にとっては、当たり前すぎて価値が分からないんですよ。一方、都会に住んでいる人も、存在自体を知らないから、やっぱり価値が分からない。
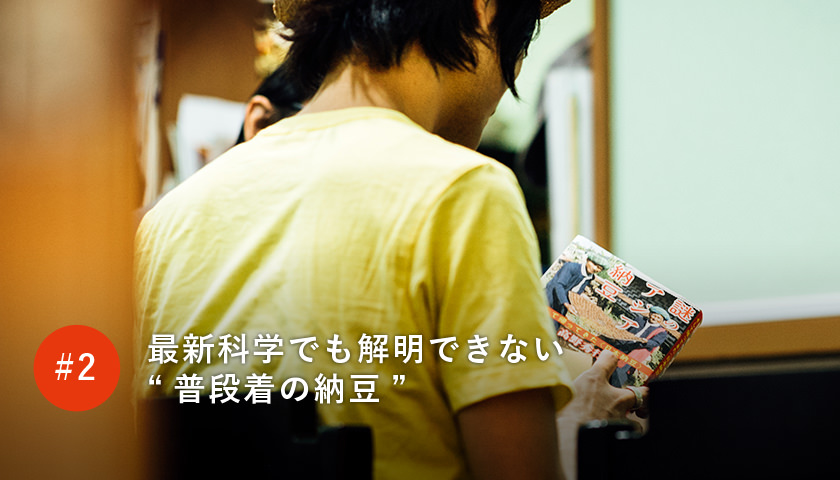

ヒラクさんは「発酵デザイナー」として、高野さんの『謎のアジア納豆』をどのように読まれましたか?
- ヒラク
-
まず、この本は、大学の先生や研究者には書けない本です。僕もしばしば研究者の調査に同行するんですが、たいてい向こうの学術機関などに全てお膳立てされていて、本当の「現場」を見ることはできません。
でも、高野さんは現地に行き、積極的にコミュニケーションを取りながらディープな場所までたどり着いていく。だから他では読めないような情報ばかり書かれているんです。一次情報中の一次情報ですよね。読んでいて、フィールドワークの大切さを痛感します。

- 高野
- そもそも、何も用意していないですからね。まず現地の市場に行って、「これは面白い」「すごくおいしい」というものを見つけてきて、「作っている人を紹介してほしい」と交渉する。東南アジアでは、親戚や知り合い、あるいは自分自身で納豆を作っているので、「現場を見たい」と言えば、たいてい「いいよ!」と快諾されるんです。
- ヒラク
- こういうやり方でしか、本当のローカルな情報って掘れないんです。現地の人が現地の価値観で作って味わっている発酵食品と、学術機関や業界でオフィシャルに扱われている発酵食品は、ややレイヤーが異なります。だから、現地に行くと、大学の先生たちが言っているのと違う情報ばかり。オフィシャルな情報は、あくまでも“よそ行き”なんですよね。

高野さんの掘り出してくるのは、家族が家の中で作っているような、“普段着の納豆”の姿ですものね。ところで、高野さんは世界各地を巡るノンフィクション作家でありながら、なぜ納豆に目を付けたのでしょうか?
- 高野
- 日本人は「納豆は日本独自の食べ物」と思い込みがちですが、東南アジアにも納豆文化があります。それをもっと知らしめ、ミャンマーのシャン族を紹介する一つの切り口にできないかと考えていたんです。そもそも僕は、20年以上前からシャン族に関わっていて、実は独立運動に関わっていたこともある。この民民族の文化を伝えるために、“納豆”がいい切り口になるんじゃないかと思いました。

ミャンマー東北部のシャン州に住み、ビルマ族に次いで200万人余りの人口を持つシャン族は、和食にも近い食文化を持っている民族だそうですね。
- 高野
- ただ調べているうちに、だんだんと納豆そのものが面白くなってしまった(笑)。しかも、実は日本の納豆についても全然知られていないな、ということに気付いたんです。過去の研究をあさってみると、納豆ご飯という風習が根付いたのも幕末から明治時代。ごく最近のことだったんです。それまでは納豆汁が主な食べ方だったと思われます。
納豆ご飯の歴史は浅いんですね! あまりに身近すぎて、そんな歴史まで調べようとすら思いませんでした。
- ヒラク
- 発酵食品って、当たり前と思われていても謎に包まれていることはとても多いんですよね。例えば、ぬか漬けをつくるぬか床の中で、どんな菌がどんな作用をしているかすら、あまりに複雑すぎて現代の科学は解明することができません。
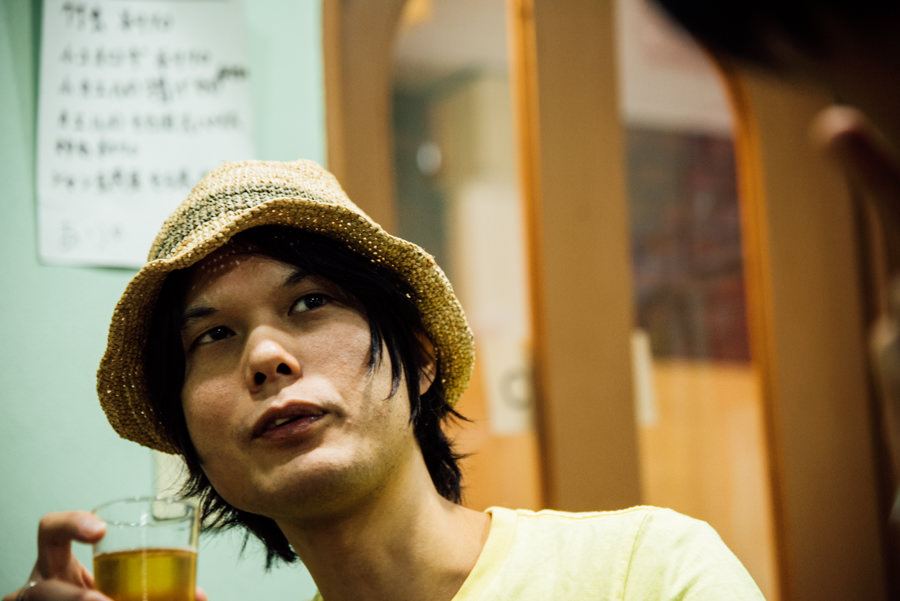
- 発酵学においては、菌を分離して研究するのですが、微生物の中には分離をすることによって死んでしまうものもいるんです。ぬか床と同様に、キムチも菌の数が多すぎて解明できません。ヨーロッパのワインやパンなどは、関与する菌の種類も少なく比較的簡単なのですが、東アジアの発酵食品は複雑すぎます。
最先端の科学でも追いつけない世界が、ぬか床の中にあるんですね!
- ヒラク
- 取材の過程で、シャン族から納豆研究へのスイッチが入った瞬間はあったんですか?
- 高野
- 日本で失われた納豆の神髄が残っているのではないか? と思った瞬間ですね。日本では、もう納豆は工業的にしか作られていませんが、昔は普通の家庭で、わらに包んだ納豆を作っていました。シャン族やカチン族といったミャンマーの民族では、今でも昔ながらの方法で納豆が作られており、工場で作られる納豆よりも日本の伝統的な手作り納豆に近いはず。そうした確信を得て、東南アジアだけでなく、日本の納豆の本当の姿を探しに行くようになったんです。
- ヒラク
- 文化を比較して観察するという、文化人類学的な発想ですね。
- 高野
- そうそう。タイやミャンマーの納豆作りを見た後は、日本の納豆を見る目も違ってくるんです。東南アジアの納豆は日本に比べて粘り気が少ない。これは衝撃的でした。過去に自分で納豆を作ったときには、匂いも味も納豆なのにねばりが普通の納豆よりも少なかったので、失敗だと思って捨ててしまっていたんです。

- けれども、東南アジアではねばらない納豆も珍しくない。納豆菌自体は基本的に同じだけど、向こうでは糸引きを強くするときもあれば、別にこだわらないときもある。あえて、糸引きが弱いものを作ったりもする。その方が料理に使いやすかったりするんです。“現代の日本の納豆”という基準で見ると失敗に見えても、別の視点から見るとそうではない。価値観を変えると、見え方もガラッと変わってきます。
- ヒラク
- 納豆菌は世界中にいるんですが、中には糸引きが強いものもあれば、そうでないものもある。作り方によっても菌の働きは変わってくる。日本人はご飯にかけて食べたいから、糸引きの強い納豆を作る傾向にあって、さらに近年では、工場生産によって培地や発酵環境を工夫して、より強く糸を引くように作っているんです。他のアジアの国では糸を引かない菌や香りの異なるものを選んだりしています。つまり納豆にはもっと多くの可能性がある。僕らが思っているよりも、“納豆”の概念は広いんですよね。
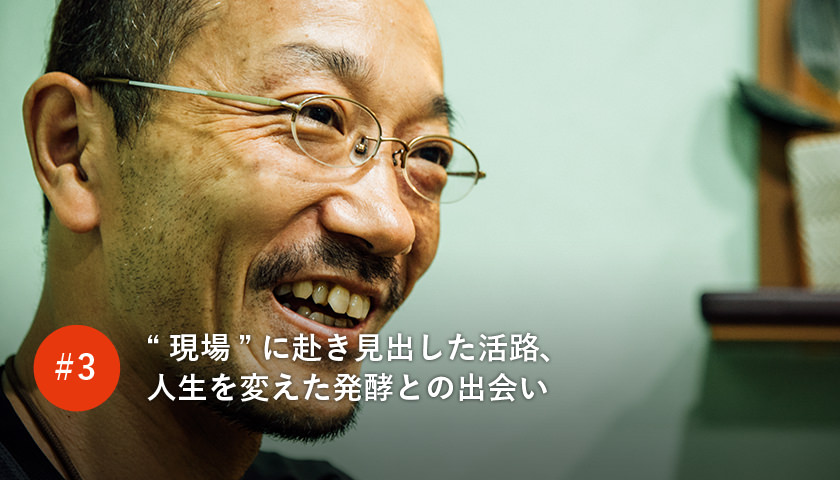

高野さんは、在学中から探検部に所属し、在学中にコンゴ共和国のUMA(※未確認生物)を追った『幻獣ムベンベを追え』(集英社文庫)も出版しています。大学ではどのような勉強をしていたんでしょうか?
- 高野
-
子どものころから漠然と「考古学者になりたい」と思っていました。高校時代には、レヴィ=ストロース〔※『野生の思考』(みすず書房)『悲しき熱帯』(中公クラシックス)などの著作があるフランスの文化人類学者〕や、『ムー』(※学研プラスの発行するオカルト雑誌)が愛読書だったので、本当は人類学をやりたかった。ムー、探検、人類学、それらが混然一体となり、世界の秘境に行き、謎を解き明かしたいと思っていたんです。
けれども、人類学を勉強する考古学専修には進めなかった。選考は成績順で決まったため、真面目な女の子たちばかりが考古学専修に入り、『ムー』を読んでいるような人間は受け入れられなかったんです(笑)。それで、フランス文学専修に進みました。
当時から、旅の魅力にのめり込んでいたんですね。
- 高野
- 早稲田に入学した当初、周囲にはできるやつばかりいて、文学、映画、演劇…何でも知識があり、頭も良かった。そんな人たちを見ながら、どうやって太刀打ちすればいいのかわ分らなかったんです。

- でも、インドやアフリカに行って帰ってくると、みんなとてもびっくりしながら話を聞いてきました。結局、なんだかんだ言っても、行ったことがなければ分からないし、やったことがなければ何も言えません。体力だけ、頭脳だけ、では勝てなくても、とにかく持っているものを総動員して活路を見出す。分からければ現地に赴き、人に会いに行く。自分は、そうやってようやく一人前なんです。今でも、現場に足を運び、自分の目で見て、人に話を聞く、というスタイルは変わらないですね。
なるほど。発酵だけでなく、文化人類学やアート、サブカルチャーなどさまざまな世界に精通し、それらと発酵とのつながりを見出しているヒラクさんは、どのような勉強をしていたのでしょうか?

- ヒラク
-
もともと美術大学を志望していたんですが、親に美大は授業料が高いから駄目と言われて、早稲田に入学しました。演劇映像専修に所属して映画の勉強などをしていたんですが、映画には100年余りの歴史しかなく、本気になって調べると、概要は半年や1年である程度分かってしまう。じゃあもっと詳細に映画を学びたいかというと、そこまでの情熱はなくて。
そんなとき、文学部で民俗芸能を専門にする和田修先生(文学学術院准教授)のゼミで新潟県佐渡島の合宿に行き、薪能(※薪の明かりを照明とする野外能)を見たんです。その瞬間「これはとんでもない世界だ!」と感じ、各地の文化やルーツを掘るようになった。アート系の勉強は最小限にして、文化人類学、民俗学、言語学、神話学といった世界にのめり込むようになりました。
ゼミ合宿がきっかけで興味の方向が大きく変わってしまったんですね。
- ヒラク
- それからは、バックパッカーをしながら各地を旅し、大学3〜4年にかけては、フランスで絵の修業をし、パリで展覧会も開催しました。ただ、日本に帰ってみたら、すでに就職活動は終わっていて…。その後、イラストのアルバイトをしていた関係で、とあるスキンケアメーカーでデザイナーとして仕事をするようになります。
当時、発酵に対する興味は?
- ヒラク
- 1ミリもなかったですね(笑)。発酵との出会いは、デザイナーとして独立するタイミングで体を壊したとき。たまたま小泉武夫さん(※発酵学者。食文化に関する書籍を数多く執筆)に出会いました。小泉先生は、僕の顔を見るなり、「このまま暮らしていたら死ぬぞ。発酵食品を食え」と言いました。それで、毎日納豆と味噌汁を食べるようになったら、本当に良くなってきたんです(笑)。それから発酵食品にハマっていくようになります。
健康を入口として、発酵食品と出会ったんですね。
- ヒラク
- 昔はマス広告をデザインして業界紙に載るような、おしゃれなデザイナーとして名を上げたかったんですが(笑)、発酵に出会ってからは夜にはこっそり味噌を仕込むような生活に変わりました。当時は、発酵なんて世間のイメージも良くなかったし、ほとんど情報もなかった。

- けれども、そんな生活を続けていくうちに、ある日「微生物以外のことはしたくない」ということに気付いてしまった(笑)。それで、ついには、自分で立ち上げて3年くらいやっていた会社も辞め、東京農業大学の研究生になったんです。もちろん相当悩みましたけど、自分への愛を優先させようと思ったんです。
「自分への愛」とは?
- ヒラク
- デザイナーとしてクライアントの課題解決をするうちに、いつのまにか人から認められるために仕事をするようになってしまっていたんです。でも、他人から承認欲求を満たしてもらわないと前に進めないなんて、健全じゃない。そこで「自分で自分のことを満たしていく生き方」に方向転換したんです。
人から認められるためではなく、自分を満たすために人生を選択したんですね。
- ヒラク
- 対象は微生物でしたけど(笑)。
後編ではいよいよ、発酵や食文化を通して見えてくる「社会の在り方」や「自由な生き方」について、お話を伺っていきたいと思います。

- 高野秀行(たかの・ひでゆき)
- ノンフィクション作家。1966年、東京都八王子市生まれ。早稲田大学第一文学部仏文科卒。1989年、同大探検部の活動を記した『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。2006年『ワセダ三畳青春記』で第1回酒飲み書店員大賞を受賞。2013年『謎の独立国家ソマリランドそして海賊国家プントランドと戦国南部ソマリア』で第35回講談社ノンフィクション賞、第3回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞。
- 小倉ヒラク(おぐら・ひらく)
- 発酵デザイナー。「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指し、全国の醸造家たちと商品開発や絵本・アニメの制作、ワークショップを開催。東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、山梨県甲州市の山の上に発酵ラボをつくり、日々菌を育てながら微生物の世界を探求している。絵本&アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014受賞。2015年より新作絵本『おうちでかんたん こうじづくり』とともに「こうじづくりワークショップ」をスタート。のべ1000人以上に麹菌の培養方法を伝授。自由大学や桜美林大学等の一般向け講座で発酵学の講師も務めているほか、海外でも発酵文化の伝道師として活動。雑誌ソトコト『発酵文化人類学』の連載、YBSラジオ『発酵兄妹のCOZYTALK』パーソナリティも務めている。
- 取材・文:萩原 雄太(はぎわら・ゆうた)
- 1983年生まれ、かもめマシーン主宰。演出家・劇作家・フリーライター。早稲田大学在学中より演劇活動を開始。愛知県文化振興事業団が主催する『第13回AAF戯曲賞』、『利賀演劇人コンクール2016』優秀演出家賞、『浅草キッド「本業」読書感想文コンクール』優秀賞受賞。かもめマシーンの作品のほか、手塚夏子『私的解剖実験6 虚像からの旅立ち』にはパフォーマーとして出演。
- 撮影:加藤 甫