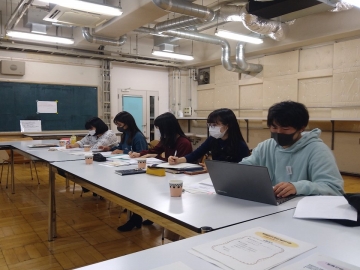「普通の友達とは違った“ななめの関係”の難しさ」
公認サークル「早稲田大学広域BBS会」
前会長(※) 人間科学部 3年 村瀬 莉佳(むらせ・りか)
前副会長(※) 法学部 3年 武内 瑞月(たけうち・みづき)
(※)早稲田大学では公認サークルの「会長」は教職員が務めるが、それとは別に、BBS会では学生が務める「会長」「副会長」を設け、法務省保護局の更生保護協力団体として活動する際などに会員の統括を行っている。

(左から)村瀬さん、武内さん
さまざまな生きづらさを抱えた子どもたちに「お兄さん・お姉さん」として寄り添い、勉強を教えたり、話し相手になる活動を行っている「早稲田大学広域BBS会(※)」 (以下、BBS会)。この秋、更生保護活動に顕著な功績のあった個人や団体に贈られる第23回「瀬戸山賞」を受賞しました。今回は2020年度に会長を務めた村瀬さんと副会長を務めた武内さんに、活動を始めたきっかけや普段の活動内容、今後の目標などについて聞きました。
(※)BBSは、Big Brothers and Sisters Movementの略。
――BBS会ではどのような活動を行っているのですか。
村瀬 BBS会の活動は大きく分けて三つあります。一つ目は最も古くからある「ともだち活動」です。ともだち活動では、保護観察所や小中学校、保護司などからご依頼をいただき、少年少女1名に対し会員1~2名が付き、中長期にわたって交流します。少し年上の「ともだち」として学習指導をしたり一緒に遊んだりしながら、自立支援を目指しています。また、ともだち活動に付随した「グループワーク」という活動では、保護観察を受けている少年少女や、地域の子どもたちを招待し、会員が企画した料理やゲームなどのレクリエーションを実施しています。
二つ目は、「健全育成活動」です。児童福祉施設や児童館などの施設を訪れ、話し相手になるだけでなく、学習支援や授業補助も行います。コロナ禍以前は、地域のお祭りでのお手伝いなどもしていました。
三つ目の活動は「自己研鑽(さん)活動」です。月に1回、更生保護や児童虐待について学び、理解を深めるために勉強会を行っています。専門家をお呼びするだけでなく、会員自身が講師を務めることもあります。コロナ禍においてはオンラインでの開催も多いです。
写真左:健全育成活動の様子。2019年9月に行われた江東区民祭りに参加し、子どもたちへ風船を配る手伝いなどをした
写真右:自己研鑽活動での勉強会の様子
――お二人がBBS会で活動を始めたきっかけを教えてください。
村瀬 私の場合は、大好きな刑事ドラマがきっかけです。刑事ドラマでは捜査や逮捕の様子までは出てきますが、罪を犯した人がその後どのように罪を償うのか、社会に戻っていくのかについて疑問に思っていました。そこで大学入学時、そのような人たちや、生きづらさを抱えた人たちと関わる活動をしてみたいと考えていたところ偶然BBS会を見つけ、入会しました。
武内 私はもともと更生保護に興味があったわけではありません。他のサークルの新歓で知り合ったBBS会の先輩からチラシをいただいたことがきっかけです。BBS会の活動は、子どもと関わることが大好きな私にとってとても魅力的で、入会を決めました。
村瀬 他の会員の入会理由もさまざまです。将来、更生保護や児童福祉に関わりたいという思いから参加する人もいれば、大学で専攻している教育学や心理学の学びを生かしたい人、ボランティアに興味があって入会する人もいます。
――子どもたちとの関わりで気を付けていることはありますか。
村瀬 普通の“ともだち”になることを心掛けています。活動で関わる子どもたちは、保護司や保護観察官と接する機会は多くありますが、私たちの役目はそうではなく、同じ目線で関わり、世代の近い友達としてなんでも相談できる存在になることだと思っています。関わりの中では、子どもたちの意見を否定しないことにも気を付けています。
武内 私も、実際の友達と同じように接するようにしています。「ボランティアの人が来た」とは思ってほしくないので、言葉遣いや声色も友達と接するときと同じようにすることを意識しています。とはいっても、子どもにとってBBS会の会員との関係は、親や先生との縦の関係や自然にできた友達の横の関係とも異なる“ななめの関係”です。普段周りにいる人とは異なる立場であり、子どもたちにとって新たなつながりを増やすことができる、ななめの関係を維持することも気を付けていますね。
2020年1月のグループワークでの様子。少年3名とBBS会会員5名でスポーツレクとバーベキューを行った
――BBS会での活動の中で印象に残っているエピソードはありますか。
村瀬 私は、児童福祉施設で授業補助として参加していたときのことが印象に残っています。虐待を受けたことがある子と連続して関わる機会があったのですが、最初、その子は誰に対しても発話、反応がなかったんです。でも、回数を重ねるごとに少しうなずいたり反応を示してくれるようになり、最終的には言葉を返してくれて、表情も明るくなりました。その子との関わりは、一人一人に寄り添うことの重要性を感じた出来事になりましたね。
武内 活動の中で少年院に見学へ行き、入所している少年と話す機会があったのですが、その少年に「なぜ僕たちのような人と関わるような活動をしているの?」と聞かれたことです。自分としては、友達として接しているつもりでも、その少年にとってはたくさんいる大人の一人でしかなかったのです。少年と同じ目線に立つというのは、口で言うのは簡単ですが、本当の意味で友達と思ってもらうのはとても難しいのだと痛感しました。この経験以来、どうしたら気を許せる友達だと思ってもらえるかを常に試行錯誤しています。
――BBS会が、日本更生保護協会によって創立された瀬戸山賞を受賞したと聞きました。
村瀬 今回の受賞は長年の活動を認めていただいた結果なのかなと思います。ただ、受賞のきっかけとしては、2月に開かれた法務省主催の「京都コングレス・ユースフォーラム」への参加があると思います。この会議は、5年に一度の犯罪防止・刑事司法分野における国連最大の国際会議「国連犯罪防止刑事司法会議(コングレス)」に先立ち、世界の若者たちが、コングレスの議題に関連したテーマについて議論を行うものです。今回は、来場参加とオンライン参加を併用したハイブリッド方式で行われ、世界中の人が集う場でBBS会の活動内容を発表できたことは有意義でした。
写真左:「京都コングレス・ユースフォーラム」の様子。早大BBS会からは、古門華子さん(文学部4年)がオンラインで参加した
写真右:瀬戸山賞の賞状と表彰盾を授与された際の写真(左から2人目が村瀬さん)
また、昨年11月に「社会を明るくする運動(※)」の一環で行われた、吉本興業の芸人の皆さんと全国のBBS会がコラボした「もっと知ってほしい! BBS会」というイベントに参加したことも大きかったと思います。イベントの企画段階から当日の登壇まで、早大BBS会の会員10名以上が参加しました。イベントでは、芸人の皆さんがBBS会の活動を基に作ったコントや、BBS会会員とのトークコーナーもありました。このイベントを含めた広報活動が、更生への理解を得られるきっかけになっていたらうれしいですね。
(※)すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動。
写真左:吉本興業とのイベント「もっと知ってほしい! BBS会」での集合写真
写真右:イベント準備期間の様子。約1カ月間、吉本興業の芸人や構成作家、法務省の方々と一緒に打ち合わせを重ねた
武内 今年9月には、吉本興業所属の「3時のヒロイン」の皆さんと早大BBS会がコラボした動画も制作されたのですが、私はそこに出演しました。テーマは「ともだち活動」についてだったのですが、一つ一つの活動に対し3時のヒロインの皆さんが熱心に聞いてくださったのが印象的でした。更生保護は社会の中で隠れた存在になりがちですが、このように芸能人の皆さんとオープンな場所でBBS会の活動内容をお話しできたことをとてもありがたく思っています。
武内さんも出演した吉本興業とのコラボ動画。その後、3時のヒロインがBBS会に関するコントを制作
――今後、BBS会での活動をどのように生かしていきたいかを教えてください。
村瀬 どんな仕事に就いたとしても、見た目やレッテルで人を判断せずに、会話を通して本質を見極めることを大切にしていきたいです。BBS会の活動では、人それぞれに生育歴や現在身を置いている環境など、目には見えない背景があることを学びました。人の表面的な部分だけでその人を判断してしまうと、その人の本当の良さを見抜けないように思います。一人一人と向き合って、関係を構築できるように、また、どんな人と接するときにも、「こんな考え方もあるよね」という柔軟な思考を持てるような人になりたいです。
武内 BBS会の活動を通して、家庭に問題があったり、生きづらさを抱える子どもたちと接してきましたが、実際の社会にはこのような子どもたちがもっとたくさんいるのではないかと思います。町や電車で見かける子どもに対しても、困っている様子を見たらすぐに手を差し伸べられる大人になりたいです。また、どうしても私たちは、自分と違う特性や過去を持っている人に対し、偏見や先入観を抱きがちだと思います。そうならないよう、BBS会での経験や得た知識を生かして、新しい人との出会いを大切にし、交流の輪を広げていきたいです。
第803回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
人間科学部 2年 佐藤 里咲
【プロフィール】
村瀬莉佳:徳島県出身。徳島文理高等学校卒業。人間科学部では、臨床心理学を専攻し認知行動療法について学んでいる。趣味はフルートやピアノの楽器演奏をすること。
武内瑞月:神奈川県出身。横浜雙葉高等学校卒業。法学部では、家族法について学んでいて、特に養子縁組についての勉強はBBS会での活動にも役立ったと話す。趣味は、観葉植物を育てること。

二人が所属する公認サークル「早稲田大学広域BBS会」の現在の会員数は約140名。コロナ禍では従来の対面型の活動を行うのは難しく、「ともだち活動」のグループワークをオンラインで行うなど、工夫しながら活動を続けている