型 にハマるな、型を使え! ラップと短歌が教える“型”の創造力言葉のスペシャリストとして、これまで
ピン芸人として活動しながら、短歌も作っています。YouTubeに投稿した「水道水の味を説明する」 が話題になって、2024年11月にそれを基にした書籍も出版しました。最近は歌人や作家として紹介されることも増えてきたんですけど、芸人になるまで「言葉のスペシャリスト」という自覚は全くなくて。それこそ大学時代はアカぺラサークル「Choco Crunch」 (公認サークル)で、歌ったりボイパをやったり、「非テキスト的」な時間を過ごしていました。だから今その空白を埋めるように、やっと赤ちゃん言葉を喋り始めたみたいな感覚で、言葉と関わっている気がします。
鈴木ジェロニモさんの大学時代の写真。本人いわく「間違えて就職しようとしていた大学3年生のときの写真」とのこと
もともと僕はバンド活動をしていて、高校生のときにラップに出合いました。バンドは基本的に既存の曲をコピーして練習することが多いんですけど、ラップには「カバーする」という概念がなくて、最初からオリジナルの歌詞を書いて曲を作るんですよ。だからラップに出合った瞬間、2時間後にはもう自分の曲ができていた。「これ、俺の曲なんだ」という感覚が本当に衝撃 でした。そのままラップにのめり込んで、大学卒業して社会人を何年か経験した後、メジャーデビューをきっかけに音楽一本で活動するようになりました。
KEN THE 390さんの大学時代のひとコマ(写真左上)。ソウルミュージック研究会GALAXYで音楽活動をしていた
鈴木ジェロニモさんの大学時代の写真。本人いわく「間違えて就職しようとしていた大学3年生のときの写真」とのこと
KEN THE 390さんの大学時代のひとコマ(写真左上)。ソウルミュージック研究会GALAXYで音楽活動をしていた
韻を踏んで歌詞を書くのは難しそうな
「韻を踏む」行為は確かに縛りなんですけど、それがあるから歌詞が書けたと思っています。白紙のページを渡されて、「君のありのままの気持ちを書いて」と言われても、正直何を書けばいいか分からないじゃないですか。だけど自分の名前を書いて、「この言葉に韻を踏んでみよう」と考えたら、そこに一つの「ルール」が生まれますよね。「この言葉に韻を踏める言葉にはこれがある」みたいに、韻を踏むことで自分のイマジネーションを超えて言葉が降ってくる感覚になるんですね。
めっちゃ勝手に僕自身の物語のように聞いてました(笑)。短歌も「五・七・五・七・七」の型があるからこそ言葉が引っ張り出されてくる。もちろん書いているのは自分ですが、「短歌に呼び出された自分の言葉」というイメージです。型によって短歌への愛情が深まるというか、短歌と自分とのコミュニケーションの中に言葉が置かれる 感覚があります。
お二人の話を伺っていると、「型」の重要性と、だからこそ言える「型破り」の面白さということ、そして型を破る場合でも、その根底には何らかの原理がある 、ということに思い至ります。「型」にもいろんなレベルがありますが、まず、「型」があることで表現しやすいという側面はありますよね。自由に表現しろ、と言われるとかえって難しいものです。その上で「型」を破った表現というものが面白くなっていきます。例えば自由律俳句の種田山頭火の「水のうまさを蛙鳴く」など、通常の文法から逸脱しているからこその面白さがあります。ただし、単なる逸脱ではなく根底には文法の原理が通底していることも面白い と思います。
言 葉にリズムを刻む! 日本語のラップは韻やリズムで言葉を伝える
ヒップホップやラップは、アメリカで生まれた英語のカルチャーなので、僕らはそれを日本語に翻訳するっていう感覚が強くありますね。例えば、日本語は1文字に1音節を使うじゃないですか。英語だと「Pop」と「Top」のように韻を踏んでも短く聞こえるけれど、日本語では「ぽ/っ/ぷ」「と/っ/ぷ」みたいに1文字が必ず1音節になるので、どうしても韻を踏むまでが長くなります。日本語でするラップはそれが嫌で、もっと短くて英語っぽい響きを作りたくて、舌を丸めたり、母音を強調して韻を踏んだり、ラッパーたちがいろいろな工夫をしてきました。
具体的にはどんな踏み方
「OK」 という曲では「ゴールは独壇場/濃くなるよ/ボーイズバンド」と韻を踏んでいます。ここで「ボーイズバンド」の「ン」を発声しないとか、「イ」を弱めるとかして「ボ」の「OU」にアタックが入るようにすることで、「GOU RU」、「DOKU DANJOU 」、「KOKU NARUYO 」、「BOU IZU」がライム(韻)に聞こえてくる、みたいな。他にも「次元が違う」と「リテラシーが」は韻を踏んでいるように全く聞こえないんですが、「JIGE」「RITE」にアクセントをそろえると…。
おお、すごい! 確かに聞こえます。萩原朔太郎(詩人)に教えてあげたら涙を流して喜ばれたかもしれません。彼は日本語の詩は韻を踏むことが難しいから冗舌に表現できないということを書いているんですが、ラップのように発音を工夫すれば、無限の可能性が出てくるのですね。
日本語のリズムが伝わり方に大きく影響
日本の盆踊りは「タタン・ガ・タン」のように、頭でリズムを取るじゃないですか。それはKENさんがおっしゃっていた、区切りやオチで韻を踏む感覚に近くて、日本人は「ここで区切れる」ことを心地よく感じる傾向があると思います。同じように、お笑いのコミュニケーションでも、常に面白いことを言い続けるより、「どこでオチるか」が明確に分かった方がウケる んです。面白い言葉を100個並べるより、90個は普通の言葉で、最後の10個だけ面白い方が伝わりやすいこともありますね。
刺 さるパンチラインは言葉を伝える上で、
ラップで大事なのは「サプライズ」 だと思います。リリック(歌詞)でもMCバトルでも、どれだけリスナーがその言葉に驚けるか。そのためには飛躍したワードを選ぶことも必要ですけど、同じように「考えさせる間」を作ることが大切 なんですね。
(※)上述した「OK」の歌詞なら「独壇場」「濃くなるよ」などがそれぞれオチの1小節になる。
いやぁ、すごくよくわかります! 私たちは予想をしながら聞いていることが多いので、いい意味でそれを裏切らないと面白くなりません。でも、いきなり飛躍するわけにもいかないから、さりげなく土台も作る。そういう点で、話の構造というものは非常に重要 だと思います。プレゼンや論文などでも同様です。さらに、パフォーマンスで言えば、「音」そのもの、例えば言葉の中のポーズ(間)を少しあけるとか、強弱を付けるとかいったことも、構造とも関わって大切ですよね。こうしたことは、学生の皆さんも意識するといいと思います。
それでは、どんなパンチラインが
フリースタイルは不思議なもので、MCバトルのときに「このパンチラインで絶対にお客さんが沸くだろう」と思って準備してきたフレーズでも、少しでも用意してきた感じが匂うと、全く沸かなくなるんですよ。逆に、本当にその瞬間にひらめいた言葉だと一気に盛り上がる。それが過去に踏んだことのあるライムでも、今この瞬間に取り出したという感覚は聞いている人にも伝わるんです。
その感覚はとても納得できますね。僕の場合は「伝わる」ためには、自分自身が裸であることが一番大事だと思っています。「こう言おう」「こう思われよう」と意識した言葉はあまり伝わらない 印象で。
僕も「正直であること」を一番大切にしていますね。もう一つ、ラップにおいて伝わる言葉を考えたときに、「発言者の背景が明確になっていること」も大事 だと思うんですよ。例えば、よくラッパーはストリートのイメージからか、「お母さんありがとう」というリリックを書いて揶揄されることがあります。でも、特に経済的に苦労なく早稲田大学を卒業した人が言うのと、一人親に育てられて、奨学金を得てギリギリの生活の中卒業した人が言う「お母さんありがとう」では、響き方が全く違うじゃないですか。
確かに、その言葉に人生が乗って
ラップでは言葉を丸くしたらダメなんです。自分と母親の間にあった歴史をこと細かく具体的に言葉にして、「お母さんありがとう」と言えば、ちゃんと心に刺さる。それがラップの魅力なんです。
言 葉の“脱臭”を防ぐために“伝わる言葉”の力を磨きたい学生が、
KENさんが言っていた「お母さんありがとう」の文脈やバックグラウンドが大事という話にすごく共感しました。というのも、「言葉を大切にして言語化しよう」の行き着く先は「脱臭」に近いと思うんですよ。「自分の言葉からどうやって匂いを消すか」ということです。でも、僕は逆に「どうやって自分の匂いが付いた言葉を言えるか」が勝負 だと思っていて。その匂いを自覚して、言葉に乗せられた方が、「自分の言葉」として伝わりやすくなります。
そうした「自分の言葉」を持つために
僕が言葉に悩んでいる人に言いたいのは、「裏アカを充実させろ」 です。本アカでは、「今日ライブあります。ぜひ来てください」とポストして、裏アカでは「本当は出たくないんだけど、ギャラが良いから出ることにした」とか、表では言えないことを書く。自分が本当に感じてるけど人前では言えないこと、つまり人には嗅がせたくない自分の匂いを知っておくことが、言葉に向き合う上で、実は捨てない方が良い部分なのだと思います。
大 切なのはインプットより編集力。豊かな言語表現を身に付けるためには
インプットをして語彙力を増やす必要があると言われがちですが、僕はそれよりも「編集力」の方が大事だと思っています。同じ話でも話す人によって受け手の印象は全然違います から。お笑い芸人さんの話を聞くとか、バラエティー番組を見ている方が、自分にとってはインプットとして役立つことが多いです。
僕も編集力が大切だと思います。僕流に言うと「言葉の関節を外す力」 です。しょっぱいものを食べたとき、「海辺の岩に付いている塩の味がする」と言えば伝わりやすい。でもあえてその言葉の関節を全部外して、「岩の味がする」と言った方がドキッとしませんか? 実際に自分が感じたのは「岩の味」だと思ったら、余計な説明を加えずにそのまま言ってみる。31音の制約がある短歌は関節の外し方の宝庫なので、そうした言葉に触れて、関節を外すことへの恐怖心をなくしていくことをインプットとして捉えるのが僕は好きですね。
それと、アンテナが立っているかどうかも大事 だと思います。例えば「自分のラップに何が必要か」というアンテナが立っていると、意識的にインプットしようとしなくても日常のどんなものからでも自然に引っ掛かってきて、「これ、次のラップに使えるな」と感じられるんですよ。反対に、そのアンテナが立っていないと、何を見ても全部スルーしてしまう 感覚がありますね。
お二人のお話、本当に共感します。よく語彙力が大切と言われますが、実はさらに大切なのは「表現を組み立てる力」です。そういう力を付けるために、ジェロニモさんやKENさんは、普段の生活でも、少し距離のある比喩を使ってみようとか、別の感覚で共感覚的に表現してみようとか、この表現と別の表現とどちらが良いか考えようとか、そんな分析的な視点を、意識的に、あるいは無意識に、常に持っていらっしゃるのではないでしょうか。そういった「表現について考えるというアンテナを立てること」 は、日本語学の研究はもちろん、芸能界でのご活躍でも、学生の皆さんの普段のコミュニケーションでも、非常に重要 だと感じています。
AI が「正解」を生むなら、SNSの影響でテキストの
SNSで自分を表現するときは、「(言葉の使い方を)間違えたらどうしよう」と感じてアウトプットにブレーキがかかりやすいかもしれません。でも、生成AIが出てきて「正しい風な」文章は誰でも書けるようになるわけじゃないですか。そう考えると、自分の力だけで完璧に正しい日本語を書くことに、そこまで価値があるのかな? と疑問に感じます。だから正しい言葉よりも、間違えることの危うさを引き受けた正直な言葉、自分が本当に思ったことを素直にアウトプットする勇気に価値が生まれる時代 になると思いますね。
僕も自分の「匂い」、あるいはどう間違えているか、どんな勘違いをしているか、ということに目を向けたいです。例えば、夜空の星はすでに存在しているけれど、星の並びを「星座」として結んだのは人間です。「さそり座」なんて、実際には全然さそりの形をしていないのに、そこにあえて「星座」を描くような行為にこそ、人間らしさが表れているんです。だから星の並びを直線で結ぶような効率的な作業はAIに任せて、自分だけの「星座」を描くような文章や文体を目指すのが良い のかなという気がします。
間違いを引き受ける勇気や、自分と
ラップに限らず、自分で詩や歌詞を書く行為は、それ自体にデトックス効果があると思います。歌詞を書くことで自分自身がその言葉に励まされたり、モヤモヤした気持ちが吐き出されて楽になったりする。仕事としてではなくても、自分が生きていく上で大事な行為だと思うので、みんなにもそういう感覚を1回味わってみてほしいですね。
歌人の穂村弘さんは著書『はじめての短歌』の中で、平岡あみさんの「大仏の前で並んで写真撮る私たちってかわいい大きさ」という短歌を「大仏の前で写真を撮る私たちってとても小さい」に書き換えると、詩的な価値が一気に失われてしまうと言っているんですね。「とても小さい」は社会的な価値を伝える言葉で、自分の思い込みや感覚を伝える要素が排除されてしまうから。今では実際に思ったことを書こうとするとAI的な正しい日本語が入り込んで脱臭されがちになるわけですけど、それに流されず、意識的に匂いを付けようとする行為が詩を書くこと なのだと思います。
匂 い立つ私の体臭、最後に学生に向けた
大学時代は「大学デビュー」や「あか抜け」と言われるように「脱臭」が進む時期。あか抜けて自分の身体が社会的な存在になるのは良いことですが、「それでも消えない自分の匂いは何だろう?」と考えていくことで、自分を悩ませる「言葉にできないもの」の根幹に近付けると思います。だから、「言葉まで脱臭させないで」 。それが僕からのメッセージですね。
何かをアウトプットするときは「これが好きだ!」という強い気持ちが原動力になります。学生時代は自分に合うものを探す良いタイミングでもあると思うから、まだ自分の「好き」が見付かっていないなら、広く、薄くいろんなものに触れてみてください。そして「好き」が見付かったら恥ずかしがらずに表現する こと。いきなり完璧になんて絶対できないんだから、気楽に構えてアウトプットすることが大切だと思います。
やはりたくさんアウトプットしていくことでアウトプットの力が付くものだと思います。そして、表現することに対して「好き」になっていただきたいです。泥臭くていいので、どんどん表現していくことを楽しんでほしいですね。また、いろいろな表現に触れ、自分を広げることも大切です。「型」を破るためには、さまざまな「型」をある程度身に付けておくことも必要でしょう。さらに、言葉に立ち止まって少し分析的に考えてみることもきっと役立つはずです。大切な学生時代、幅広く学んだり挑戦したりしながら、いろんな「表現」を、また、「表現する自分」を思いっきり楽しんでください。


![KEN THE 390(けん・ざ・さんきゅーまる)[写真左]、鈴木ジェロニモ(すずき・じぇろにも)[写真右]、森山卓郎(もりやま・たくろう) 文学学術院教授[写真中央]](https://www.waseda.jp/inst/weekly/assets/uploads/static/specialissue-gengoka/img/img-3shot-pc01.jpg)

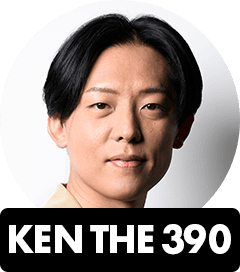
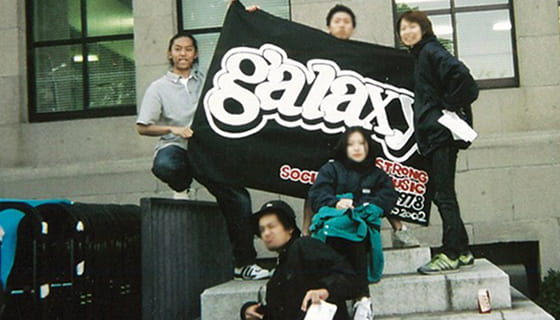


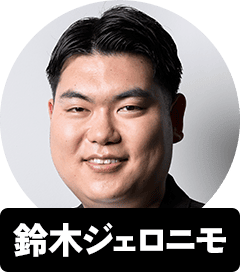


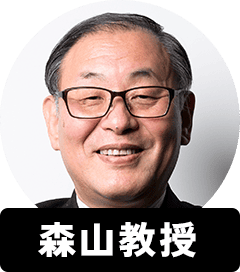
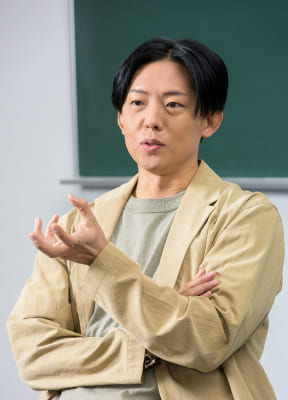









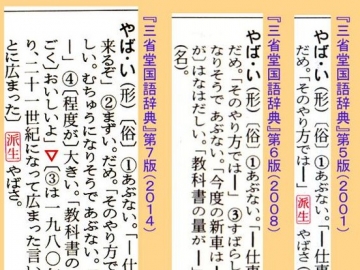


ピン芸人として活動しながら、短歌も作っています。YouTubeに投稿した「水道水の味を説明する」が話題になって、2024年11月にそれを基にした書籍も出版しました。最近は歌人や作家として紹介されることも増えてきたんですけど、芸人になるまで「言葉のスペシャリスト」という自覚は全くなくて。それこそ大学時代はアカぺラサークル「Choco Crunch」(公認サークル)で、歌ったりボイパをやったり、「非テキスト的」な時間を過ごしていました。だから今その空白を埋めるように、やっと赤ちゃん言葉を喋り始めたみたいな感覚で、言葉と関わっている気がします。