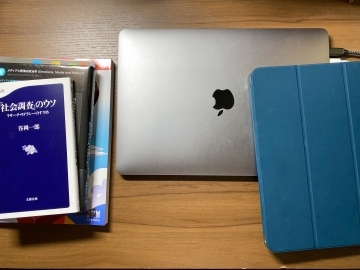ニュース記事やTwitter投稿のテキストから人々の感情を分析する
大学院政治学研究科 修士課程 2年
政岡 良祐(まさおか・りょうすけ)
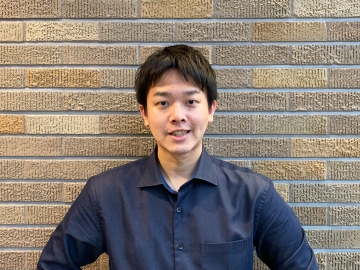
私は、大学院政治学研究科のジャーナリズムコースに在籍しています。では、大学院でジャーナリズムを学ぶと聞くと、どのようなイメージが浮かぶでしょうか。取材をしてニュースを届ける様子や、時事問題について専門的な知識を用いて議論や分析を行う様子などさまざまだと思います。
私は学部で社会学を学んでいましたが、日常生活の大部分がマスメディアやSNSなどのソーシャルメディアに依存していることに問題意識を抱き、ジャーナリズム専攻の大学院に進学しました。コロナ禍でオンラインの活動が急増した体験も大きなきっかけでした。「マスメディアの情報発信について考えたい」、「ソーシャルメディアでの感情の広がりを分析したい」という気持ちが自分の中にあったのだと思います。
私が取り組んでいる研究は、マスメディアとソーシャルメディアの分析です。それぞれ主にニュース記事とTwitter投稿を材料に、人々の感情を理解することを目指しています。具体的には、分析プログラムを使用してテキストから感情表現を抽出し、分析します。私たちが抱く感情は、機械的に判断できないニュアンスを含んでいます。しかし、大量のテキストを分析することで、記者や投稿者の手を離れた文章が、社会で他の読み手に対してどのような感情を与えているのかを概観することができます。例えば、Twitterではトレンド機能により今注目されている話題を知ることができますが、その感情バージョンのようなものをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
私の研究は2020年のコロナ禍を対象としています。当時のニュース記事とTwitter投稿を分析するとそれぞれネガティブな単語が多く使われ、社会に不安が広がっていた様子が分かります。しかし、同じネガティブな単語でも、ニュース記事では「懸念」や「深刻」のように社会の様子を伝える言葉が多く、Twitter投稿では「いや」「迷惑」など、気持ちをストレートに表す言葉が多く見られます。特に、Twitter上では報道機関の公式アカウントに対するリプライ等で、ニュースの受け手が強い感情を発信している様子が分かります。私はマスメディアとソーシャルメディアの両方に目を向け、それぞれの感情発信の違いを明らかにすることで、社会に不安が広がるプロセスを知ることができると考えています。
写真左:作業用デスク。集めた論文や資料はタブレットで管理し、メモもそこに書き込んでいます
写真右:研究でよく使用する、早稲田キャンパス 3号館地下1階の李健熙(イゴンヒ)記念図書室(政治経済学術院研究図書室)前のフロア。
研究を始めると、私たちのソーシャルメディアでのコミュニケーションが非常に短い表現で成立している不思議さと、その断片的な情報で心情が大きく揺さぶられる危うさをあらためて感じました。一方、マスメディアでは、オンライン記事の場合、取材をした記者と記事を配信するデジタル部門の担当者とでは考えや権限に違いがあるなど、さまざまな実情の中で記事が発信されるため、報道の姿勢や表現を単純に批判することはできない難しさも知りました。これらを踏まえ、コロナ禍の感情分析を修士論文にまとめる予定です。
いつでも誰とでもつながれる社会は、同時に恐怖や怒りなどの強い感情を瞬く間に広げてしまう危うさを秘めています。ソーシャルメディアを使ったコミュニケーションでは、こうした性質を忘れないことが重要だとあらためて感じます。自分自身も将来は、大学院での経験を踏まえて、オンライン化が進んだ社会で人々の生活に貢献したいです。

ジャーナリズムコースの同期との夕食。いろいろな経験をしている人が多く、刺激になります
ある日のスケジュール
- 09:00 起床
- 09:30 朝食
- 10:00 作業予定やスケジュールの確認、メール返信、家事、ジョギングなど
- 12:00 昼食
- 13:00 授業に出席(授業は対面、個別面談や研修会などはオンラインということが多いです)
- 15:00 大学図書館で作業(文献探し、課題提出、報告資料作成など。大学院生のみが閲覧できる資料もあり、修了生の論文なども調べられます)
- 19:00 夕食
- 20:00 TV・インターネット視聴、読書など
- 21:00 入浴
- 22:00 研究作業、データ収集等(手作業で集めるデータもあるので、夜の時間にまとめて進めます!)
- 26:00 就寝