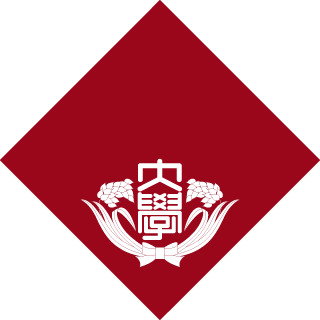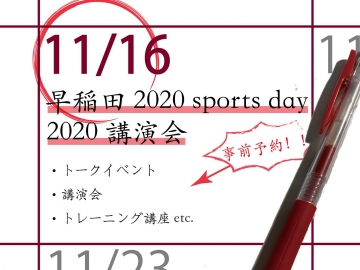VIVASEDAでは、日本パラバレーボール協会の真野嘉久会長にインタビューしました!
プロフィール

真野 嘉久(まの よしひさ)
東海大学体育学部卒業。1997年に日本シッティングバレーボール協会会長就任後、現在まで会長職と男女シッティングバレーボール日本選手団の監督を兼務。これまで、パラリンピック4大会で監督を歴任。
真野会長はどのようにシッティングバレーボールと出会われたのですか?
サラリーマン時代に、シッティングバレーボールを見に行ったら、夢中になってしまいました。学生時代にバレーボール選手として活動しており、当時は垂直跳びで100㎝跳べました。しかし、サラリーマン生活で体重が増えてジャンプできなくなってしまい、バレーボールから遠ざかっていました。しかし、シッティングバレーボールのルールだとジャンプは禁止されているので、ケガが心配でも問題なく競技を楽しむことができます。そこで「シッティングバレーボールは自分にぴったりのスポーツだ!」と思いました。また、健常者も障がい者も一緒になって競技している様子を目の当たりにして、衝撃と感動をおぼえたことも、熱中した理由の一つです。
シッティングバレーボールの普及に関してどう思いますか?
今は認知度が低いですが、東京大会を機に認知度を上げたいと考えています。東京大会でメダルを取って認知度100%にできることを目指して、頑張っています。
また、特に子ども達に障がい者スポーツを教えており、コロナウイルスの拡大前は、年40回小学校で出張授業を行っていました。障がい者スポーツを子どもの頃に知っておくことで、大人になった時に、障がい者のことや障がい者スポーツを受け入れやすくなると考えています。さらに、障がい者スポーツの特徴の一つに、高齢になってもできるということがあります。私たちは、障がい者スポーツが「一生涯スポーツ」になるように活動しています。

体験会で意識していることや伝えたいことはありますか?
体験会では、「失われたものを数えるな、残された機能を最大限に活かせ」と伝えています。一般の人や子ども達には、「生の現場を知ってもらう」ことを大事にしています。つまり、選手を知ってもらうということを大事にしており、選手に親しんでもらえれば、たとえルールや競技がわからなくても楽しめると考えています。
また、シッティングバレーボールは、健常者も障がい者もはじめはうまくできません。シッティングバレーボールは車いすのような特別な道具を使わずに床に直接座って移動します。日常生活では健常者の人も障がい者の人も、床に直接座って動く経験はあまりありません。そのため、全員で「どうやったらうまく移動できるか?」と一緒に考えることができる、という魅力を伝えるようにしています。
体験会で大変なことは、一般の体験会だと、幼稚園児から80歳のお年寄りまでいらっしゃいますので、幅広い年代の参加者全員に興味を持ってもらうことが大変です。大変ではありますが、また参加したいとリピーターの方が来てくれることがあり、その時はとても嬉しいです。
今、コロナウイルスによって困っていることはありますか?
合宿や大会を開催できなくて、大会を目標にしてきた人が悲しい思いをしていることが辛いと感じています。
しかし私はこの状況を試練と思い、下を向くことなく乗り越えようと思っています。今だからこその新しい取り組みとして、岩手県陸前高田市の子ども達とオンラインのリモートで、シッティングバレーボールの教室をやる予定です。

インタビューを終えて ~VIVASEDAメンバーからのメッセージ~
コロナウイルスの感染が収束したらシッティングバレーボールの体験会に行ってみませんか? 再開の際は、協会のHPで情報が確認できます。とても面白そうなので、VIVASEDAでも参加してみたいと思いました!