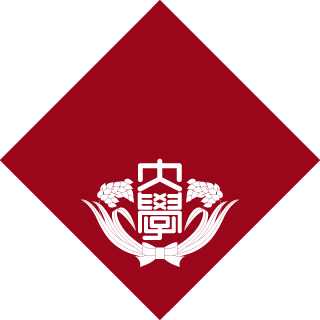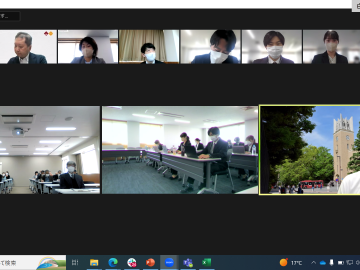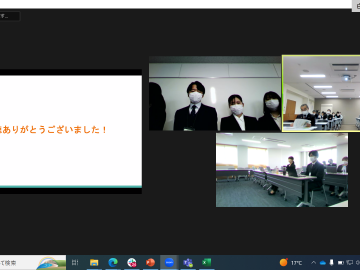【活動概要】
木島平村との地域連携ワークショップは2009年に始まって以来、今年度で14回目の実施となりました。今年のテーマは『子育て世帯が住みたい田舎No.1 になるための施策を考えよう』少子高齢化が進み、人口維持・人口減少の鈍化が村の大きな課題の一つである木島平村。参加学生10名(5名×2チーム「白鷹革命」「きじまっ子ふやし隊」)は木島平村が抱える課題解決の糸口となるような提案をするべく、約2か月間にわたるワークショップに取り組みました。(ワークショップは新型コロナウイルス感染症対策を施した上で、基本的には対面形式での実施となりました。)
【活動の様子】
■オリエンテーション(1/26):
本ワークショップのキックオフとなるオリエンテーションでは、来校した木島平村役場担当者より、今回のテーマおよびその背景について説明いただきました。この日初対面となった学生たちは、学年や学部もバラバラな学生が集まっていることに、驚きながらも自己紹介を進め、その中で意外な共通点などを見つけ合い、穏やかな雰囲気でのオリエンテーションとなりました。

■ フィールドワーク(2/20-23)
フィールドワークは現地に直接おもむき、地域住民やテーマに関連した役場担当者、関係企業の方々などに学生がヒアリングすることのできる貴重な機会です。2020、2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しオンラインによるヒアリングとなりましたが、今回は感染対策を徹底した上で、3年ぶりに木島平村を訪問し、日䑓村長との懇談をはじめ関係者へのヒアリング、また村内及び近隣市町村の観光施設を巡ることもできました。
ヒアリング対象者は、村のサッカークラブに所属する小学生や村内の高校生、担当業務別に参加いただいた村役場担当者、実際に木島平村に移住した方を含めた子育て世代や高齢者といった地域住民の皆様、教育長や保育園長など多岐に渡り、各回学生がファシリテートしてインタビューを実施しました。ヒアリング開始当初は予め準備してきた質問を投げかけることで手一杯の様子でしたが、次第に質問への回答に学生自身の考えや追加の質問を投げかけるなど、会話の流れに沿って柔軟にやりとりし、ヒアリング対象者の言葉の真意を深堀りできるようになりました。
現地調査中は農村交流館に宿泊し、その日のうちに、様々な方からお話いただいた内容を振り返り、チーム間、メンバー同士で意見交換を実施しました。
■ チームミーティング(2月~3月)
チームメンバーでお互いの時間を調整し、基本は対面で集まりつつ、オンラインも活用しながら、アイディア出しや意見交換など活発に行いました。時には職員からの助言も受け、次第にチームの雰囲気もできあがり、より円滑な議論が進んでいきました。課題を設定し、仮説検証を行いながら着実に提案をつくりあげていく過程は、苦しいながらも楽しい時間となったことでしょう。また、木島平村について調べるうちに村への愛着もわいてくるのも、このワークショップの醍醐味です。「もう一度、村へ行って関係者の生の声を聞いてみたい!」という声も多く聞かれました。
■ 中間報告会(3/6)
木島平村役場担当者4名に来校いただき、2チームの提案を対面で直接プレゼンできる機会となりました。中間報告ということで各チームともその時点での提案方針を示すこととなったため、提案内容の具体性には改善の余地が見受けられましたが、役場担当者の方々からは親身に講評、フィードバックをしていただけました。中には厳しいご意見もありましたが、2チームとも、最終報告会に向けてどうすればよりよい提案につなげられるかと前向きに考えている様子がうかがえました。
■ 最終報告会(3/20)
チームメンバーで時間をかけ、何度も見直しを加えながら練り上げてきた企画を発表する最終報告会。当日は大学会場と木島平村会場をオンラインでつなぐハイブリッド形式での実施となりましたが、木島平村会場には日䑓村長はじめヒアリングに参加いただいた方々にも参加いただけました。
白鷹革命は子どもの非認知能力を伸ばすことで親の満足度を高める施策を、きじまっ子ふやし隊は移住希望者への村内生活体験ツアーや農村交流館の施設面の改善案を提案し、2チームともフィールドワークやこれまでのヒアリング内容を存分に生かした、具体性やオリジナリティのある提案となりました。
現地で実際に見聞きし五感で感じたことを発表内容に取り込み、村の将来を見据えた提案をすることができたため、最終報告会参加者からは温かいコメントが多く寄せられました。ここまで全力で走り抜けてきた分、発表を終えた学生たちの笑顔からは達成感や喜びを感じとることができました。また日䑓村長からは、「子育て世代ではない学生の立場では難しいテーマだったように思うが2チームとも内容が素晴らしかった。それぞれの提案が具体的だったため何らかのかたちで今後の施策に生かせるのではないかと感じる。」と総括いただけました。
【参加学生の声】
- ワークショップを通じて自分が一番学べたと思っていることが、グループで何かを成し遂げることの意味です。最終発表会で”早く行くなら一人で、遠くに行くなら仲間と”というお話がありましたが、本当にグループで活動を行うことで単純に視点が増えるだけでなく、それぞれ異なった専門性から1つの事柄を検討できていると実感しました。(教育学部 2年)
- ワークショップに参加して、考えの異なるメンバー間でどのように合意形成をしていくかが重要であることを学びました。また提案を考える上では、決して自分の理想だけを対象となる地域に当てはめるのではなく、まずは地域の実情を理解し、同時に「よそ者」として自分が持つ視点を失わないようにする事も大切であると感じました。(文化構想学部 2年)
- 首都圏出身であることもあり、自分の中で当たり前ではなかった地方や地域という言葉が、身近になったように感じています。グループワークでは、他のメンバーのうち誰の意見が正解で誰の意見が間違っているか、という観点ではなく、全ての人の意見を一度平らかな視点で受け入れることが重要だと学びました。(文学部 2年)
- このワークショップを通して、異分野協働により生まれる相乗効果やその難しさを実感するとともに、自分に合った新たなリーダーシップを開拓できたように思います。また、現地調査やヒアリングを通して地域に存在する社会問題を五感で感じることで、知識として持っていた情報が現実問題であることを認知することができました。(創造理工学部 3年)
- 「子育て世帯の住みたい田舎No.1になるための施策を考えよう」というテーマは子育て世代ではない自分たち学生にとって解釈が非常に難しい場面もありました。しかし、観光に携わる方・住民サークル・保育園・役場の担当部署といった関係者の皆様から伺ったお話をもとに、チーム内で連日夜遅くまで議論を尽くしたことは貴重な経験でした!このワークショップを通して、自身のキャリアを通して地域活性化の支援をしていきたいという想いがますます強まりました!(商学部 4年)
【担当職員後記】
- 現地調査前に、昨年同じワークショップを経験した学生との交流を実施し、全編オンラインとなった昨年のワークショップで工夫した点や、現地調査実施できた場合にやりたかったこと等を事前に確認できたことが奏功したように思います。現地調査ではそのやり取りも踏まえて、2チームともヒアリングや施設見学等に積極的に参加する様子がうかがえました
- グループワークではチームとしての意見がすんなりまとまることばかりではなく、5名それぞれのテーマに対する思いや、その先にある木島平村のあるべき姿をすり合わせることが多々ありました。一見回り道のようにも思えるその時間が、考えに考え抜く、という本ワークショップの醍醐味の一つだったように思います。
- 木島平村の豪雪に圧倒されながらも、リアルで訪れることでしか体感できない景観の美しさや村民の温かさに触れることができたと思います。木島平村の方々にご協力いただいたことで、提案に責任感を持っていることも感じられ、2か月という短い期間にも関わらず、みるみるうちに成長していく過程を見ることができました。講評者からも良い評価をいただく提案につながったと思います。
■概要
連携先:長野県木島平村
テーマ: 子育て世帯が住みたい田舎No.1 になるための施策を考えよう
参加学生数:10名
活動期間:2023年1月26日(木)~3月20日(月)