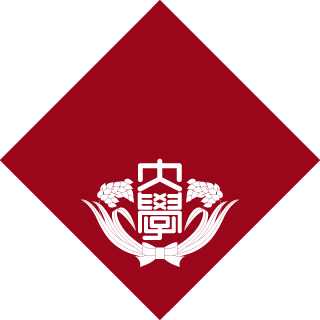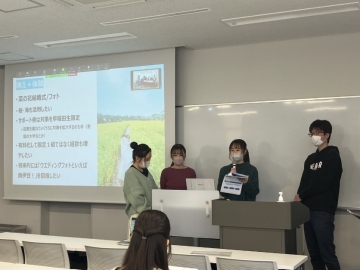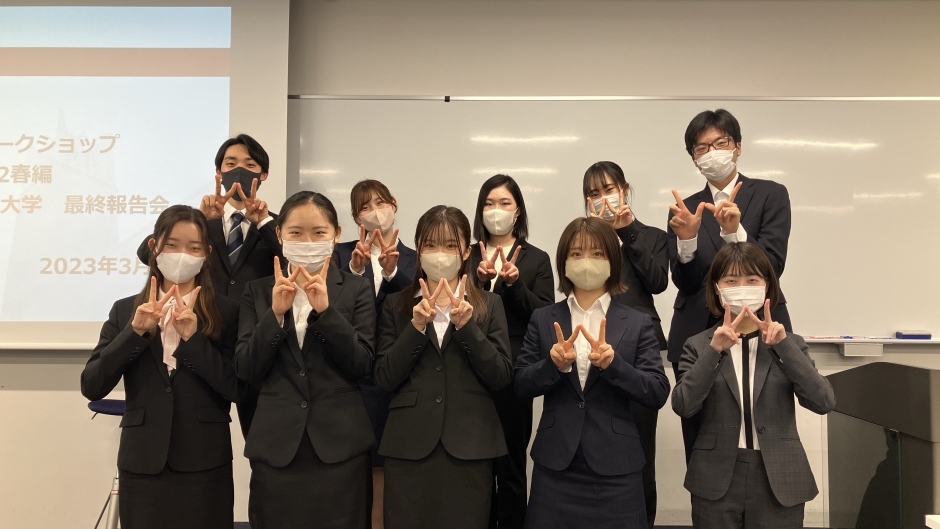【活動概要】
2022 年度静岡県南伊豆町と早稲田大学の地域連携ワークショップが終了しました。新型コロナウイルス感染症の影響により昨年は全面オンラインでの活動となりましたが、感染対策を徹底し、今回は現地でのフィールドワークを実施することができました。たくさんの美しい自然に囲まれている南伊豆町では、定住人口の維持を図りつつ、町と継続的・積極的に関わりを持つ人口(関係人口)の創出にも取り組んでいます。そのために、町の主要産業である観光を通して交流人口の拡大を図ることで多くの方に町を訪れ・知るきっかけをつくり、その後の関係人口や移住・定住にも結び付けていきたいと考えています。
今回のワークショップは、「若者の“旅したい”を引き出す PR 施策を提案せよ!」をテーマとし、若者が南伊豆町に「旅したい」「訪れたい」と思う地域になるための魅力や課題を洗い出し、「若者が南伊豆町を訪れたくなるような PR 施策」「若者の心をつかむキャッチフレーズ」について、多数の応募者の中から選考を通過した 10 名の学生が 5 名ずつ 2 チームに分かれて検討を重ねました。
【活動の様子】
1月13日のオリエンテーション(キックオフ)を皮切りに、3月14日の最終報告会までの2か月間、グループワークや南伊豆町の方々へのオンラインヒアリング、フィールドワークなどを通して施策を考え抜きました。
オンラインヒアリングでは、学生たちが立てた仮説を基に、ジオガイドの方、観光協会の方、バス会社の方々など、南伊豆町の観光を支える多くの方々にインタビューをさせていただきました。ヒアリング初回では緊張する様子も見られ少しぎこちない表情でしたが、回数を重ねるごとに学生も慣れていき南伊豆町の方々から興味深いお話を引き出すなど、その後の提案に繋がる充実した時間となりました。
そして、およそ3年ぶりとなるフィールドワークを2月17日から3泊4日で実施しました。「みなみの桜となのはな祭り」で賑わう南伊豆町で多くの方のご協力を賜り、弓ヶ浜や石廊崎をはじめとする観光名所の視察、岡部克仁町長をはじめとする町のキーマンの方々へのヒアリングなど、充実したフィールドワークとなりました。事前調査やオンラインヒアリングによってある程度の情報を備えてはいましたが、実際に訪れることで気づく新たな発見や現地の方々の温かさなど、南伊豆町ならでの魅力を肌で感じられる4日間となりました。
2月28日の中間報告会では、ヒアリングや現地調査を経て気付いた視点や現時点での施策を説明し、南伊豆町の方々や教職員から様々な視点のフィードバックをいただきました。その後も限られた時間の中で何度もグループワークを行い、自分たちが思い描く理想の南伊豆町の姿や町が抱える課題を整理するなど、最後の最後までチームでの話し合いを重ねました。
そして迎えた最終報告会、「南伊豆町の名産品にフォーカスしたフードフェス」や「サークル合宿の誘致」といった施策が学生たちから提案されました。どちらの施策も現地調査やヒアリングで得られた生の声とこれまでの議論の内容を、丁寧にかつ学生らしい柔軟な発想で組み合わせたものとなりました。
講評では「新しい旅の大きな可能性を感じる提案に大変感動した」「若い人の感性で新しい魅力を引き出してほしい」など温かいコメントを頂戴し、学生たちは無事に提案を終えた安心とともに達成感を得られた様子でした。
最終報告会後の学生同士の振り返り会では、「グループワークでは色々な考え方を知ることができた」など、活動を通して様々な学びがあったようでした。参加学生全員がワークショップで得た経験や学びを今後の学生生活に活かしてくれることを信じて、全日程を終了しました。
【参加学生の声】
- 地域連携ワークショップは入学前から興味がありましたが、調べていくと想像以上に大変そうで自分が自治体の方々へのプレゼンまで終えられるか不安がありました。しかしそれでも挑戦し、最終報告会では練習した中で1番想いを伝えられたと思う結果で終われたため、少なかった自分の自信が増大しました。
チームメンバーとは初対面でしたがオンライン会議や現地訪問を通して仲が深まり、価値観が異なる複数人と初対面の状態から互いを知っていく経験が自分にとっては新鮮でした。ワークショップを通して、自分が知らなかったこと・自分ができること・できないことを何度も考える機会があり、本当に参加してよかったです!
最後に、参加を考えている方におすすめしたい点がいくつかあります。まず、長期休みに実施されるため、時間の余る大学生にとっては魅力的です。考えて行動する何かがあるだけでその期間の充実度は格段に上がります。さらに、今まで出会ったことのない人と出会える点も魅力です。大学の職員さん、他学部・他学年の学生、自治体の方、地元の方など、非常に多くの人と出会えて世界が広がります!(教育学部1年) - 今回のワークショップは自分の将来を考えるためにとても意味のある経験になりました。沢山のグループワークを重ねていく上で、自分に向いている役割は何であるか考えそれを実行に移すというようなことをしました。このことは、自身の成長の機会になり、私にとって大きな収穫でした。
また、グループディスカッションを行う場面が多くあったため、大学生活において社会に備えた貴重な経験が出来ました。これは社会に出てからも当てはまると思いますが、グループワークを重ねると自分とは異なる考え方の人がほぼ確実にでてきます。その中でどのように発言、行動したら自分の意見を伝えられるのか、また、普段の大学の授業のレポートなどとは違い、グループワークを通すことによって自分の意見そのものが本当に最良なのか考えさせられる良い経験になりました。
ぜひ、貴重な大学生活、自身の成長の機会となること間違いなしですので迷われてる方は飛び込んでみてください♡(社会科学部1年) - 短期間で密にチームのメンバーとディスカッションを重ねるからこそ深い議論ができ、とても濃い二ヶ月間になりました。そのおかげでこの短期間の中で自分自身の長所やさらに伸ばしたいことは何かを知るきっかけになりました。(国際教養学部1年)
- 今までは「地方創生」という言葉に対して観光地としての認識しかなかったのですが、ヒアリングやフィールドワークを通して居住地としての観点も忘れてはならないと感じました。現地の方々の中でも観光に対する意識の違いがあることが大変興味深かったです。また、ミーティングや発表などを通して、自分の得手不得手への理解も深まりました。南伊豆町だけでなく自分とも向き合えた2ヶ月間だったと感じています。本当に楽しく、充実したワークショップでした!(社会科学部2年)
- 正直自分は地域貢献に関する授業を受けたこともないし、関連知識が0の状態から日本について知りたいからという動機で参加しました。このワークショップは私に地域創生とはそんなに専門知識が必要な、入門するハードルが高いものではないということを教えてくれました。学年問わず本当に尊敬できる素晴らしい仲間に会えましたし、自分が知らなかった自分の強みや弱みについても分かるし、日本が抱えている課題についても分かる、そして関われるという本当に貴重な経験ができました。そして、学生になにができるのかということが分かるということが本当に強いと思います。学生といえば、お金も力もないから影響力のあることができないと考えがちですが、このワークショップでは自分にできることを考え、それによって学生にできることが意外とあるということがすぐ分かります。この活動では学生らしさがキーとなるなので、学生という身分に誇りを持ちながら、思いっきり自分にできることを尽くしてみると良いと思います。(国際教養学部2年)
- 今回のワークショップは、地方創生・地域貢献という自分にとっては新しい分野への挑戦でした。連日にわたるミーティングや発表の準備など大変な部分もありましたが、そのぶん最終報告会が終わった後の達成感は大きなものでした。チームで協力し、南伊豆町のことを考え抜いた2か月間の経験は、将来必ず活きてくると思っています。(文化構想学部2年)
- このワークショップに参加して自分の思いやアイディアを言語化することの大切さや楽しさを学ぶことができました。ワークショップ参加前の私は自分の考えに自信がなく、ゼロから作り出した自分のアイディアを他人に伝えることに抵抗がありました。しかし、ワークショップのグループワークの中で自分のアイディアを面白いと言ってもらえたり、自分の意見を言うことによって議論が活性化したりするという経験をすることができました。もちろん、実現可能性が低いといった指摘を受けることもありましたが、そういった意見も自分自身の考えをブラッシュアップさせる上でとても重要なものとなりました。このワークショップに参加して自分の意見を言うことの大切さを学ぶことができて本当に良かったです。(文化構想学部2年)
- 今回のワークショップを通じて、多くの方にヒアリングをする事ができました。ヒアリングを通じ、自身の「質問力」を上げる事ができたと考えています。具体的には、どのようにしたら、相手の本音を引き出すことができるか分かった気がします。質問力は今後社会に出た時、必ず役に立つと思うので、これから先も継続的に質問する機会を作っていきたいと思います。(人間科学部2年)
【担当職員後記】
- 学部や学年、ワークショップの志望動機も様々なメンバーが集まりスタートしたなかで、初回から「敬語を使わない」などルールを決めてチームビルディングに取り組んでいた学生たち。フィールドワークではチームの垣根を超えて親睦を深め、報告会の場ではお互いにエールを送り合うなど、10人全員で切磋琢磨して粘り強く提案を磨き上げていく姿に感銘を受けました。
- 現地調査やヒアリングを通して、南伊豆町の魅力に触れることで気付いた課題を「自分事」としてとらえ、最後の最後まで施策を磨き上げた姿勢を頼もしく感じました。最終報告会はハイブリッド形式の開催となり、現地の方や講評者はオンラインでの参加でしたが、各チームとも、施策の魅力を画面越しでもきちんと伝えることができ、提案後は達成感とともに清々しい表情の学生の様子が印象的でした。
- 南伊豆町の多くの方々のご厚意によって無事にワークショップを終えることができました。関係者の皆様には心より御礼申し上げます。そして、そうした町の方々の思いになんとかしてお応えしたいと貴重な春休み期間の大半をワークショップのために費やした学生たちにも心からの敬意を表します。今後もふと思いを馳せたり現地を訪れたりしながら、まずは自分たちが南伊豆町の関係人口になっていってほしいと思います。