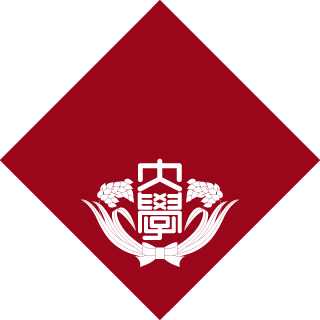今年で3回目となる石川県珠洲市との地域連携ワークショップが無事終了しました。過去2回は全面オンラインでの実施となりましたが、今回は初めて現地でのフィールドワークを実施することができ、能登半島の先端に位置する同市の豊かな里山里海を肌で感じながらワークショップに取り組みました。
今回は「若者Uターンのボトルネックを突き止めよ!~Uターン促進に向けて何が変わるべきなのか~」というテーマに4名の学生が挑戦。全員が首都圏以外の地域出身者であることや、地元へのUターン就職を予定している学生もおり、自分たちのこれまでの経験などをふまえてUターンが進まない要因(=ボトルネック)の分析や考察を進めました。
ワークショップは2022年7月中旬のオリエンテーションにて学生同士の顔合わせや市のご担当者からテーマの内容や背景について説明を受けることからスタート。初対面の学生たちはすぐに打ち解け、試験やレポート作成の合間を縫って情報収集や議論を重ね、自分たちなりの仮説(どうすれば若者のUターンが増えるのか)を立てていきました。
仮説の検証を行うため、8月7日~10日の3泊4日で待ちに待った現地でのフィールドワークに入りました。市内の観光地や街並みをご案内いただくともに、本学校友でもある泉谷満寿裕市長との懇談をはじめ現地の方々のお話を伺う機会を多く組んでいただきました。珠洲市へUターンした方や現地の事業者の方々、さらには県立飯田高校の生徒さんなど、多種多様な視点からお話を聞くことができ充実したフィールドワークとなりました。
また、お盆休み後には珠洲市を離れて暮らす20代の方々へオンラインでのヒアリングも実施。あふれる情報の処理に苦労しながらも徐々に自分たちの提案の輪郭が見えるようになってきました。

緊張の面持ちで泉谷市長との懇談に臨みました

Uターンされた方の思いに耳を傾けます
9月初旬の中間報告会では、フィールドワークやオンラインヒアリング、市が実施したアンケート結果の分析をふまえた考察をまとめました。オンラインで報告を聞いた珠洲市の方々からは厳しくも期待を込めたお言葉をいただきました。また、過去のワークショップ経験者で自身もUターン就職を予定している学生からもアドバイスをもらい、それらのフィードバックを提案にどう結び付けるかを議論する日々が続きました。
発表の直前まで考えに考え抜き迎えた最終報告会。泉谷市長をはじめとした多くの市の関係者の方々を前に、データから見えてきたいくつかのボトルネック、そしてその中から自分たちが解決したいと考えたものを報告。集大成となる提案内容は「珠洲を離れて暮らす若者に向けて、市に関する情報の“周知”と、それによる“愛着”の醸成を目的とした贈り物をする」というものでした。そこに至った背景や、主観と客観を組み合わせて導き出された提案は熟考・熟議の痕跡を感じさせるものでした。泉谷市長からは、「Uターンのボトルネックを突き止めるというのは難しいテーマだったと思うが、懸命に取り組んでくれたことが伝わってきた。今回の提言を今後の移住定住施策に活用していきたい」とのコメントをいただくなど、達成感と充実感に満ちた報告会となりました。

オンラインでも身振り手振りを交えて思いを伝えました
最終報告会後に実施した学生同士の振り返り会では、「ワークショップでの経験がすでにインターンシップなどの場面で活かされていると感じる」「他のメンバーの姿勢からやり抜くことの重要性に気づかされた」「提案が思いつかず無理かもしれないと思ったこともあったが成長を実感できた」など、自身の率直な思いや苦楽をともにしたチームメイトへのメッセージを伝え、2か月半にわたる活動を終えました。
参加学生の声
- このWSは自分の弱み、強み、将来についてを考える一つのきっかけにもなりました。自分が積極的に発言できる力があるものの、上手く聞き出すヒアリングの力が弱いということを改めて実感することができ、自分自身の成長の大きなチャンスにもなった上にフィールドワークを通して様々な人と触れ合うことで人生設計の選択肢が参加前と比べて倍以上に広がったと実感しています。普段の学生生活では経験できないことへのチャレンジに加え、新たな価値観や考え、視野の広さなど色々な力もつけることができました。(法学部2年)
- 私にとって、このワークショップは、地域のもつ課題だけではなく「自分」とも向き合った2カ月でした。ヒアリングやグループワークをする中で気が付いた新しい自分、より明確になった強み、そして課題は、今後に生かされていきます。進路に悩む今だからこそ、参加する価値があると思います!(文化構想学部2年)
- このワークショップに参加して、とても充実した2カ月間を過ごすことができました。Uターンのボトルネックという日本全体に関わる大きな問題に対し、自分事として考え、そして主体的な行動を繰り返した経験は、未熟な自分にとって成長の連続でした。
期間中は、現地調査で感じ取った珠洲市ならではの雰囲気や、ヒアリングでリアルな声を聞けたことで、机上の空論にとどまらない話し合いとなりました。それゆえに思い通り進まないこともありましたが、チームの一人一人がパズルのピースのように助け合って乗り越えた経験は、自分の糧となり、大切な思い出です。得られた多くの学びを今後の生活に存分に活かしていきたいです。(教育学部3年) - 私は今回のワークショップを通して「一から物事を考えること」を学べたと思っています。実際に今までの授業などではグループワークをすることがあっても、その場で終わったりと深堀りすることはほとんどありませんでした。しかし今回のワークショップでは、「ボトルネックを探る」「解決策を考える」といった2段階で考えることがあり、議論が膠着状態になることも多々ありました。そんな中でも4人それぞれの役割を果たし、最終報告まで至ることができたと思っています。
また、今回は実際に現地に伺うことができたために、珠洲市の空気感や現地の方々のお人柄といったところに直接触れることができたのが、とてもよかったです。現地を見たからこそ見いだせたキーワードなどもあり、とても実りのあるものとなりました。私はこのワークショップを通して、自分が持っている力というものを再認識・再発見できたと思っています。「必ず何かが身に付く」。そんなものになるはずなので是非チャレンジしてみてほしいです!(社会科学部4年)

同じテーマでワークショップに取り組んだ金沢美術工芸大学の学生さんたちと