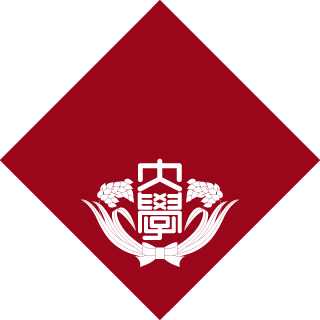2021年度佐賀県唐津市と早稲田大学の地域連携ワークショップが終了しました。
系属校の早稲田佐賀中学校・高等学校も所在しており、本学とも非常に縁のある同市では、地域資源の輝きが生み出す「ひとの流れ」の創生に向けて、観光地域づくりの推進に取り組んでいます。その一環として今回で3回目の実施となるワークショップのテーマは「地域資源のポテンシャルを引き出すための施策とは?~「肥前名護屋城跡・陣跡」のファンを創出せよ!~」でした。
多数の応募者の中から選考を通過した10名の学生が2チームに分かれて、豊臣秀吉の権力の強大さを物語るこの史跡の活用に挑戦しました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、残念ながら全面オンラインとなった本ワークショップですが、7月12日のオリエンテーション(キックオフ)から8月31日の最終報告会までの約1か月半、学生たちはひと夏を捧げる思いで取り組みました。
ワークショップは唐津市役所の方からのご説明や峰市長との懇談など、唐津市のみなさんの期待値の高さをうかがい知るところからスタートしました。画面越しではありますが、市の名産品である呼子のイカを市長とともに堪能させていただくなど、朗らかな雰囲気で動き出しました。

峰市長、呼子のイカと記念撮影
8月に入ると、学生は自治体の方や地域の観光業に携わる方、唐津市にお住まいの方などへのヒアリングに入りました。慣れないオンラインでのヒアリングに最初は戸惑っていた学生たちですが、回を重ねるにつれ、市の皆様が観光産業へ抱く想いを深掘りする傾聴・質問の能力を身につけ、的確な現状分析を行っていきました。
ヒアリングと同等、あるいはそれ以上に学生たちが注力していたのがグループワークです。学年も学部も異なるメンバーが日夜議論を重ね、課題解決のための仮説を検討し、提案内容を磨き上げていきました。

市長からは唐津市の魅力や課題をお話しいただきました
こうした仮説は8月中旬以降の中間報告会などを経てさらに練り上げられ、最終報告会へと至りました。「秀吉が隠した宝を探せ!」「なごやかいち」「出世制度」「からぱプロジェクト」といった印象的なフレーズが織り込まれた提案は、どれも実現可能性の高い具体的なもので、学生たちが議論を積み重ねてきたことを感じさせるものでした。報告会の総評をしてくださった峰市長からは「まだ原石である名護屋城跡、陣跡を磨き上げるためにも今回の提案を生かして事業展開をしていかないといけない」とのコメントをいただきました。
報告会を終えて少しの疲労と安堵、そして大きな達成感を感じた表情の学生達は、「最後のグループワーク」として自身が成長したと感じた点やチームメイトに助けられた点などをお互いに語り合い、なごやかな雰囲気でワークショップを終了しました。

達成感に満ちた表情でワークショップを終えました
【参加学生の声】
●地域の方へのヒアリングで、ターゲティングの重要性や、独りよがりのPRではなく相手の立場に立つことの大切さについて教えていただきました。相手の立場に立って何かを企画・提案するということは、その相手の興味関心にも敏感になる必要があると感じました。食わず嫌いせず様々なことにアンテナを張って試してみるのも、自分の世界を広げるきっかけになるし、「相手の立場に立つ」という人としての姿勢を養うことができるのではないかと思いました。(文化構想学部1年)
●自分が住む地域をよりよくするために、行政の方々だけでなく、ヒアリングでお伺いした多くの方々がそれぞれ熱い思いをもって様々なことを考えていらっしゃることがとても印象的でした。今思えば、ワークショップ参加前は「地域貢献」「地方創生」といったキーワードを軽く考えていたと思います。唐津市の方々は、たくさんの取り組みをなされていて、思いがあってもうまくいかないこともあって、とても難しいことだと感じました。しかし、難しいからこそ挑戦してみたいという思いも芽生えました。(教育学部1年)
●ヒアリングを通して、自分たちが何を知りたくて質問しているのか、頭の中のイメージを言語化して相手に分かりやすく伝えることの大切さを知った。これは今回のヒアリングに限った話ではなく、普段の会話でも必要なスキルだと思った。チームで一つの課題に真剣に向き合った1ヶ月半の経験は今までの大学生活の中で一番充実していて、何にも替えがたい私の成長の糧になった。(文化構想学部2年)
●今までの大学生活で何度かグループワークを行ってきたが、あまり内容の濃くないディスカッションだった。それはなぜかというと、意見をぶつけあうような信頼感や雰囲気がなかったからである。今回のワークショップでは、きちんとアイスブレイクなどを通して、メンバー全員が意見を言い合える環境を作ったことによって良いディスカッションが行えて、満足のいく提案ができた。(社会科学部3年)
※本ワークショップの様子は複数の新聞やメディアにて取材・報道していただきました。その一部を以下のリンクよりご覧いただけます。