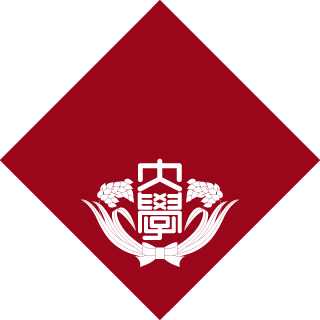地域連携ワークショップ(以下、地域WS)に参加した学生同士の親睦を深めることを目的とした「参加学生の集い」を開催しました。イベントには地域WSへの参加を経て社会人となった校友の方々4名にもお越しいただき、学生生活の過ごし方や社会人としての日々についてのお話もたくさん聞かせていただきました。
概要
開催日:2022年5月21日(土)13:30~15:30
会場:早稲田キャンパス 18号館(国際会議場)3階会議室
対象:2020年度/2021年年度の地域WS参加学生
内容:
第1部 社会人によるトークセッション
第2部 交流会
登壇者(卒業年順):
花輪 祐樹さん(2020年3月法学部卒、4年時に津山市の地域WSに参加/まちづくりを手がける企業にお勤め)
倉持 光さん(2021年3月教育学部卒、3年時に木島平村の地域WSに参加/電機メーカーにお勤め)
石田 穂高さん(2022年3月政治経済学部卒、2年時に木島平村の地域WSに参加/金融機関にお勤め)
平野 敬子さん(2022年3月商学部卒、1年時に南伊豆町の地域WSに参加/金融業界にお勤め)

第1部 社会人によるトークセッション
社会人の方々に以下のようなトークテーマでお話しいただきました。
掲載されている内容以外にも学生時代のお話、就職活動や現在のお仕事といったキャリアに関するお話なども聞かせていただきました。
地域WSに参加した理由やきっかけは?
- 自身が京都府出身ということもあり、地域にはもともと興味があった。学部で学んだことを実践する場を求めていたところ地域連携ワークショップの存在を知り参加を決めた。大学生活の後半に向けて自分の進む道の方向性を見定めたかった。(石田さん)
- 「地域連携演習」という授業で、先生から紹介いただいたことがきっかけで申し込んだ。他学部・他学年の学生と自分の知らない地域について一緒に考えられることにも魅力を感じた。(平野さん)
- 地域のことをもっと知りたいと思ったことが率直な気持ち。1年時にWAVOCの地域交流サークルに入り、「地域創生」「地域格差」などの言葉は知っていたが、実際の意味を知りたかった。地域の現場で実情を感じてみたかった。(倉持さん)
- 大学1年生の夏に同様のプログラムに参加し、幅広い学部・学年の学生でチームとなって地域に寝泊まりするような活動が印象的だったから。多様な価値観に触れる経験を卒業前にもう一度重ねることで大学生活を経た自分の成長を確認したいと思って参加した。(花輪さん)
地域WSでの経験をその後の学生生活や就活にどのように活かしましたか?
- 自分の強みや弱みを知ることができ、キャリアの方向性を決めるきっかけにもなった。どのような業界に進むべきかを迷っていたが、ワークショップで具体的な提案まで踏み込めなかったため、金融業界に入り地域への提案を実行に移す支援をしたいと思った。(石田さん)
- ワークショップの経験が就活で活きたと感じたのはグループディスカッションのとき。初対面の就活生と意見交換しなくてはいけないときも臆せず対応することができた。ワークショップで学んだ課題設定の方法や議論の進め方といったスキル面での自信が大きかったと思う。(平野さん)
就活はいつ頃、どんなことから着手しましたか?
- 3年生の5月下旬から開始。最初にサマーインターンシップに申し込むにあたり、どういう企業が自分のやりたいこととあっているのかを調べた。その後はES(エントリーシート)作成、ウェブテスト受験、面接、グループディスカッションの回数を重ねた。体力勝負の就活だったと言えるかもしれない。就活のノウハウ本通りに行動するより、自身の直感を信じてやりたいことを探して行動した。 (石田さん)
- ゼミの論文執筆に注力していたため、3年生の2月中旬から開始した。4年生になる直前というタイミングではあったが、周囲と比べて遅れたとは特に感じなかった。限られた時間の中でESの土台づくりや自己分析、面接を想定した問答集作成などをした上で、面接はぶっつけ本番という感じ。インターンにも参加していなかったが、それでも短期集中でやりきれたと思う。(平野さん)
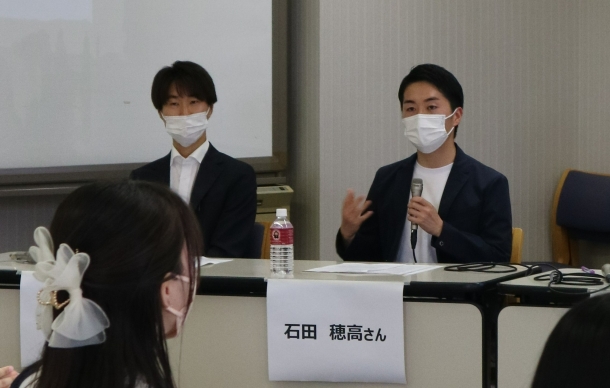
身振り手振りを交えて話してくださる石田さんと花輪さん(左)
地域WSでの経験が日々の仕事などに活きていると感じることは?
- お客様へ自社のサービスを提案する際に、ワークショップでの活動と似ていると感じる。例えば、提案の準備をしているときに、ワークショップでは地域の方々へのヒアリング結果などを提案に盛り込む。業務においてもお客様のニーズ=求めていることと自分たちの提案のすり合わせが必要であり、そうした部分が共通点だと感じる。
また、新規のお客様とお話しするときにワークショップのことを思い出す。「はじめまして」の状態からどうやって関係を構築していくかを考え、一緒に何かを作りあげていくプロセスはワークショップも仕事も同じだと思う。(倉持さん) - 仕事において活きていると感じるのは組織、成果に当事者意識をもつ、という点が大きい。4年生でワークショップに参加したのでリーダー的な立ち回りが求められた。内向的なメンバーもいたし、かみ合わない時間があった。チーム内の雰囲気をよりよくする方法、どうすればよいかを試行錯誤したことが活きている。
ワークショップ期間中は納得いくまで自主的な打合せを何度も重ねた。今でも当時の提案は実現してほしいと思っているほど。成果にこだわり抜く姿勢は社会人として働く上でも重要な要素でありワークショップで培われた。(花輪さん)
後輩たち(参加学生)への学生生活の過ごし方のアドバイスは?
- 学生時代はとにかくいろんな世界にふれてみてほしい。早稲田大学は環境が整っていて多様性もあると思う。一方で、外に目を向けて多様性に触れてほしい。ワークショップではさまざまな取り組みをにかかわる方々や人生に触れたと思う。その経験から自分がどのように生きていくべきかを感じられた。(花輪さん)
- 学生のうちは少しでも興味を持ったことにはどんどん取り組むべきだと思う。その経験が自分の適性、向き不向きを見定めるきっかけになると思うし、社会人になった後の人生の指針となると思う。時間があるうちに行動してほしい。(平野さん)
- 学問に取り組める時間は学生ならでは。社会人の勉強と大学の学びは少し別に感じる。研究のプロである教授と語る時間は貴重だった。体系的な学びに触れた経験は、他の業界、事業でもいかせる、人生が豊かになる要素だと思う。(石田さん)
- 時間があるようでない4年間なので好奇心を深めるために、読書したり現場に赴いてみてほしい。実際に体験することで自身の興味や関心が明文化される。社会人は仕事以外の時間が少ないため、大学生の期間に好奇心、興味の土台を広げておくと良いと思う。(倉持さん)
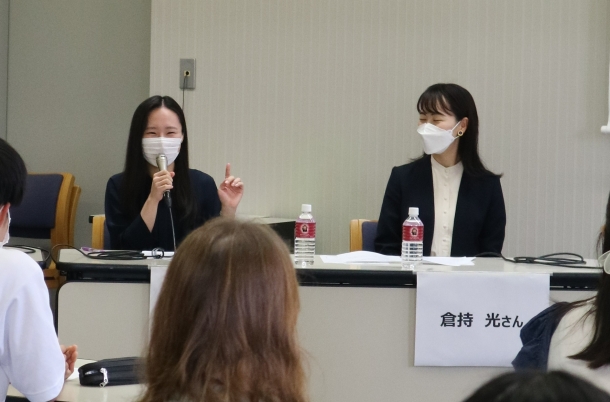
表情豊かに話してくださる平野さん(左)と倉持さん
第2部 交流会
交流会の前半は、参加した地域や年度をシャッフルして学生同士の横をつながりを作ってもらうために4名程度のグループに分かれての交流を行いました。ワークショップ中の苦労話やワークショップ後に取り組んでいることなど、「地域WS」という共通項でつながった学生同士で大いに盛り上がりました。
後半は社会人の方々にお一人ずつグループに分かれてもらい、参加学生は話を聞きたいと思う方のところへ行っての交流を行いました。社会人の方々からは1日の具体的なスケジュールや休みの日の過ごし方などの話題で盛り上げていただいた一方、学生たちからは質問が飛び交いゼミ選びや就活に関する具体的なアドバイスなどもいただきました。

交流会後半で先輩の話に耳を傾ける学生たち
交流会後、記念撮影を終えると質問し足りない学生たちが社会人の方々のところへ押し寄せ、会場の熱気はさらに高まりました。学生同士で親交を深めたりお互いに情報交換をする姿も見られ、さまざまな「つながり」を作ることができたことと思います。
参加学生の声
- 先輩のお話がとても貴重でした。同じワークショップに参加した経験を活かしての就活においての活かし方や、経験の活かし方がとても参考になりました。
- こう言った形で同じ熱量で話せる機会はあまりないので、とても有意義な時間でした。また、自分の進路に進まれている先輩に赤裸々にお話を聞ける機会も少ないため、ありがたかったです。
- 地域連携という共通点を持つ先輩方なので、自分の描きたい将来像に似たキャリアを選んでいる方もいらっしゃり勉強になりました。
- 学部学年関係なく普段会わないような方に会えました。また、どのような取り組みがあるのかを知るきっかけになりました。
- 地域連携ワークショップに参加した人と意見交換をすることができてとても良かった。同じ学部の人と授業以外であまり交流したことがなかったので今回話をすることが出来た。