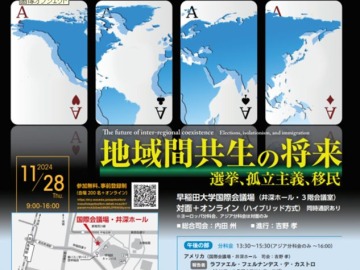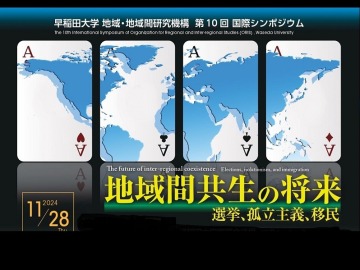2024年11月28日(木)、10年にわたるORIS活動の締め括りとなった今回の国際シンポジウムは、米カリフォルニア大学サンディエゴ校よりラファエル・フェルナンデス・デ・カストロ教授をゲストに迎え、学内外から10名あまりの研究者の参画を集めて開催された。午前の部はカストロ教授の基調報告に始まり、アメリカ、ヨーロッパ、日本それぞれの視点から「選挙、孤立主義、移民」にまつわる世界の動きを展望。これを踏まえ、午後の部ではアメリカ、ヨーロッパ、アジアの各部会に分かれ、反グローバリズム/孤立主義と移民受け入れについて議論を深めた。
【午前の部】 米国・欧州・日本から見る「選挙・孤立主義・移民」をめぐる世界的潮流
総合司会:内田 州(早稲田大学地域・地域間研究機構 主任研究員)
進 行:吉野 孝(早稲田大学地域・地域間研究機構機構長/政治経済学術院 教授)
[開会挨拶]
折しも11月5日の米国大統領選でトランプ氏が返り咲きを果たし、自国第一主義と移民制限を公約に掲げる共和党が連邦議会議員選挙で勝利を収めたことは、この日の議論の意義と緊迫性をよりいっそう高めることとなった。

早稲田大学 総長 田中 愛治(ビデオ出演)
シンポジウムの冒頭で開会挨拶のビデオメッセージに登場した田中愛治・早稲田大学総長はそのことに触れ、「アメリカの将来は、孤立または連帯・共生、排除もしくは受容、といった選択にかかっており、それは国際社会にも大きな影響を与えることになる」と述べた。
周知のように、ウクライナ戦争を機に増幅するロシアとNATO諸国の対立や、資源や先端技術をめぐる米中の覇権争いに見られるように大国間の関係悪化が際立つ一方、欧米諸国の国政選挙では反グローバリズムや孤立主義、移民問題が争点となり、これまでの既定路線であった国際協調主義や移民受け入れ方針に疑義が突きつけられる傾向にある。「このような国際情勢のなか、どのようにして連帯と共生の道を探ることができるのか。答えのない問題に立ち向かい、いかにして解決策を導くか。世界人類に貢献する大学として覚悟を持って臨みたい」。田中総長はそう言葉をつなぎ、シンポジウムの意義を強調した。

早稲田大学地域・地域間研究機構長 吉野孝(政治経済学術院 教授)
これを受け、進行役を務める地域・地域間研究機構長の吉野孝教授(政治経済学術院)がシンポジウム全体の流れを紹介。午後に行われる分科会への問題提起となる4つの講演へと場をつないだ。
[基調報告]ラファエル・フェルナンデス・デ・カストロ/
カリフォルニア大学サンディエゴ校 教授、アメリカ・メキシコ研究センター 所長
” The End of Pax Americana: its Global and Regional Impacts”
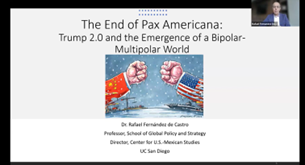
ラファエル・フェルナンデス・デ・カストロ(カリフォルニア大学サンディエゴ校 教授、アメリカ・メキシコ研究センター 所長)(ビデオ出演)
基調報告には比較政治学を専門とするカリフォルニア大学サンディエゴ校のカストロ教授がビデオで登場。第二次世界大戦後にアメリカを中心に構築された国際秩序を表すパックス・アメリカーナ(Pax Americana)が、主に3つの要因によって終焉を迎えようとしているとして警鐘を鳴らした。
第1の要因は「トランプ2.0」の成立によって加速するアメリカの崩壊。上下両院を支配下に置く第2期トランプ政権の成立により、政府の要職は国家よりもトランプへの忠誠を第一に考える腹心らによって占められ、ナショナリズムと孤立主義が加速するとともに民主主義は後退し、内部崩壊が始まるとして危機感を露わにした。
第2に挙げられるのは中国の台頭。中国はもはや経済力だけでなく、軍事や技術の戦略においてもアメリカを凌駕する存在となり、ロシアをはじめとするBRICS諸国を結託して新しい世界秩序を打ち立てようとしている。
3つめの要因は、巨大テック企業が国家のように強大な力を持ち、それを率いるイーロン・マスク氏のような人物が大統領の側近として力を振るい、政治の世界にも影響力を行使し始めたことである。 米中覇権争いの下、BRICSなどを交えて多極化する世界には今、1万2000発もの核弾頭があり、軍備費はますます増大する傾向にある。カストロ教授は最後に「世界は暴力と統治不能が激化する時代に入ろうとしている」として、鍵を握るトランプ政権の動きを注視する必要性を訴え、話を終えた。
米中覇権争いの下、BRICSなどを交えて多極化する世界には今、1万2000発もの核弾頭があり、軍備費はますます増大する傾向にある。カストロ教授は最後に「世界は暴力と統治不能が激化する時代に入ろうとしている」として、鍵を握るトランプ政権の動きを注視する必要性を訴え、話を終えた。
[報告1]前嶋和弘/上智大学総合グローバル学部 教授
「大統領選挙後のアメリカと世界」

前嶋和弘(上智大学総合グローバル学部 教授)
次に登壇したのは、上智大学教授で現代アメリカ政治・外交を専門とする前嶋和弘氏。トランプ勝利の実態と新しい政権の方向性、日本の対応などについて論点を挙げた。
選挙結果については「トランプ圧勝」の論調で報じられたが、実態は決してそうではなく、得票率はハリス48.4%に対してトランプ49.9%で僅差に過ぎず、過去20回の大統領選で4番目の接戦だったと指摘。連邦議会議員選挙でも共和党が上下両院を制したが、上院での議席数奪回は既定路線であり、下院ではむしろ議席は伸びず苦戦に終わったとして、「過剰な解釈は避けるべき」と釘を刺した。
しかし、トランプ陣営は勢力が拮抗するなかでも確実に支持層を味方につけるため、「ペットを食べる不法移民」「バイデンフレーション(バイデン政権下での物価高騰)」「女の大統領でいいのか?」などの過激な言葉を戦略的に使い、巧みに分断を煽って世論を誘導したことは確か。その結果、トランプ氏に投票した割合は、「男性」「白人」「ヒスパニック」などのカテゴリーで前回の大統領選を顕著に上回ったことが出口調査から明らかになったという。なかでも政治学の専門家さえも驚かせたのは、これまで民主党を支持する傾向が強かった比較的所得の低い層が一転して共和党支持に回ったことで、1980年代以降の出口調査で初めての現象だった。
今後のトランプ政権の方向性としては、「1期目で達成できなかったこと」に取り組むことが予測され、不法 移民の強制退去や関税引き上げなどから着手し、「全国民の大統領にはならず、片方の世論だけを重視して動く」政策により、政治的分極化はさらに深まると前嶋教授は見る。そうしたなかでアメリカ主導の国際秩序は衰退するものの、日本としては「トランプ後を見据えた工夫」も重要であり、「面倒でもアメリカとの付き合いはまだ続けていかなくてはならない」と語って話を結んだ。
移民の強制退去や関税引き上げなどから着手し、「全国民の大統領にはならず、片方の世論だけを重視して動く」政策により、政治的分極化はさらに深まると前嶋教授は見る。そうしたなかでアメリカ主導の国際秩序は衰退するものの、日本としては「トランプ後を見据えた工夫」も重要であり、「面倒でもアメリカとの付き合いはまだ続けていかなくてはならない」と語って話を結んだ。
[報告2]日野愛郎/早稲田大学政治経済学術院 教授
「欧州における移民争点と右派新興政党の台頭:欧州選挙研究(EES)による検証」

日野愛郎(早稲田大学政治経済学術院 教授)
アメリカで分断が進む一方、ヨーロッパの情勢はどうか。早稲田大学の日野愛郎教授は、6月に行われた欧州議会議員選挙の結果とこれまでの欧州選挙研究(ESS)の成果を踏まえ、移民争点から見た各政党会派の位置づけや、支持層を広げる右派新興政党の動きについて検証した。
日野教授はまず、欧州議会議員の任期に沿って2014年選挙からの5年間と、2019年選挙からの5年間における政党グループ(会派)を比較。それによると、2大政党として多数派を構成する欧州人民党(EPP)と社会民主進歩同盟(S&D)がともに2019年選挙で大きく議席を減らした一方、中道派の欧州再生(Renew Europe)や緑の党(Greens-EFA)、さらに極右系のアイデンティティと民主主義(ID)が議席を伸ばしたことがわかる。これを踏まえて今回の2024年選挙の結果を見ると、2大政党が横ばいで、中道派は減少するなか、IDから転じた極右派のPatriots of Europeが大きく伸長、全720議席中84議席を占めて第3勢力となった。すなわち、「この10年間で極右勢力だけが伸び続けていることがわかる」と日野教授は言う。
こうした動きは有権者の投票行動の研究によっても明らかで、メインストリームといえる既存政党の得票率に比べ、チャレンジャーである右派政党の得票率は顕著に上がっている。
 また、今回の選挙でチャレンジャー右派に投票した人のうち8割が前回の2019年選挙でも投票しており、支持者が固定化される傾向が強まっているという。
また、今回の選挙でチャレンジャー右派に投票した人のうち8割が前回の2019年選挙でも投票しており、支持者が固定化される傾向が強まっているという。
有権者はなぜ、中央から離れて左右の道に振られているのか。選挙研究の分析によると、移民受け入れの賛否をはじめ、欧州統合の是非、環境問題への対応、富の再分配をめぐる4つの争点が関係することがわかっている。日野教授は、これは10年前からすでに見られた傾向であり、特に移民反対/統合反対の立場を取る人は、今回の選挙においても既存政党からの離反ないし右派政党への継続的支持が強いことが確認できたとして、分断の度合いが高まる世界の流れと同調していることを指摘した。
[報告3]遠藤十亜希/城西国際大学国際アドミニストレーション研究科 教授
「世界の中の日本の入管政策」

遠藤十亜希(城西国際大学国際アドミニストレーション研究科 教授)
続いて、各国の移民政策や入管制度について研究する城西国際大学の遠藤十亜希教授が登壇。日本の入管政策の軌跡と現状を追いつつ、日本が考えるべき論点と方向性を示唆する報告を行った。
遠藤教授によれば、世界規模で移住者人口の拡大が進むなか、かつては「労働移民に依存しない唯一の先進国」といわれ、移民政策(外国人受入政策)では後発的とされてきた日本においても変化が見られるという。1970年代の経済成長期にアジアからの非正規労働者で人手不足を補う「裏口」が開かれると、90年代からは南米日系人への定住ビザの発給や技能実習生の受け入れといった「サイドドア」が開き、2010年代になって少子高齢化と労働力不足が深刻化すると「表玄関」を開け、多種多様な業種で外国人材を求めるようになった。
日本にとってこれはPolicy Transformation(政策転換)といえるのか。移民国家への移行だとする見方がある一方、市場・経済のニーズに応じて短期的な「労働力」としては柔軟に受け入れるが「人間」としては排除するという二元論で捉えることもできると遠藤教授は指摘。事実、2024年6月に成立した改正入管難民法には、外国人の永住権取り消し要件を拡大する規定が追加された。
 日本がこのような曖昧な政策を取る背景として、自民党支持層に一定数の移民反対派が存在することや、移民庁などの独立した機関がなく、移民に懐疑的な法務省と入管庁が出入国管理行政を管轄している点が挙げられた。そのため日本の受け入れ政策は後追い的なものとならざるを得ず、アジア労働市場の動きにも後れを取って必要な人材が確保できていない。一方、非正規移民に対する取り締まりは欧米の動きと同様、ますます厳格化しているのが実情だ。
日本がこのような曖昧な政策を取る背景として、自民党支持層に一定数の移民反対派が存在することや、移民庁などの独立した機関がなく、移民に懐疑的な法務省と入管庁が出入国管理行政を管轄している点が挙げられた。そのため日本の受け入れ政策は後追い的なものとならざるを得ず、アジア労働市場の動きにも後れを取って必要な人材が確保できていない。一方、非正規移民に対する取り締まりは欧米の動きと同様、ますます厳格化しているのが実情だ。
日本政府は多文化共生社会の実現に向けた施策を打ち出しているが、対応は十分とはいえない。効果的な政策を打たなければ移民をめぐって社会が分かたれ、ポピュリストらが煽り立てる移民脅威論から差別が拡大する。欧米を悩ますそうした移民問題が日本でも起こる可能性はあり、社会の分断を防ぐには差別やヘイトに対する法的規制など、そして、真に多文化共生社会を目指すならば、支援策の拡充が必要ではないかと遠藤教授は指摘する。
東アジアには人権に関する地域間の枠組みや組織が不在であり、国際的な人の流れは国別に管理されているのが現状だ。しかし、地政学的リスクや気候変動など、超国家的要因で大規模な移動が起きた場合は対応に限界がある。地域・地域間協力システム構築の必要性を訴える遠藤教授の提言により、第1部のセッションは幕を下ろした。