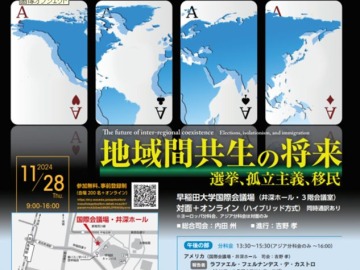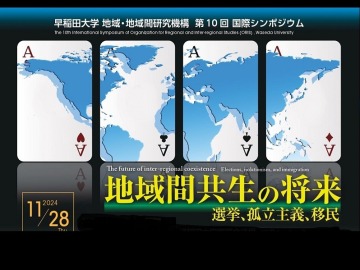【午後の部:ヨーロッパ分科会】 EUと加盟国における移民・難民政策とそのゆくえ
司会:中村英俊(早稲田大学政治経済学術院 教授)
ヨーロッパ分科会では臼井陽一郎教授(新潟国際情報大学国際学部)、大嶋えり子准教授(慶應義塾大学 経済学部)、大道寺隆也准教授(青山学院大学法学部)の3名の研究者を招き、 移民政策をめぐるヨーロッパの政治状況について発表と討論を実施。ファシリテーターは早稲田大学の中村英俊教授(政治経済学術院)が務めた。
移民政策をめぐるヨーロッパの政治状況について発表と討論を実施。ファシリテーターは早稲田大学の中村英俊教授(政治経済学術院)が務めた。
[報告1] 臼井陽一郎/新潟国際情報大学国際学部 教授
「欧州議会選挙と(反)移民の政治」

臼井陽一郎(新潟国際情報大学国際学部 教授)
分科会はまず、EU政治に関して地域統合論や国際組織論の観点から研究する臼井教授による発表から開始。演題に(反)とあるのは反移民の動きは明白であるものの、なお予断は難しいからだとしたうえで、2024年の欧州議会選挙で明らかとなった「EU統合派の微減とEU懐疑派の増加」から話を始めた。
統合賛成派の連立会派であるグランドコアリション(欧州人民党、欧州社民党、欧州刷新)は過半数を維持したものの過去最低の議席数となり、ポピュリスト傾向が強い統合懐疑派の右派・極右勢力の増大が長期的趨勢と見られるなか、ヨーロッパ文明の優位性とキリスト教共同体の必要性を強調する傾向が強まっている。そうした状況下、グランドコアリションの支持によって再選したフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は政策決定を安定化させるため、右派・極右勢力への接近を余儀なくされている。
臼井教授によれば、右派・極右勢力におけるイデオロギーの共通ラインには主権主義や愛国主義などと並んで反移民があり、レイシズムが助長される傾向にある。その一方、ヨーロッパの根底には国境を越えた普遍的人権を志向する精神があるはずで、その狭間で安全保障や労働力の確保、難民保護といった種々の要因がせめぎ合う状況にある。ウクライナ要因などでEUへの難民流入が急増するなか、移民受け入れを取り巻く状況は厳しさを増す。非EU市民を排しても加盟国市民の連帯を求め、地政学的一体化を進めるのか、EU条約が定める人間の尊厳に則り普遍的価値の実現を目指すのか。移民をめぐる問題にEUリベラリズムの行方が深く関わっていると、臼井教授は指摘した。
[報告2]大嶋えり子/ 慶應義塾大学経済学部 准教授
「フランス政治と移民」

大嶋えり子(慶應義塾大学経済学部 准教授)
次に登壇した大嶋准教授は、「中道」といわれるフランス・マクロン政権の政策的立場と移民対策を概観しつつ、右派的政策と左派的理念が政権内でどのように共存するのかを紐解いた。フランスでは第五共和政が成立した1958年以来、社会党を中心とする左派勢力と、現在の共和党へとつながる右派勢力の二大ブロックが交互に政権を担う状況が続いてきた。しかし、この10年で既成政党における刷新の欠如や金銭スキャンダルなどが相まって政党システムが弱体化。そこに登場したマクロンが社会党の若きホープとして新風を吹かせ、2017年の大統領選では共和党の一部の協力も得ながら当選を果たす。同年の総選挙でもマクロンの政党・共和国前進が過半数を獲得。その背景には、左派的な文化的リベラリズムと右派的な経済的リベラリズム、さらに親EU/統合賛成派による組み合わせの妙があったと大嶋准教授は指摘する。
一方、移民政策はフランス政治にとって過去一貫した重要課題であり、1970年代の入国管理の厳格化、80年代からの反移民派・国民戦線の台頭、90年代のサン・パピエ(非正規滞在者)をめぐる議論を経て、2005年以降の選別的移民政策へと流れていく。大嶋准教授によれば、その裏側には自由と平等、ライシテ(国家と諸教会の分離)、普遍主義(人間の尊重)などの理念があり、それらを土台に、共生を脅かすとされる「分離主義」への予防法制、排他的と捉えられているウォーキズムとの対立立、全身を覆うムスリム女性の衣装アバヤの禁止といった近年の動きがあるという。2024年1月には、外国人労働者の受け入れ拡大や非正規滞在・外国人犯罪対策の厳格化を含む移民関連法制が成立した。
これらを総じて、マクロン政権の移民政策は全体的に右派寄りだが、それを裏づける理念は左派寄りであることが特徴だと大嶋准教授は言い、フランス政治では左派・右派の位置づけに注意が必要だとして報告を終えた。
[報告3]大道寺隆也/青山学院大学法学部 准教授
「EU域外出入国管理政策とポストコロニアリズム」

大道寺隆也(青山学院大学法学部 准教授)
EUでは近年、域外の第三国において移民・難民の出入国を管理する動きが加速している。大道寺准教授はその点に着目し、難民排除などの問題を孕みながら巧妙化する「域外化」の様相と、そこに見え隠れするEUと第三国との「共犯関係」について考察。新たな理論的枠組みに向けた試論を報告した。
大道寺准教授はまず「問題の所在」として、EUやEU加盟国が難民を排除する動きが現実にあり、欧州人権条約などに触れる違法性が問題視されたことを機に「域外化」が進展したと解説。その手法は、①一方的入国不許可、②協力による到着阻止、③委任による到着阻止、④外注による出発阻止などに類型化され、巧妙化の最たるものとして「移動と開発の連関」を挙げた。これは「負担となる保護対象」として見られてきた難民を「利益をもたらす経済主体」へと転換するもので、難民が出国し移動する理由を失わせる働きかけとしての「自立支援」を意味するという。一見してWin-Winといえる関係性だが、「果たしてそれでいいのか?」と大道寺准教授は問題提起をする。
なぜなら、域外化における第三国は往々にしてかつての植民地であるアフリカ諸国であり、そこには必然的に非対称的な権力関係が介在するに違いないからだ。そのようなポスト植民地主義の観点から域外出入国管理を批判的に読み解く研究は未だ不十分であり、見方によっては難民の選別と排除においてEUと第三国の「共犯関係」が成り立つのではないかと指摘する。また、その手掛かりとして、形式上の植民地支配は去ってもその構造は残るとしたヨハン・ガルトゥングの「帝国主義の構造」論に着目。その実例と見られる事案を例証しながら共犯関係の構図を炙り出していった。
最後に大道寺准教授は、「EUと第三国の利益は必ずしも調和しないが、EUと加盟国は第三国の中心(≒政府)を“橋頭堡”としてWin-Winの関係を築き、難民の人権侵害を準備(facilitate)している」と述べ、EU域外出入国管理政策に帝国主義的な動きが底流することを示唆。「共犯」や「利益」といった概念の精緻化を今後の研究課題とした。