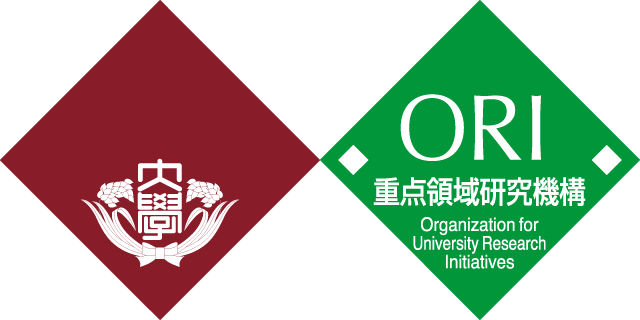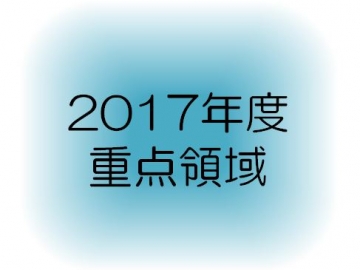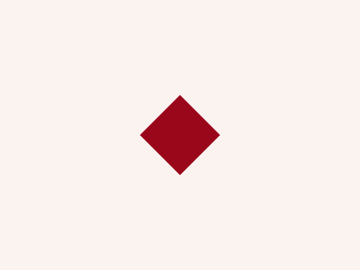2016年03月31日に終了しました
所長:柴山 知也[しばやま ともや]
理工学術院教授
研究テーマ
東日本大震災をはじめとする過去の甚大な災害を分析し、その複合災害としての特性を明らかにする。分析結果をもとにして新たな防災・減災のシステムを提案する
研究概要
- 津波被災機構:本研究所では、全国レベルでの課題として、防災対策の策定において想定されている津波の規模を見直すとともに、想定値に縛られずに、それを超える津波が来襲した場合にも対応可能な避難計画をあらかじめ作成しておくなど、日本全国にわたる防災計画の練り直しを提案し、その方法を考案する。具体的には全国の都道府県で、既に作成した津波ハザードマップの再検討を行い、県レベルでの防災計画を見直す必要がある。これまで生起する確率が比較的低いと考えられて防災計画に含まれていなかった地震にも焦点を当て、津波の予測シミュレーションの波源モデルを修正して、来襲する津波の予想波高をより高く設定しなおす必要がある。このため、既存の津波防潮堤などの防災構造物の嵩上げや津波水門の改築、津波水門閉鎖の自動化などのハード面での対策強化が必要になる。また既存津波防潮堤の越流現象の解明や洗屈防止策の検討が必要である。一方で、今回の津波では、防災構造物のみで居住地を守ることは困難であることがはっきりしたため、市町村レベルでの避難計画の修正というソフト面での対策も直ちに行う必要がある。
- 環境影響:津波によってもたらされた環境問題を研究する。ヘドロを含む堆積物や瓦礫の撤去作業に伴う有害物質を含有する粉じんの飛散、津波によって陸に打ち上げられた船舶の解体作業に伴って発生するアスベストの飛散、原子炉事故によって大気中に放出された放射性物質の広域拡散、放射性物質による農地表層土壌汚染とそれに伴う農作物汚染、放射性物質の土壌浸透に伴う地下水汚染などの困難な課題を解決すべく、総合的なフィールド調査と多岐にわたる対策技術の検討を行う。
- 複合巨大クライシス:大震災による福島原子力災害に焦点を当て、「原因評価」、「影響評価」、「対策評価」、「地域復興」といった災害プロセスを社会科学と技術工学の両面から考察する。4つのクラスター構成で研究を行う。(1)政治・行政・経営システム:福島原子力災害を引き起こした政治構造・行政構造・経営構造の解析とリスク・コミュニケーションのあり方、法制度のあり方、今後の復興のための政策統合と政治・行政・経営のあり方を研究する。(2)原子力エネルギー・技術システム:福島原発事故の技術的分析、安全管理や事故対応の技術システム、環境影響評価などを研究する。(3)持続可能なエネルギー・技術システム:再生エネルギーを組み込んだ分散エネルギー・システム、スマート・エネルギー、スマート・シティのあり方、持続可能なエネルギー戦略に向けた技術的基盤について研究する。(4)地域復興システム:政策統合を踏まえた地域復興のあり方を、地方自治体、地域社会、小規模集落の運営システム、地域企業の経営システムなどの視点から研究する。
研究所員
柴山 知也(理工学術院教授)
依田 照彦(理工学術院教授)
香村 一夫(理工学術院教授)
松岡 俊二(国際学術院教授)
リサーチ・アシスタント(RA)
山田 洋平
連絡先
理工学術院
柴山知也研究室
E-mail:shibayama(at)waseda.jp
(Please change (at) to @)