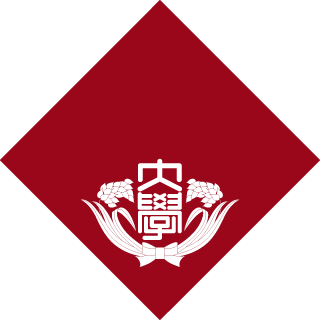JST 未来社会創造事業 本格研究 所課題
「製品ライフサイクル管理とそれを支える革新的
解体技術開発による統合循環生産システムの構築」
公開シンポジウム
ライフサイクル思考に基づく分離・解体技術の革新
循環型社会実現のために
開催概要
SDGsの中でも目標12「つくる責任つかう責任」に直接的に関係し、昨今のカーボンニュートラル政策においても一層の促進が重要視されている資源循環は、社会システム的にも技術的にも変革が求められています。
この要請に応えるため、未来社会創造事業「持続可能な社会の実現」領域において資源循環課題が立てられました。
本プロジェクトでは2017年より、新規電気パルス法を主軸とした省エネルギーかつ高精度な解体・分離技術を有効に適用することで、これを達成しようとしています。
本シンポジウムでは、新しい資源循環ループを創成する分離技術としての新規電気パルス法のポテンシャルのみならず、GHG評価および循環シナリオ評価といった社会的な成立性を考える手法についても最新の適用例を通じて概観し、今後多くのプレーヤーが参画し得る方向性を探ります。
主催
JST未来社会創造事業 本格研究 所課題グループ(研究代表 早稲田大学理工学術院 所 千晴)
早稲田大学 オープンイノベーション戦略研究機構
共催
早稲田大学 理工学術院総合研究所
早稲田大学 持続的環境エネルギー社会共創研究機構
早稲田大学 循環バリューチェーンコンソーシアム
後援
化学工学会、資源・素材学会、環境資源工学会、日本LCA 学会、エコデザイン推進機構、日本工学会
開催日時
2022年10月28日(金) 13:30~17:30
開催言語
日本語
開催方法
Zoom ハイブリッド開催 @早稲田大学 大隈記念講堂 小講堂/Zoomウェビナー
①会場:早稲田大学 大隈記念講堂 小講堂
②配信:Zoomウェビナー
お申し込み方法
事前登録制となります。ご参加を希望される方は、下記の各リンク先申し込みフォームよりご登録ください。
 ① 会場参加お申込み:https://forms.gle/LNeSeby8xZMuGaed9
① 会場参加お申込み:https://forms.gle/LNeSeby8xZMuGaed9
*定員200名(先着順):新型コロナウィルスの感染状況により変更となる場合があります。
② Zoom配信参加お申込み:https://w-as-jp.zoom.us/webinar/register/WN_f147koxFR0mooYEgc3J26A
チラシ
プログラム
13:00 開場
13:30 ~ 13:35 開会挨拶
 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部・環境資源工学科 教授
早稲田大学 理工学術院 創造理工学部・環境資源工学科 教授
所 千晴
13:35 ~ 13:40 運営統括挨拶
 JST 未来社会創造事業「持続可能な社会の実現」領域 運営統括
JST 未来社会創造事業「持続可能な社会の実現」領域 運営統括
國枝 秀世 氏
13:40 ~ 13:45 来賓挨拶
 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 戦略研究推進室 室長
文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 戦略研究推進室 室長
釜井 宏行 氏
13:45 ~ 14:10 基調講演1

車載電池業界の現状とサーキュラーエコノミー実現に向けて
(一社)電池サプライチェーン協議会 業務執行理事
森島 龍太 氏
脱炭素社会実現に向けて車載用電池のマーケットは急拡大し多くの課題に対し、電池のサプライチェーンの業界として、課題解決に向けた方針を提言する。とりわけ、バッテリーメタルの都市鉱山化は資源を有しない我が国において重要であり、その事業環境整備に向けたBASC内での取り組みについて紹介する。
14:10 ~ 14:35 基調講演2

接着技術の高度化と分離技術への期待
東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 教授
佐藤 千明 氏
接着技術は異種材料の接合が可能である利点があり、自動車などの軽量化の観点で注目されている。一方、接合した箇所が分離解体し難く、リサイクルできない複合物を作りだす問題を抱えている。この観点で接合部の剥離技術が求められている。本講演では、最近の接着技術を剥離技術と関連付けて解説する。
14:35 ~ 15:00 基調講演3

ライフサイクル評価の観点からみた循環経済型ビジネスのあり方と必要とされる技術
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部
環境・エネルギーユニット/持続可能社会部長・上席主任研究員
清水 孝太郎 氏
限りある資源を有効利用するためには、資源採掘から、製品製造、またその使用済み製品の廃棄及びリサイクルに至るまで、ライフサイクルの範囲で効率化を考えなければならない。これをビジネスの中で実現しようとするのが循環経済型ビジネスであり、そこでは高度な資源循環に資する従来とは異なる新技術体系が必要とされる。
15:00 ~15:20 研究全体概要
 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部・環境資源工学科 教授
早稲田大学 理工学術院 創造理工学部・環境資源工学科 教授
所 千晴
循環経済への移行を目指し適切な資源循環の技術開発とライフサイクル思考が求められている。当プロジェクトでは、カーボンニュートラル社会に必須のLiB、PV、軽量化材料を主たる対象とし、新しい分離技術とライフサイクル評価を通じてこの要請に応えようとしている。計画と成果概要、今後の方向性につき紹介する。
15:20 ~15:40 研究概要1

LiBリサイクルへの電気パルスの適用
熊本大学 産業ナノマテリアル研究所 准教授
浪平 隆男
電気パルスとは、パルスパワーとも呼ばれ、ナノ秒やマイクロ秒などわずかな時間ではあるものの、ギガワットやメガワットクラスの電力、「ちから」を有する電気エネルギーである。今回は、このパルスパワーをリチウムイオンバッテリーのリサイクルへ活用すべく、その急速加熱効果の最適化に成功したので、これについて紹介する。
15:40 ~16:00 研究概要2

マルチマテリアルへの電気パルスの適用
早稲田大学 理工学術院 講師
小板 丈敏
カーボンニュートラルに向けて、燃費向上のために自動車の車体軽量化が進められており、リユース・リサイクルにおける接着体の易解体技術が重要な技術となる。本講演では、資源循環に資するため、接着体および軽量化材のCFRPに電気パルスを適用した革新的な物理分離技術の研究開発状況を紹介する。
16:00 ~16:20 研究概要3

LiBとPVのライフサイクル思考
東京大学 未来ビジョン研究センター 准教授
菊池 康紀
カーボンニュートラルへ向かう社会において必須の設備であるLiBとPVは様々な資源を活用し製造されている。これらを持続的に社会で使い続けるためには、資源を循環する技術を適切にライフサイクルの中で活用できる必要がある。本講演ではライフサイクル思考に基づき、LiBとPVの持続的利用について考える。
<休憩>
16:35 ~17:25 パネルディスカッション
テーマ「資源循環への期待と課題」

▲ 長谷川 史彦 氏
<モデレーター>
所 千晴 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部・環境資源工学科 教授
<パネリスト>
森島 龍太 氏 (一社)電池サプライチェーン協議会 業務執行理事
佐藤 千明 氏 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 教授
清水 孝太郎 氏 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 持続可能社会部長・上席主任研究員
長谷川 史彦 氏 (独)製品評価技術基盤機構 理事長
17:25 ~ 17:30 閉会挨拶
 早稲田大学 理事(研究推進担当)
早稲田大学 理事(研究推進担当)
若尾 真治
お問い合わせ先(受付期間:2022年10月31日まで)
◆ シンポジウムの内容に関しては →[email protected]
◆ 参加お申込、Zoom配信に関しては →株式会社早稲田大学アカデミックソリューション/ [email protected]