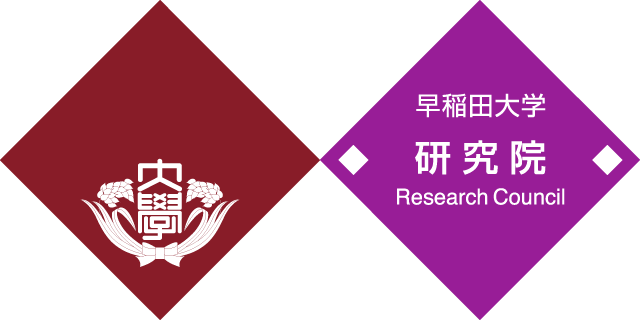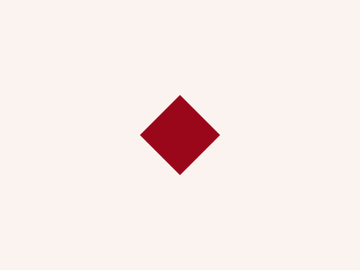早稲田大学イスラーム地域研究機構では、来る3月18日(月)に下記の通りイスラーム地域研究コロキウムを開催致します。
今回は、慶應義塾大学名誉教授の坂本勉氏をお招きし、19世紀末から20世紀初頭にかけての日本領有下の台湾を舞台としたイラン産アヘンの交易をめぐる総督府の対イラン政策、さらにはインド洋海域から南・東シナ海へとネットワークを広げた中東イスラーム世界出身の商人の活動とその意義についてお話しいただきます。参加自由ですので、ご興味・ご関心をお持ちの皆様方のご来場をお待ちしております。
●日時:2019年3月18日(月) 16時30分~18時
●会場:早稲田大学早稲田キャンパス11号館606教室 キャンパスマップ
※ 11号館6階にはエスカレーターでお越しください。エレベーターは停まりませんのでご注意ください。
●報告者:坂本 勉氏 (慶應義塾大学名誉教授)
●報告題目:イラン・アヘンと帝国日本の交易ネットワーク
●報告要旨:
日清戦争後、台湾を植民地として領有するようになった日本は、そこではじめてアヘン問題に直面する。台湾におけるアヘンの吸煙事情は、中国本土のようにインド産アヘンにその消費を依存する割合が比較的小さく、その多くをイランからの輸入アヘンに負うという特徴を有していた。ここから台湾総督府は早くからイランに対して関心を向け、アヘンの輸入貿易を行っていくようになる。
本発表ではこのようにしてはじまった日本領有下の台湾とイランとの間のアヘン貿易の問題、対イラン政策を取り上げ、それを通じて19世紀末以降帝国日本がその交易ネットワークとそれによって形成される広域的な経済圏をマラッカ海峡を越えたインド洋海域にまで拡大させ、イランを含めた中東イスラーム世界との関係を深めていく過程を明らかにしていくことにしたい。アヘンの輸入貿易は、日清・日露戦争後にグローバルな世界経済のなかに積極的に参入していくようになる帝国日本にとって、日本の産業革命の中核を担った綿紡績業とそれが生みだす綿製品の輸出貿易とともにその対外経済、国際貿易を成り立たせるのに欠かすことのできない両翼のひとつであったという意味で経済的にきわめて重要なものであった。
他方、1870年代に大飢饉に見舞われたイランにとってアヘンの商業的生産と輸出は、疲弊した国の経済を回復させる活路のひとつであった。その輸出先として重要だったのが、台湾を含む広大なアジア市場である。これをめざしてさまざまな商人がイランからボンベイ(ムンバイ)、シンガポール、香港へとその広域的な交易ネットワークを延ばしていくようになるが、こうした中東イスラーム世界出身の商人たちの東方への進出の問題を、これまでイスラーム世界史のなかで強調されてきたインド洋海域から南・東シナ海にかけてつながるネットワーク論を踏まえながら再検討してみたいというのが本発表のもう一つの狙いである。史料的にはペルシア語史料はさほど多いとはいえないが、これを補うものとして近年閲覧が容易になってきた台湾総督府文書を紹介しながら、具体的に話していくつもりである。
※ 本コロキウムに関するお問い合わせは、下記メールアドレス宛にお願いいたします。
宛先: islam-info [at] list.waseda.jp