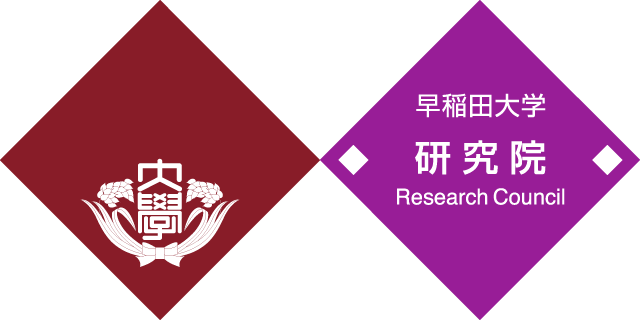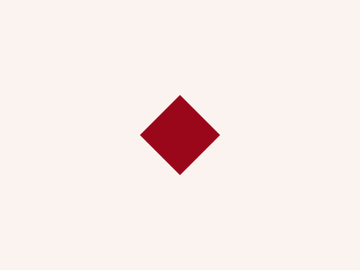イスラーム地域研究コロキウム(2017年2月15日開催)
報告者:佐藤秀信氏(外務省職員)
報告題目:現代イランの国民動員組織と政治社会
‐ イスラーム革命防衛隊国民動員部門「バスィージ」の軌跡(1979-2016) ‐
去る2月15日に開催されたイスラーム地域研究コロキウムでは、外務省の佐藤秀信氏に報告を行っていただいた。佐藤氏は早くも2000年代初頭の時点でイラン政治における「新保守派」および革命防衛隊の台頭に着目され、その後1979年のイラン革命後から近年に至るまでのイラン政軍関係の変容について、革命防衛隊を主たる考察対象にして多くの論考を著してきた気鋭の研究者である。今回の報告は、佐藤氏が長年考察を続けてきたイラン革命防衛隊傘下の国民動員部門バスィージについて、組織の拡大と変容、さらに国民動員部門としての社会管理の促進に焦点を当てて考察するものであった。
実際の報告では、まずパフラヴィー朝末期における国民動員政策とその限界についての解説が提示された後、1979年の革命防衛隊の設立とバスィージの組織化と特徴、および拡大の過程とその背景の説明がなされた。最初期の革命防衛隊とバスィージは、ホメイニーを支持する若者ら非軍人の革命勢力が組織の中核を担ったことから、国軍とは異なる「プロフェッショナル的」でない組織文化を形成し、さらにイラン・イラク戦争での兵力需要の高まりがバスィージの組織化を促したとの指摘がなされた。続けて、ホメイニー没後から改革派が台頭する80年代最末期から2000年代前半期のバスィージの変化が取り上げられた。注目すべきは、この時代において、文教・開発など非軍事分野へのバスィージの進出を容認する法制度が整備され、その運用も徐々に進められた点である。当時バスィージは、ハーメネイー最高指導者の権威確立や「文化侵略」への対抗等の必要性から、80年代のベビーブームで誕生した多数の若者の取り込みを目指していく。報告ではその取り込み策に関し、文教部門での具体例の紹介を交えつつ説明が行われた。最後に2005年のアフマディーネジャード政権誕生以降のバスィージにつき、組織出身の内閣・各省庁への多数の人材の登用による政治的発言力の向上や文教部門での活動拡大、さらに同政権のポピュリスト的政策による厚遇や2009年大統領選後の混乱への介入等で、その政治・社会面での活動がさらなる広がりを見せたことが指摘された。但し、その一方で、バスィージを巡りイラン社会の亀裂が深まっていったことについても言及がなされた。
報告後の質疑応答では、組織における女性や外国人構成員の存在と彼らの役割、バスィージに対して組織外の市民が抱く感情といった、現在の同組織を巡る質問が多数出された。加えて、当初ホメイニー支持を掲げていたこの組織が、現在忠誠を誓う対象(「法学者の統治」、個人としてのハーメネイー最高指導者…)はいったい何なのか、といった今後のイラン政治の展開に結びつく問いも出され、活発な議論が交わされた。
バスィージの組織拡大と国内社会の制御の試みについて、議会議事録、法令、機関誌、報道等幅広い資料を駆使してその解明を試みた今回の報告は、他に類のないものであると同時に、今後のイラン政治の変化を考える上でも重要な材料を提供するものであったと言える。激務の中、報告を快く引き受けて下さった佐藤氏にこの場を借りて御礼申し上げたい。(杉山隆一)
※なお、本コロキウムにおいて報告者(佐藤秀信氏)が示した見解は、報告者の勤務先及び日本国政府の見解一般を表したものではないことを付記しておく。