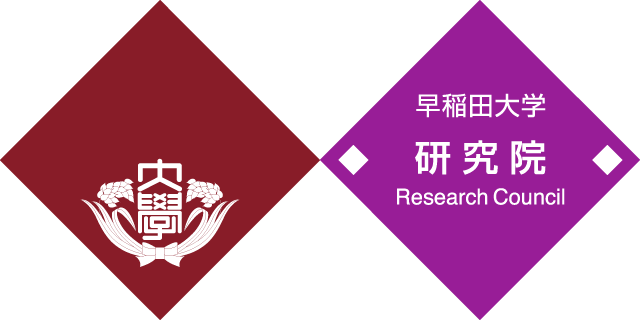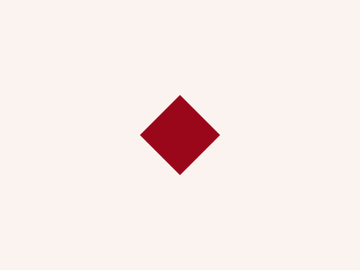「前近代イスラーム社会知識人再考」第3回研究会(2016年12月25-27日開催)
場所:早稲田大学120-4号館405会議室(25-26日)、同120-5号館124会議室(27日)
参加人数:10名
イブン・ハルドゥーン自伝研究会は12月例会を3日連続研究会という形式で行い、研究代表者の佐藤健太郎(北海道大学)、研究分担者である中町信孝(甲南大学)、五十嵐大介(中京大学)に加えて7名の研究協力者(中村妙子、吉村武典、原山隆広、橋爪烈、柳谷あゆみ、荒井悠太、福光叶恵)が参加した。
初日はヒジュラ暦799年にマムルーク朝スルターン、ザーヒル・バルクークと、マグリブの諸王朝(チュニスのハフス朝、トレムセンのザイヤーン朝、フェスのマリーン朝)の間で書簡と贈り物のやり取りがなされた件について、『自伝』当該箇所の訳読(担当:中町信孝)に基づき、その内容の検討を行った。2日目は、まずヒジュラ暦801年のマムルーク朝スルターン、ザーヒル・バルクークの死後にカイロで起こった政変の顛末と、同時期のイブン・ハルドゥーンの動向(マーリク派の大カーディー職への再任・解任、シリア・パレスティナ地方への旅行など)について、『自伝』当該箇所の訳読(担当:五十嵐大介)に基づき、出来事の整理と内容の検討を行った。ヒジュラ暦9世紀初頭にはティムールがシリア・パレスティナ地方に遠征しており、『自伝』巻末の話題は、ティムールがその末裔であることを主張したモンゴルについて、イスラーム史上での位置づけから始まる。2日目後半及び3日目はこの部分の訳読(担当:柳谷あゆみ)を進め、イブン・ハルドゥーンのイスラーム史観の検証を行った。この3日間の検討箇所は、マムルーク朝を中心として、マグリブ諸国及びモンゴルとの交渉にかかわる情報や知見を含んでおり、ヒジュラ暦9世紀前後のイスラーム世界の交流史を読み解くうえで貴重な史料といえる。
(文責:柳谷あゆみ)