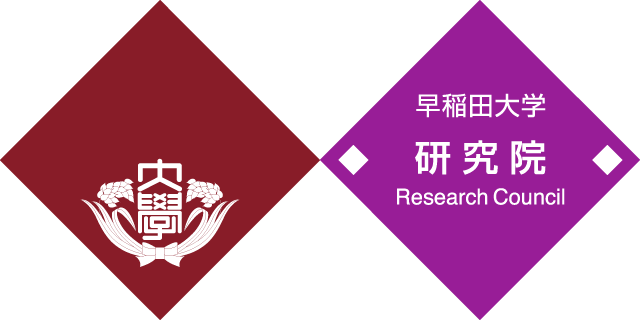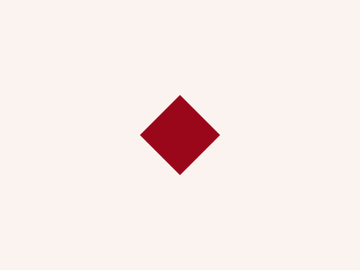早稲田大学拠点では、2月12日(木)早稲田大学22号館において、公募研究「メガシティとしてのイスラーム都市—ジャカルタとカイロを中心に」2014年度第3回研究会を開催しましたので、報告を掲載いたします。
今回の研究会の発表者は長谷川氏、深見氏の2名であり、最初に長谷川氏の発表が行われた。
長谷川氏は、「前イスラーム時代の都市・村落―エジプトの事例―」と題する発表を行った。同時代の都市・村落がどのような構造を有し、どのような立地の仕方をしていたか、宗教、生態環境の観点から考察を行った結果が報告された。事例として取り上げられた都市は、メンフィスおよびアレキサンドリアである。メンフィスはエジプト固有の多神教を基本とした思想が反映された都市地域構造を有し、とくに水辺空間を生と死の世界の境界的空間として位置づけるという特徴をもっていた。変動するナイル川の流域に位置し、居住環境を維持するという目的によって都市の立地を移動させており、それによって河川やその周辺の湖との関係は変化していった。他方、アレキサンドリアは、歴史的巨大都市であり、外来政権が地域の統治を進める目的も兼ねて建設した水運ネットワークによって、地中海と内陸部とも接続された都市として、当時としては圧倒的な規模に成長した。メンフィスとアレキサンドリアの両都市は、宗教的あるいは政治的な思惑によって建設されつつも、依拠していた生態環境との関係によって盛衰を経験した都市と思われる。2大都市に関する報告の後に、衛星観測データを利用した村落の立地および遺跡の内部構造の調査に関する報告がなされた。光学センサを利用した遺跡分布の推定手法に加え、磁気探査による遺跡の内部構造の調査手法が紹介され、景観復元に至る発掘調査にとって重要な知見が提示された。
深見氏からは、「都市の類型と都市の巨大化:メガシティへの進化と多様性」と題する発表がなされた。歴史軸および地域軸において、形態(市壁の有無、街区形状、密度、階層)によって類型化された都市の位置づけが提示された。対象都市は特定の地域の都市ではなく、既往研究によって1800年以前に都市人口の記述のある459都市を対象としている。メガシティを含む大都市がどのような類型を経て巨大化したか報告された。メガシティの発展パターンは、固有性と共通性を有するものであることが歴史的、地域的観点からの考察によって提示された。また、メガシティにおいて、地域的に共有された都市間関係、居住環境の割合が変化し、現代に至り、とくに居住環境については地域的に共有されていたものとは異なる、世界的な共有された居住環境がメガシティの都市域において広域に広がりつつあることが指摘された。
全体討議においては、とくにメガシティを含む都市を形態によって分類することの意義と課題について議論がなされた。形態を固定することによって、それを成立させている、文化、政治などの要素の影響を考えるということが、深見氏の都市類型の考察手法においては可能であるが、地域性や都市の機能(政治や商業)などの要素が複合的に影響した結果成立している都市形態を類型化する際に、類型化するための指標を簡素化し過ぎると、それらの影響を的確に考察しにくくなる可能性が指摘された。また、形態によって類型化を行った都市について、歴史的な変化を考察する際に、対象とする都市の文化や政治に焦点をあてるということは、周辺の都市地域との関係の在り方の変化の影響を理解するということであり、同時にとくに都市内部の権力の空間的なバラつきの影響を考察するということであることが、今後の課題として議論において共有された。長谷川氏の都市の立地および都市の内部構造の議論は、上記の議論に接続するものであり、全球都市、メガシティの進化を捉える方法論における課題への対応の手掛かりが見出された。
文責:内山愉太(総合地球環境学研究所)