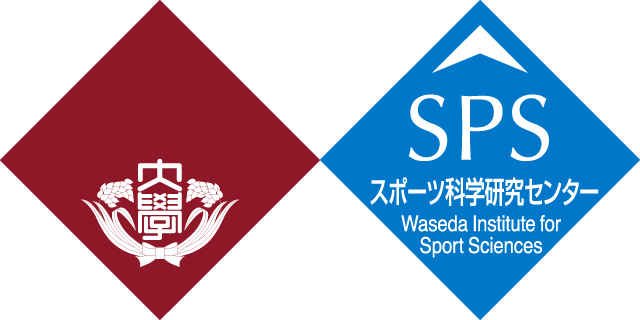出版物

スポーツ科学研究
Sport Sciences Research
掲載論文
以下のリンクより、掲載論文を閲覧いただけます。
早稲田大学リポジトリ J-STAGE
発刊の言葉
| 山崎勝男 (スポーツ科学学術院 スポーツ科学部長 2004年10月1日)
この度,懸案の 「スポーツ科学研究」 がオンラインジャーナルとして発刊される運びとなりました。いよいよ早稲田大学所沢キャンパスから、スポーツ科学の情報を日本全国はもとより、世界に向けて発信する誠に喜ばしい事態を迎えたことになります。この 「スポーツ科学研究」 の発刊につきましては、編集委員会で相当の議論をしました。当初は従来型の紙媒体で、コンテンツも従来型を踏襲するのが妥当ではないかという意見もありました。しかしながら、このスタイルを採る限り、何ら面白みがなく、多様な情報は発信できないという意見も多く出されました。そこで発想を転換し、最終的にジャーナルの性格は実験室的研究から踏み出したものにしようということにまとまりました。編集委員会の案内によりますと掲載する論文のカテゴリーは、(1) 実践報告、(2) アイデア、トッピクス、(3) 原著論文、(4) 授業研究、(5) 解説記事、資料となっており、研究とフィールドのリンクを目指したことが明らかです。この編集方針は、以下に示す学部設立の理念や目的と合致するように思われます。早稲田大学は第 10 番目の学部として、2003 年 4 月にスポーツ科学部を誕生させました。学部設立の理念は、「スポーツ文化を創出し、人間の幸せに貢献する」ことであり、スポーツ科学部が目指す目的は、1) 国際的に通用する選手を作り出す人材の育成、2) 怪我の管理やコンデショニングを適切に指導出来るハイレベルのトレーナーの育成、3) スポーツビジネスを担える人材の育成、4) 少子高齢化社会における健康の維持と管理が出来る人材の育成、5) スポーツによって生活の質を高められる人材の育成、としています。これらの目的を達成することは、またスポーツ科学に寄せられている社会的な要請でもあります。それらを端的にまとめますと、スポーツニーズ、ソーシャルニーズ、パーソナルニーズとなります。このようなニーズに応えて、「スポーツ科学研究」 というオンラインジャーナルを発刊する所以も、まさに私達の具体的な努力の強化を自ら願ってのことであり、同時に、これを通して新しい 「スポーツ科学」 の情報交換の場が実現されれば幸いと願っております。編集委員長の言にもありますように、「スポーツ科学研究」は誰でも、何時でも、何処からでも自由に投稿できる開放的なオンラインジャーナルとなっております。多くの方々からのご指導、ご鞭撻を賜り、今後この 「スポーツ科学研究」 がスポーツ科学の先駆的役割を果たす機関誌に育っていくようご支援、ご協力をお願い申し上げる次第です。■ |
発刊の目的
福永哲夫 (初代編集委員長)
スポーツ科学に関する研究雑誌は少なくない。その多くは身体運動のメカニズムに関する研究を収録したものである。多くの研究がそうであるように、科学的研究とは客観性や再現性が保証されていなければならない事が多い。 一方、スポーツ現場では時々刻々変化する環境条件に心と身体が適応しながら身体運動が実施される。この場合、その変化する環境条件とそれに対応する心身の状態とを再現する事は困難な場合が多い。例えば、自己ベスト記録が10秒21である陸上選手が2度と同じタイムをだせる事が出来るとは限らない。つまり、スポーツの記録は様々な因子の複雑な作用により影響され、ベスト記録を生み出すための最適な条件は簡単に再現されるものではないからである。 さらに、野球やサッカー、ラグビー等のチームスポーツになればその因子はさらに複雑になり、科学的客観的分析に求められる再現性を作り出すことが困難になる。ここに、生きている人間が実施するスポーツ現象への科学的アプローチの困難さが読み取れる。生きている人間を対象とする学問である以上、様々な条件をコントロールすることは困難な場合が多い。スポーツ科学は人間科学でもあり、様々な領域からの科学的アプローチが求められる。 一方、個々の人間が実施しているスポーツ現象を正確に報告することは、其の研究事例が多くなればなるほど人間が実施するスポーツ現象に関わる普遍的な原理原則を抽出する事が出来るようになる。このような数多くの事例研究が集積されることが、新しいこれからのスポーツ科学を発展させることにつながるであろう。 スポーツ科学の中でも自然科学的領域では比較的条件設定が容易である場合が多いが、それでも研究のアプローチは簡単ではない。例えば、身体運動を様々な関節運動に分析し、それぞれの関節運動を科学的に分析する研究は多い。しかし、個々の関節運動の機構が明らかになったとしても、総合された身体運動のメカニズムを解明できるとは限らない。多数の関節が参加して運動が行われる場合には、単一の関節の機能の総合和ではなく、複数の関節の動きそのものがユニットして別の機能を発揮する場合が多いからである。 とはいえ、現在まで数多くのスポーツに関するデータの収集が行われ、その結果に基づき、適切なスポーツの指導や効果的なトレーニングが実施されているのも事実である。特に、近年の様々な機器の発達により、簡単にかつ正確なデータ収集が可能になっている。例えば、テレビのスポーツ中継では投手(野球)の投げた球速が瞬時に計測され、ボールの軌跡が画面上にほとんどリアルタイムで現され、毎秒5000コマでの高速度ビデオでボールとバットのインパクトの瞬間が映像化されている。 このようなスポーツに関する情報はテレビ等を通じて氾濫している。それぞれの情報は大変興味あるデータとして捉えられているが、そのデータは殆どがその場限りで捨てられる場合が多い。 上記の例に見られる様に、様々なスポーツに関する事象が数多く記録されているはずにも関わらず、そのデータや情報がスポーツ科学の研究論文として研究誌などに掲載されているのはまれであると言えよう。小学校から大学まで、さらに、社会におけるスポーツ教室まで、スポーツ教える教育の現場においてもこのことは当てはまる。様々な指導法や練習方法が考案されているにもかかわらず、その結果が研究論文として発表されているのは極めて少ない。 「スポーツ科学研究」は、スポーツ事象に関わる様々な現象を論文として収録しようと企画された研究雑誌である。従って、グランドや体育館で実施されているスポーツ現場の指導やトレーニングの具体的な例などに関する論文を数多く収録していきたいと考えている。例えば、特別な選手に関する例外的なデータであっても、そして、そのデータを普遍化するための統計的手法などがとられていなくても、掲載していきたいと考えている。 前述のように、そのような具体例に関する論文が数多く収録されることから、スポーツ事象に関する客観的科学的事実が生まれてくることが期待されるからである。つまり、多くのスポーツに関わる人たちによるスポーツ現場の具体例の積み重ねにより、生きている人間の行うスポーツ活動に関する生きた科学が生まれてくることを確信しているからである。 「スポーツ科学研究」は早稲田大学スポーツ科学部により出版されるが、投稿は自由で誰でも可能である。編集方針として、スポーツ科学に関するあらゆる分野の論文に対しても査読を行いより良い論文としての価値を高める予定である。また、オンラインジャーナルとして投稿から出版までの時間を出来る限り短縮する予定である。「スポーツ科学研究」に全国のスポーツに関わる人々の論文が集積され、スポーツ現場に利用されることを期待するものである。■ |
「スポーツ科学研究」への寄稿
「スポーツ科学研究」では、学術論文の投稿を受け付けています。
論文の投稿を希望される方は、以下の規程各種および論文投稿についてをご一読ください。
投稿規程
「スポーツ科学研究 (Sport Sciences Research) 」 は,スポーツ科学の発展とスポーツ競技力の向上ならびに健康・体力の維持・増進に寄与することを目的とする.この目的を達成するため,以下のように投稿規程を定める.
I. 投稿者の資格
スポーツの競技力向上や,健康・体力の維持・増進に努める指導者,選手,リハビリテーション従事者およびスポーツ科学に携わる研究者とする.
II. 投稿締切
投稿原稿は随時受付する.
III. 投稿原稿の種類
論文の種類は,スポーツ科学に関する原著論文,総説,資料とする.
1. 原著論文
科学論文としての内容と体裁を整えているもので,新たな科学的な知見をもたらすものであることが必要である.ただし,人文系と自然系の論文構成には違いがあるため,論文の構成や見出しはそれぞれの研究領域に応じて適切なものを用いること.
2. 総説
特定の研究領域に関する主要な文献内容の総覧であるが,その内容は,単なる羅列ではなく,特定の視点に基づく体系的なまとまりを持つことが必要である.
3. 資料
調査や実験の結果を主体にした報告であり,スポーツ科学の研究上,客観的な資料として価値が認められるものである.この場合,原著論文に必要な見出しや,それに相当する内容のすべてを含む必要はないが,関連研究とのつながりの中で,その資料を提出することの意義が明らかであり,資料そのものの説明が十分になされていることが必要である.スポーツに関するアイデア,意見およびトピックス,学会・競技会報告,書評等も含まれる.
IV. 研究倫理
スポーツ科学に関する原著論文,総説,資料は,原則として,早稲田大学が定める研究倫理に関する規程に則ったものとする.特に,早稲田大学の「人を対象とする研究に関する倫理規程」「生物実験安全管理規程」(「生物実験安全管理規程(遺伝子組換え実験)施行細則」「生物実験安全管理規程(動物実験)施行細則」を含む.)「病原体等の管理に関する規程」に定められた審査に該当する研究については,当該審査を受け,承認番号を投稿論文に記載するものとする.他機関で行った研究に関しては,原則として,当該機関ないしその他の機関での倫理審査を受け承認されたもののみを対象とし,その承認番号を投稿論文に記載するものとする.
V. 投稿原稿の形式
1. 原稿はスポーツ科学研究ホームぺージ上のオンライン投稿システムより投稿する.別に定める投稿用テンプレートを使用する.制限頁数は投稿用テンプレートを使用して40頁以内とする(本文,抄録,図表,文献を含める).著者が特定されないよう著者の名前,所属機関等の識別情報を削除した論文も提出する.
2. 図表は,本文に挿入する.
VI. 投稿原稿の内容
1. 原稿の種類
原著論文,総説,資料のいずれかを選択する.
2. 原稿は日本語,英語のいずれかで執筆する.
3. 論文表題
3.1 論文が和文の場合,和文・英文表題を記載する.
3.2 論文が英文の場合,英文表題を記載する.
4. 抄録
和文の場合600字以内,英文の場合300語以内とする.抄録は本文の言語に合わせる.
5. キーワード
3~5語.日本語・英語どちらでも可とする.
VII. 原稿作成要領
1. 本文はスポーツ科学研究ホームページより,投稿用テンプレートをダウンロードして使用する.
2. 見出番号は,I. II. III. ・・・,1. 2. 3. ・・・,1) 2) 3) ・・・,① ② ③ ・・・ の順とする.
3. 原稿の下部中央にページ番号をつける.
4. 数字は算用数字を用い,数字・英字は半角とする.
5. 単位は国際単位系(SI)を使用する.
6. 文末に参考文献リストを作成する.文献リストの見出し語は「参考文献」とし,本文中に記述された引用及び参考文献についてのみ記載することを原則とする.文献の記載は著者名のアルファベット順とし,各文献の2行目以降は1文字下げて記載する.
1) 雑誌の場合
著者名(発行年)論文タイトル.雑誌名,巻(号):ページ.の順とする.
① 著者名および発行年
共著の場合,和文の場合には中黒(・),英文の場合には“and”で続ける.ただし,英文で3人以上の場合にはコンマ(,)でつなぎ,最後の著者の前だけに“and”を入れる.発行年は著者名のすぐ後の( )内に記入し,論文名と区切る.著者名の前に番号は不要とする.本文中の表記で同一著者であり,かつ同発行年の複数の論文を引用した場合は年号の後に a, b, c, …をつけて区別する.
例1 阿江通良・湯海鵬・横井孝志 (1992)
例2 Morris, R., Tod, D., and Eubank, M. (2017)
例3 Brown, S. (2013a) This study contributes to….
② 論文タイトル
論文タイトルの文末はピリオド(.)とする.英文では,論文タイトルの冒頭の文字,固有名詞の冒頭の文字を大文字にする.
③ 雑誌名
和文誌の場合は略記しないで記載する.英文誌の場合は,該当雑誌の指定された略記法,または広く慣用的に用いられている略記法に従う.
④ 巻号およびページ
同一巻が通しページとなっていない場合には,号数を( )で巻数の後に示す.
例4 Hunter, J. P., Marshall, R. N., and McNair, P. J. (2004) Interaction of step length and step rate during sprint running. Med. Sci. Sports Exerc., 36: 261-271.
例5 Taylor, D. (2007) Performance efficiency rating for basketball. Coach and Athletic Direction, 26(1): 26-28.
例6 谷めぐみ・長ヶ原誠・長岡雅美・伊藤克広・玉井久美代・増富真子 (2015) 自治体における成人人口を対象とした運動・スポーツ推進事業と市民の実施頻度・継続期間・組織所属との関連性. 生涯スポーツ学研究. 12(2): 1-13.
例7 村岡康博・堀田曻 (1991) 高校一流水球選手の形態・体力. 健康科学, 13: 139-142.
⑤ 早期公開論文
正式に発刊される前の早期公開論文を引用する場合は,以下の例を参照し,巻(号),ページの代わりにDOIを記載する.発行年は早期公開年を記載する.
例8 安田純輝・吉永武史・金沢翔一・深見英一郎 (2024) 小学校体育科の水泳運動における第 3 学年児童を対象としたけ伸び習熟のための等質ペア学習を適用した学習指導方略の実践.体育学研究,https://doi.org/10.5432/jjpehss.23018
⑥ 未公刊論文
印刷公刊されることが確定してはいるが未刊の場合,発行年の代わりに“(in press)”と記載する.未公刊論文を引用する場合は,査読者より提供を求める場合がある.なお,原則として公刊されることが確定していない論文の引用はできない.
例9 並木伸賢・堀野博幸 (in press) 大学生アスリートのキャリア困難感尺度の作成の試み.スポーツ科学研究,20.
2) 単行本の場合
記載方法の原則は雑誌の項に従う.
① 単行本の全体を参考文献とする場合
著者名(発行年)書名(版数,ただし初版は省略).発行所.の形式とする.また,編集(監修)書の場合には,「編」,「監」,あるいは「編著」と表記する.英文では編集者が1 人の場合は (ed.) ,複数の場合は (eds.) をつける.
例10 小塩真司 (2018) SPSS と AMOS による心理・調査データ解析(第三版). 東京図書.
例11 Wilmore, J. H. and Costill, D. L. (2004) Physiology of Sport and Exercise (3rd ed.). Human Kinetics.
例12 柳沢和雄・木村和彦・清水紀宏編 (2017) テキスト 体育・スポーツ経営学.大修館書店.
例13 Nicholas, H. and Margaret T. (eds.) (2011) Lifelong engagement in sport and physical activity: Participation and performance across the lifespan. Routledge.
② 単行本の一部を参考文献とする場合
論文(章)著者,論文(章)の題名.編集(監修)者名と「編」,「監」,「編著」など,書名(版数,ただし初版は省略).発行所,論文(章)のページ(p.またはpp.)の形式とする.英文の場合には,論文(章)の題名.の後に“In:”をつけたあと編集(監修)者名と (ed.) ,または (eds.) を記載する.編者が2名の場合,和文の場合には中黒(・),英文の場合には“and”でつなぐ.ただし,編者が3名以上の場合は,筆頭編集(監修)者の姓の後に,和文の場合には「ほか」,英文の場合には“et al.”を用いる.
例14 Peponis, J. and Wineman, J. (2002) Spatial structure of environment and behavior. In: Bechtel, R. B. and Churchman, A. (eds.) Handbook of environmental psychology.John Wiley, pp. 271-291.
例15 鈴木守 (2006) NF の組織化の現状と課題. 佐伯年詩雄監・菊幸一・仲澤眞編, スポーツプロモーション論. 明和出版, pp.100-114.
③ 翻訳書の場合
原著者の姓をカタカナ表記し,その後ろにコロン(:)をつけて訳者の姓名を記載する.共訳の場合は中黒で,訳者が3人以上の場合は「:…ほか訳」と省略して筆頭訳者だけ記載する.翻訳書の場合,原著を引用したときは,原著の表記を最後に<>内に記載する.
例16 ロッシ・リプセイ・フリーマン: 大島巌ほか訳 (2005) プログラム評価の理論と方法 : システマティックな対人サービス・政策評価の実践ガイド. 日本論評社.<Rossi, P.H. (2003) Evaluation: A systematic approach (7th). Sage.>
例17 アメリカスポーツ医学会編:日本体力医学界体力科学編集委員会監訳(2006)運動処方の指針原著第7版.南江堂.
3) ウェブサイトの場合
参考文献リストには「著者名(発行年またはonline)ウェブページの表題,ウェブサイトの名称,URL,(参照日)」を記載する.
例18 文部科学省 (2023) 令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果, https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1411922_00007.html, (参照日2024年8月5日) .
例19 スポーツ庁 (online1) 政策, 学校体育・運動部活動, 小学校体育(運動領域)指導の手引~楽しく身に付く体育の授業~, https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/1371875.htm, (参照日2024年7月30日).
例20 スポーツ庁 (online2) 政策, 学校体育・運動部活動, 令和3年度地域運動部活動委託事業成果報告書, https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405721.html, (参照日2024年7月30日).
例21 EU Expert Group on “Education and Training in Sport” (online) EU guidelines on dual careers of athletes: Recommended policy actions in support of dual careers in high-performance
Sport, https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf, (accessed 2023-05-01)
7. 参考文献を本文に引用する場合は,著者名,発行年,引用ページを記載する.引用した文献はすべて参考文献リストに記載する.
例1 「学生アスリートの先駆者」(池田,2018) と言われる・・・.
例2 “Modifying the built environment attributes” (Koohsari, 2023) と表記し・・・.
1) 著者が 2 名の場合,和文の場合には中黒(・),英文の場合には“and”でつなぐ.著者が 3 名以上の場合は,筆頭著者の姓のあとに,和文の場合には「ほか」,英文の場合には“et al.”を用いる.
例3 「・・・・・」(武田・池上,2013) という考察は・・・
例4 “…..” (Hoffman and Weiss, 2016) という考え方には・・・
例5 「・・・・・」(小林ほか,2019)という結論は・・・
例6 “…..” (Morris et al., 2017) の研究は・・・
例7 「・・・・・」(高橋編,2013)という意味で・・・
2) 引用ページをする場合は,著者名,発行年,引用ページを記載する.引用ページが複数ある場合には,括弧内の引用ページをコンマ(,)でつなぐ.なお,文献全体を参照しているなど,参照ページが限定できない場合には,ページは省略できる.
同一著者の文献が複数ある場合には,括弧内の発行年をコンマ(,)でつなぐ.
「ほか」や“et al.”に対応する共著者が異なる場合も含めて,本文中の表記で同一著者であり,かつ同一年に発行された複数の論文は発行年の後に a, b, c, d ・・・をつけて区別する.複数の文献が連続する場合はセミコロン(;)でつなぎ,筆頭著者のアルファベット順を優先して列挙する.
例8 伊東ほか(2012)によれば・・・
例9 青山(2002,pp.128-131)は・・・
例10 佐藤(2015,pp.104-108,pp.208-212)の報告では・・・
例11 岡部ほか(2016a, 2016b)による研究では・・・
例12 伊藤・藤森(2019, p.10)によれば・・・
例13 Omar (2015, pp.7-11)および Bullock et al. (2017, p.12)は・・・
例14 Bagozzi and Yi (1988, p.460) が示した・・・
例15 Chen (2009, 2012) の先行研究では・・・
例16 …と判断した(小塩,2018,pp.170-184;伊藤・三倉,2021,pp.5-9;竹村ほか,2013,pp.484-501).
例17 取り組む考え方などがあり(Ramos et al., 2017, pp.118-120; Ryba et al.,2017, pp.137-140),
3) 翻訳書の著者を表記するときは,カタカナ表記とする.
例18 グリフィン(1999,p.124)によれば・・・
4) ウェブサイトに掲載されているPDFファイルなどを参考文献とする場合は,(著者名,発行年)または(著者名,online)を記載する.発行年やファイル名が特定できない場合は,(著者名,online)と記載する.同一著者が同一年に複数のウェブサイト掲載した場合の引用は,発行年の後ろにa, b, c, ・・・をつけて区別し,発行年が特定できない場合は文献リストの表示順(1, 2, 3,・・・)をつけて区別する.
例19 公益財団法人日本スポーツ協会 (2023) の調査では,・・・
例20 との報告がある(文部科学省,online1).一方で,文部科学省(online 2)に
よれば,・・・
8. 図表はカラーも可とする.写真および図表に含める.図表にはタイトルをつける.
VIII. 原稿提出方法
原稿提出ならびに投稿に関する問い合わせは早稲田大学 スポーツ科学研究センターホームぺージ(https://www.waseda.jp/fsps/rcsports/)上で受け付ける.
IX. 原稿の受理および審査
原稿投稿後,「スポーツ科学研究」編集事務局で受付を行い,投稿者のメールアドレス宛に受付通知を送信した日を受付日とする.掲載決定を投稿者のメールアドレス宛に通知した日を受理日とする.投稿された原稿はすべて編集委員会による審査を受ける.
X. 日本語論文の英語版の再投稿
本誌に受理された日本語の論文・資料について,投稿者はその英語版を本誌に再投稿することができるものとし,これについて以下のように定める.
1. 投稿者はこの英語版について,英文としての完成度を担保するものとする.
2. 編集委員会は内容の再査読は行わないが,英文としての完成度を審査し,掲載の諾否判断あるいは投稿者への修正依頼を行う.
3. この英語版を本誌に掲載するに際しては,そのタイトルページに二次出版資料であること,および日本語版,英語版それぞれの発行日を編集委員会が記載する.
XI. 掲載料
「スポーツ科学研究」への掲載は無料とする.
XII. 著作権
投稿された原稿の著作権の取扱いは,別に定める著作権規程による.
なお,投稿者は,本規程に同意したものとする.
XIII. 二重投稿および自己剽窃の禁止,および学位論文について
本誌への投稿は未刊行のものに限る.二重投稿,自己剽窃は認めない.ただし,機関リポジトリ等で公開されている学位論文(修士論文・博士論文等)の扱いについては以下に定める.
1. 学位論文の投稿について
学位論文と同一内容の投稿については,二重投稿,自己剽窃とみなされない.ただし学会等が発行する学術誌・学術書籍において未刊行の場合に限る.学位論文を投稿する場合は,付記に学位論文であることを明記する.
2. 学位論文への転載について
本誌に掲載した論文を学位論文に転載(一部の転載も含む)が認められる.その場合は,学位論文に書誌情報を記載し,修正を行った場合はその旨を明記する.
XIV. 著者校正
採択後の論文の著者校正は,原則として 1 回とする.
附 則 この規程は 2009年12月15日から施行する.
附 則 この規程は 2024年9月5日から施行する.
附 則 この規程は 2025年4月17日から施行する.
お問い合わせ先:
〒162-0801 東京都新宿区山吹町 332-6 パブリッシングセンター(株)国際文献社内
「スポーツ科学研究」編集事務局
Email: [email protected]
著作権規程
著作権規程
(趣旨)
第1条 本規程は、早稲⽥⼤学スポーツ科学学術院(以下「本学術院」という。)の学会誌である「スポーツ科学研究」(以下「学会誌」という。)に投稿されたスポーツ科学に関する総説、論⽂または資料(以下「論⽂」という。)の著作権の帰属について、著作者および本学術院間の権利関係を明確にし、適正な運⽤を図ることを⽬的とする。
(著作権の帰属)
第2条 著作者は、学会誌に投稿した論⽂に関する⼀切の著作権(著作権法第27条および第28条を含む。)を無償で本学術院に譲渡し、本学術院が当該論⽂を受領した時点で、著作権は本学術院に帰属する。ただし、論⽂が学会誌に掲載されない旨が決定された場合は、著作者に対してその決定通知の発信と同時に、著作権は著作者に返還されるものとする。
2 前項の著作権とは、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(⼝述権)、第25条(展⽰権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権)および第28条(⼆次的著作物の利⽤に関する原著作者の権利)をいう。
(リポジトリシステムへの登録等)
第3条 著作者は、論⽂が学会誌に掲載された際、本学術院が論⽂を、以下のシステムへの登録および公開による公衆送信を⾏うことを、あらかじめ承諾する。
⼀ 早稲⽥⼤学リポジトリシステム
⼆ 国⽴情報学研究所の研究紀要ポータルシステム
三 国立研究開発法人科学技術振興機構のJ-STAGE
(著作者⼈格権)
第4条 著作者は、学会誌へ投稿し、著作権を譲渡した論⽂の著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
2 本学術院は、著作権を⾏使する場合は、著作者の名誉・声望を害することのないよう⼗分に配慮するものとする。
(著作権の管理)
第5条 第三者から著作物の利⽤申請があった場合は、本学術院が、その裁量により適当と認めた者について利⽤を許諾することができる。これにより、対価が発⽣した場合は、本学術院がこれを収受し、学会誌に関する活動にのみ使⽤するものとする。
2 本学術院は、第三者による著作権侵害等の違法⾏為を防⽌するため、適切であると判断する措置を講ずることができる。
(著作物の利⽤)
第6条 著作者は、著作者⾃⾝が⾃ら論⽂の全部または⼀部を、著作権法で認められている⼀定の範囲内で利⽤する場合は、本学術院の許諾を必要としない。
2 著作者は、前項の利⽤を⾏う際には、学会誌名および当該論⽂が掲載された刊・号を明⽰しなければならない。
3 著作者は、当該論⽂を、他の学会誌ならびに学術誌等に重ねて投稿することはできない。
(著作者の責任)
第7条 学会誌に投稿された論⽂が第三者の著作権およびその他の権利を侵害した場合は、その⼀切の責任を、著作者が負うものとする。
(その他事項)
第8条 著作権に関し、本規程に規定されていない事項については、著作権法に拠るものとする。
附 則 この規程は 2009年12⽉15⽇から施⾏する。
附 則 この規程は 2025年4⽉17⽇から施⾏する。
原稿提出方法
「スポーツ科学研究」は、通年で投稿を受け付ています。
「投稿規程」にて指定された以下の日英いずれかのテンプレートを用いた原稿作成が必須となります。
投稿先
論文(WordおよびPDF)を査読システムに投稿してください。
投稿先リンク:https://iap-jp.org/wssr/journal/
※初めて投稿する際は、新規アカウントの作成が必要です。
英文翻訳・校正、論文投稿支援サービスを利用される際は、以下サイトをご確認ください。
見積り依頼時に本学に所属している方で、かつWasedaメールアドレスにて申込みをしていただくと
5-10%の割引が適用される会社があります。
〇早稲田大学研究ポータル「学術論文に係る補助制度」:
https://waseda-research-portal.jp/culture-support/academic-paper/
投稿論文に関する各種変更については決まり次第、随時掲載いたします。
各自ご確認ください。
問い合わせ
〒162-0801
東京都新宿区山吹町332-6 パブリッシングセンター(株)国際文献社内
「スポーツ科学研究」編集事務局
Email: [email protected]