- ニュース
- 【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(一)-モスクワ勃興期編』(文学学術院教授 三浦清美)
【著作紹介】『中世ロシアの聖者伝(一)-モスクワ勃興期編』(文学学術院教授 三浦清美)

- Posted
- Wed, 15 Mar 2023

松籟社、2023/1/16、469頁
モスクワ・ロシアの聖者伝-モンゴル襲来の壊滅のなかで
本書は、14世紀中葉から15世紀の第1四半世紀にかけての諸事績を描いた3つの聖者伝、『ラドネジのセルギイ伝』、『ペルミのステファン伝』、『ベロオゼロのキリル伝』を収めています。これらの聖者伝は、文学史や歴史の概説書では、しばしば名前を見かけるものですが、本格的な翻訳、紹介はなされていませんでした。これらの重要な作品群を読み理解することは、15世紀から各々が独自の道を歩むロシア、ウクライナ、ベラルーシの複雑な歴史を理解するうえで、きわめて深い意味があります。
荒野修道院創設運動とロシア国土の誕生
13世紀の第2四半世紀にモンゴルの襲来を受けたあと、かつてキエフ・ルーシと呼ばれ、やがてロシア、ウクライナ、ベラルーシとなる地域は、モンゴル・タタールの軍勢を引きこんでの諸公の内乱によってこの壊滅状態に陥りました。人々の生活の中心は馬が容易に入れない森林地帯に移りましたが、森林地帯は生産性が低く、モンゴル・タタールの重い貢税に苦しみました。そうした状況のなかで、「血を流さない殉教」として俗世と縁を切り、未開拓の森のなかに分け入り、食うや食わずの生活をしつつ自給自足の共同体を作ったのが東方正教の修道士たちでした。これは「荒野修道院創設運動」と呼ばれています。この荒野修道院創設運動によって、北東ルーシの大森林はロシアの国土となっていくのですが、荒野修道院創設運動に最初で最大の立役者が、ラドネジのセルギイにほかなりません。
〈研究内容紹介〉
『ラドネジのセルギイ伝』

熊を慣らすセルギイ
ラドネジのセルギイは、モスクワ大公国によって領地を奪われたロストフの貴族の末裔で、さきに述べた悲惨な俗世を離れ、修道士になりました。就業初期の様子を聖者伝は次のように書いています。「なんと名づけようと、何物もなかったのだ。こういうあらゆることに加えて、悪霊たちとの戦いがあった。…彼の魂は恐怖を知らず、彼の心は怖れを知らなかったし、その知もこのような悪魔の罠や無慈悲な試練や謀はかりごとに怯えはしなかった。」ほかにも、異教的霊威として畏れられた熊を手なずける話などがあり、荒野修道院創設運動の実相がわかって興味深いです。
『ペルミのステファン伝』

ペルミのステファン(ウィキメディア)
ペルミのステファンは、フィン・ウゴール系のコミ・ズィリャン人にキリスト教を宣べ伝えた人物ですが、『ペルミのステファン伝』は宣教の際の困難を生き生きと伝えています。かつてキュリロス、メトディオス兄弟がスラヴ人に布教するためにスラヴ文語を創造したように、ペルミのステファンはコミ・ズィリャン人の文字を作り、聖書をコミ・ズィリャン語に翻訳しましたが、それは、キリストの愛がすべての人間におよぶようにという博愛主義に基づいていました。この聖者伝も、荒野修道院創設運動の精神の高揚を伝えるものです。
『ベロオゼロのキリル伝』
ベロオゼロのキリルは、モスクワ大公国の貴族の出身で、権勢を帯びる地位にいましたが、俗世と離れ修道士となる夢を捨てきれずに、シーモノヴォ修道院の修道士となりました。キリルは修道士として認められるにつれて、神ではなく人に褒められる境遇に満足できず、狂人を装う瘋癲の行に勤しみ、周囲から狂人として退けられますが、それが故意であることを見抜かれてやがてシーモノヴォ修道院の修道院長になります。しかし人に褒められる修道院長職にあることに飽き足らず、北方の未開の地ベロオゼロに逃れてそこで沈黙の行に勤しみ、ベロオゼロに修道院を創建します。

リルベロゼルスキイ修道院(近景)
『ベロオゼロのキリル伝』は、そうしたキリルの生涯を描いています。
早稲田大学文学学術院教授
三浦 清美(みうら きよはる)
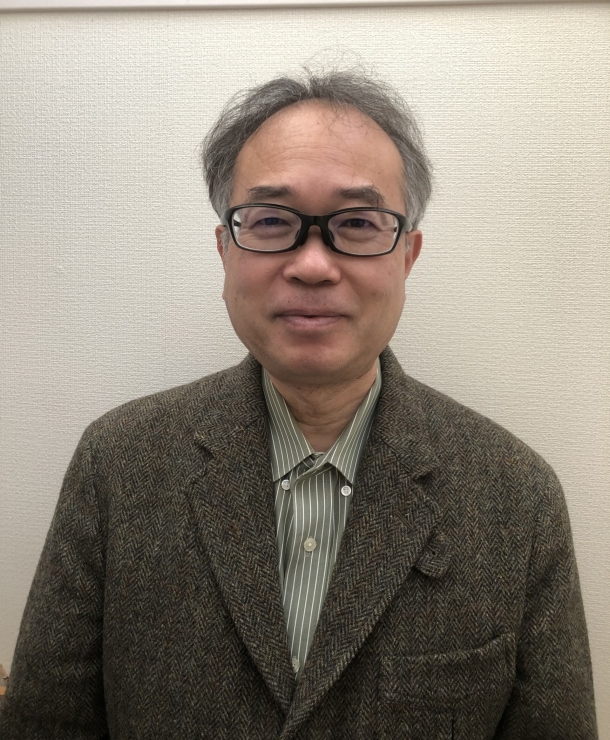
1965 年(昭和40年)、埼玉県生まれ。専攻はスラヴ文献学、中世ロシア文学、中世ロシア史。博士(文学)。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、サンクトペテルブルク国立大学研究生、電気通信大学(1995年から)を経て2019年から現職。著書に『ロシアの源流-中心なき森と草原から第三のローマへ』(講談社)、『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』、訳書に『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(松籟社)、『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(松籟社)、『中世ロシアの聖者伝-モスクワ勃興期編』(松籟社)、ペレーヴィン『眠れ』(群像社)、ストヤノフ『ヨーロッパ異端の源流-カタリ派とボゴミール派』(平凡社)、ヤーニン『白樺の手紙を送りました』(共訳、山川出版社)がある。
