- ニュース
- 部門研究「多角的アプローチ」◆第2回研究会・出版記念シンポジウム(10/11)
部門研究「多角的アプローチ」◆第2回研究会・出版記念シンポジウム(10/11)
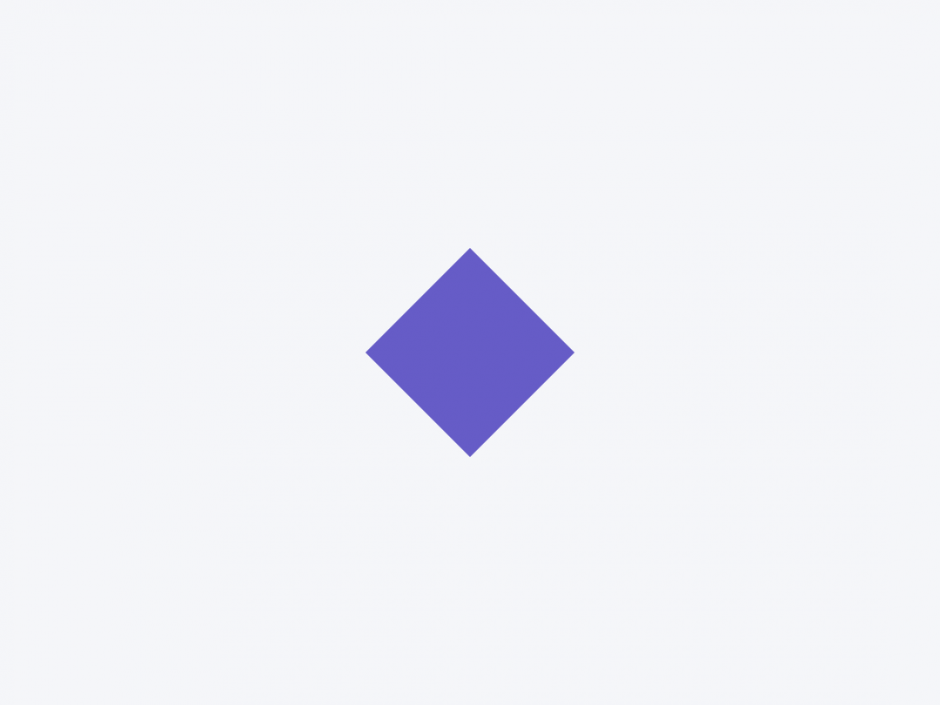
- Posted
- Tue, 30 Sep 2014
<早稲田大学総合人文科学研究センター>
「行動・社会・文化に関する多角的アプローチ」部門主催
2014年度第2回勉強会
- 日時
2014年10月11日(土)13:00-15:30 - 場所
早稲田大学文学学術院(戸山キャンパス)36号館6階 682教室
≪出版記念シンポジウム≫
「人間関係の生涯発達心理学-自己/他者/意味との出会い」
人間の心は、自己/他者/意味が発現し、それらが豊かな表象活動をとおして分化統合され続ける世界である。この人の心を、4つの発達期に出現する人間関係の視点から検討する。
司 会:大藪 泰(早稲田大学文化構想学部)
発 表
1. 大藪 泰(早稲田大学文化構想学部)「乳児が意味世界と出会うとき」
人間の生活世界は先人が生みだしてきた意味に満ちあふれている。人の一生は、その意味に気づき、意味世界に同化しつつ、そこに自分らしい意味世界を構築し続けてゆくことである。しかし、乳児は意味世界の存在を知らずに誕生する。その乳児が意味世界とどのように出会うのだろうか。人の乳児に豊かに備わる情動と認知の働きに由来する「共同注意」の視点からこの問題を論じてみたい。
2.林もも子(立教大学現代心理学部)「思春期の始まりにおける孤独の意味」
小学校高学年になると、多くの子どもは自分や家族をはじめとする身近な環境を大きな世界の一部として相対的に見る視点を獲得する。自己を他者の視点から見たとき、子どもと世界との間に深いところで裂け目ができ、子どもは世界を冷ややかにあるいは恐れをもって見わたすと同時に孤独を体験する。思春期の苦しみと成長を、孤独を否認や昇華などにより避けようとする必死の試みという視点から論じる。
3. 小塩真司(早稲田大学文化構想学部)「青年から成人へ-人間関係や自己の広がりと変化-」
青年期から成人期にかけて、それまでよりもさらに一層、人びとと社会との関わりは大きくなり、人間関係も広く展開するようになる。就職や結婚、子育てというライフコースの道筋は、一定の人間関係、自己意識、パーソナリティの変化を生み出す。同時に、その道筋は個々人によって多様なものとなり、個人差も大きくなる。ここでは、このような青年期以降の共通性と多様性について考えてみたい。
4.福川康之(早稲田大学文学部)「ライフサイクルにおける老年期の機能と適応」
「老化」は多くの生物に認められる現象であるが、ライフサイクルに「老年期」を有する生物は稀である。今回は、ヒトのライフサイクルにおける老年期の機能について、生活史理論や世代間交流の観点から考える。特に、「祖母仮説」に関する国内外の研究知見の概観を通じて、ヒトの長寿化の進化的適応の可能性を検討したい。
<協賛>丸善出版株式会社/早稲田大学心理学会
「行動・社会・文化に関する多角的アプローチ」部門代表者:日野泰志
連絡先:日野泰志([email protected])
- Tags
- イベント
