- News
- 【2022年3月8日(火)】「ライフコース論×環境社会学―エネルギー産業の転換と移動をめぐって-」開催のお知らせ
【2022年3月8日(火)】「ライフコース論×環境社会学―エネルギー産業の転換と移動をめぐって-」開催のお知らせ
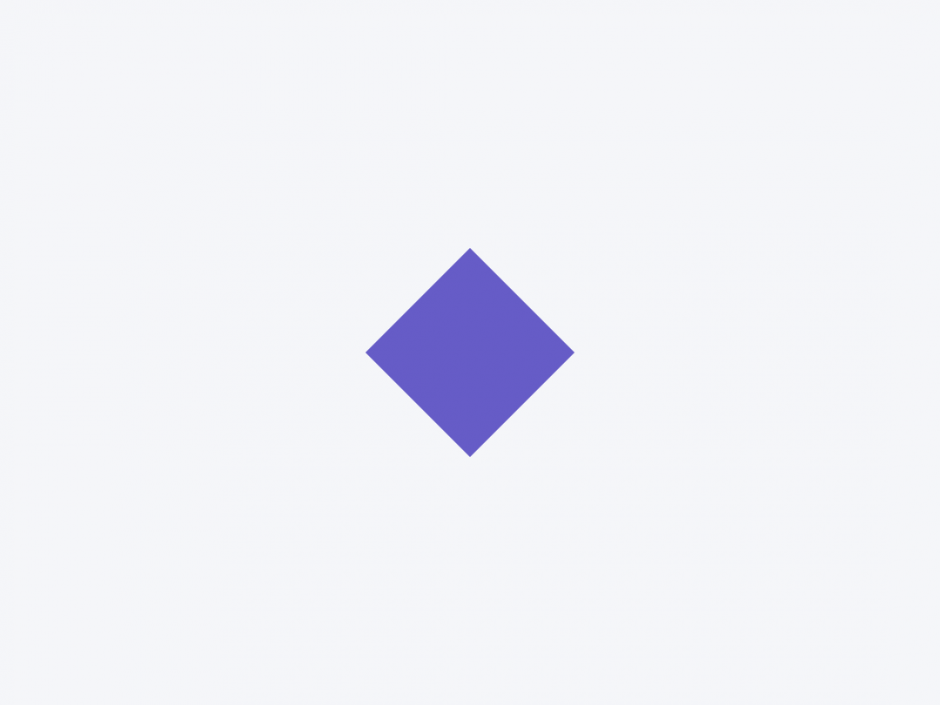
- Posted
- 2022年2月24日(木)
下記のように「ライフコース論×環境社会学―エネルギー産業の転換と移動をめぐって-」と題して研究例会を開催いたします。なお、本企画は、環境社会学会研究活動委員会/震災・原発事故特別委員会・早稲田大学総合人文科学研究センター「知の蓄積と活用にむけた方法論的研究」部門・早稲田大学大学院社会学コースとの共催です。
環境社会学会における震災研究において、避難者の「多様な被害」や避難者支援に関する調査研究が多いが、原子力災害によって地域移動を余儀なくされた避難者のその後の生活に関する調査研究はそれほど多くはない。その中で『鳥栖のつむぎ』(関礼子・廣本由香編、新泉社、2014年)は、佐賀県鳥栖市に迷いや葛藤を抱えながら移動した人々が、さまざまな人と「つながり」、支えられ、助け合って生きてきた避難とその後の生活が描かれており、環境社会学会では何度か議論に取り上げられてきた。
一方、ライフコース研究、地域社会学を専門とする産炭地研究会(JAFCOF)の研究成果の一つである『〈つながり〉の戦後史』(嶋崎尚子ほか、青弓社、2020年)では、北海道・尺別炭砿のコミュニティにおいて生まれた職場・家族・学校・地域の「つながり」が、1970年の閉山に伴って、どのように維持され、変化していったのかが示されている。また、約4000人が半強制的に移動を強いられ、日本全国各地に定着し、同郷団体を結成していった一方で、当時は子どもだった人々が抱える「故郷喪失」の思いなどが描かれた本書は、予期しない危機的状況に直面した際に、何が起こるのかという点を想像し、その対処方法を考えていくための経 験にも資する。それゆえ、炭鉱の閉山による地域移動と東日本大震災や福島第一原発事故による避難の経験と交差させることは必然であろう。
エネルギー産業(閉山、事故)による住民の地域移動/避難という現象という共通性を踏まえて、「産業と家族」というテーマを掲げる家族社会学やライフコース論から環境社会学は何を学べるか。産業転換や災害等に伴う「地域移動」による家族関係の変容や、その経験・物語を論じ方に、家族社会学と環境社会学の間で共通点や相違点があるのだろうか。イエ・ムラ論以外では、これまであまり学術的交流がなかった家族社会学やライフコース論と環境社会学の接点を、2つの書籍から考えてみたい。
【日時】2022年3月8日 13:00-16:00
【開催方法】オンライン
【登壇者(タイトルは仮)】
報告
1『つながりの戦後史』を読む ー環境社会学からの応答ー:廣本由香(福島大学)
2『鳥栖のつむぎ』を読む ーライフコース論からの応答ー:笠原良太(早稲田大学)
総合討議
コメント1 嶋崎尚子(早稲田大学)
コメント2 大倉季久(立教大学)
司会:西城戸誠(早稲田大学)
【参加方法】
下記に登録をお願いします。開催前日までにzoomのURLの情報をお知らせします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHkGtNE0xLaKYg5YwkpkTlrFb2Nz6H63phzP8Gpcxy5JsDeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
【問合せ先】研究活動委員・西城戸誠(早稲田大学)
nishikido[at]waseda.jp
↑[at]を@に変えて送信してください
