- News
- サムライ・イメージの光と影 ―国際日本学の観点から―(2018年10月3日)開催のお知らせ
サムライ・イメージの光と影 ―国際日本学の観点から―(2018年10月3日)開催のお知らせ
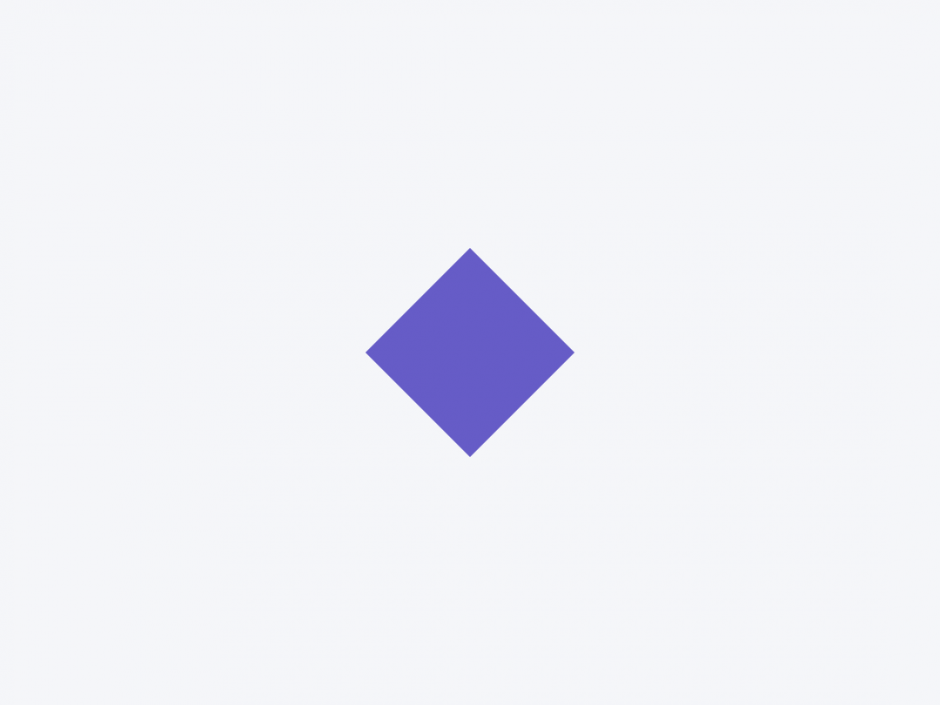
- Posted
- 2018年8月28日(火)
ワークショップと国際シンポジウム
サムライ・イメージの光と影
―国際日本学の観点から―
主 催:私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・第2グループ
「ポストコロニアル時代の人文学、その再構築―21世紀の展開に向けて」
共 催:早稲田大学高等研究所
早稲田大学文学部 フランス語・フランス文学コース
早稲田大学文化構想学部 文芸・ジャーナリズム論系
日 程:2018年10月3日(水)
場 所:早稲田大学戸山キャンパス33号館16階第10会議室
共通言語:日本語
事前予約不要、参加無料
~ワークショップ「1900年代~1940年代のサムライ・イメージ」~
10:00~10:10 開会の挨拶、趣旨説明(早稲田大学:谷口眞子)
10:10~10:40 「1905年~1940年代の新聞に表象されたサムライ・イメージ」
(早稲田大学:オディール・デュスッド)
10:40~11:10 「1930年代の武士道とサムライ・イメージ-「葉隠」を中心に-」
(早稲田大学:谷口眞子)
11:10~11:20 休憩
11:20~11:50 「ナチ時代の”サムライ精神”」
(早稲田大学:松永美穂)
11:50~12:30 ディスカッション(日本語)
(谷口眞子/オディール・デュスッド/松永美穂/フランソワ・ラショウ/
李衣雲/アレクサンドル・ニコラエヴィチ・メシチェリャコフ)
12:30~12:35 閉会の挨拶
~国際シンポジウム「20世紀のサムライ・イメージ」~
14:00~14:15 開会の挨拶、趣旨説明(早稲田大学:谷口眞子)
14:15~14:45 「ドイツ語圏の日本旅行記にみる「日本人」言説の変遷と受容」
(立教大学助教:馬場浩平)
14:45~15:15 「ダーク・サムライの系譜―浮世絵からハリウッドまで―」
(フランス極東学院教授:フランソワ・ラショウ)
15:15~15:45 「反日、親日、あるいは哈日――台湾における「日本」イメージの変化」
(台湾国立政治大学台湾史研究所准教授:李衣雲)
15:45~16:00 休憩
16:00~16:30 「ロシア・ソ連における日本のイメージ:女性の国からサムライの国へ
(19世紀末から1930年代まで)」
(ロシア国立人文大学および高等経済学校教授:
アレクサンドル・ニコラエヴィチ・メシチェリャコフ)
16:30~18:00 パネルディスカッション(司会:谷口眞子)
(馬場浩平/フランソワ・ラショウ/李衣雲/
アレクサンドル・ニコラエヴィチ・メシチェリャコフ/オディール・デュスッド/松永美穂)
18:00~18:05 閉会の挨拶
開会趣旨
21世紀に入り、人文学の各分野で専門分化が激しくなるとともに、膨大な量の情報がインターネット上に流れ、これまでの人文学のあり方は岐路に立たされています。しかしディシプリンが破綻し始める一方、学際的あるいは学融合的動きがみられることも確かです。
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業・第2グループ「ポストコロニアル時代の人文学、その再構築―21世紀の展開に向けて」では、以上のような共通認識のもと、「歴史」となった20世紀を国際日本学の観点から見直したいと考えました。サムライ・イメージをキーワードとし、表象・メディア論の手法も用いながら、外国の日本人観やその形成過程の一端を、政治的文化的歴史の流れの中で探ることを目的としています。
19世紀中葉の開国以降、日本にはお雇い外国人や駐留軍人が滞在し、日本からは使節派遣団や留学生などが国外に飛び立ちました。人の移動とともに、ヨーロッパの軍事・法制・教育などをめぐる学問も流入し、幕藩体制下で培われた学知と融合しながら、日本では近代国民国家が形成されていきます。不思議なことに、武士の存在が否定された明治時代以降、武士道が喧伝されるようになり、武士(サムライ)のイメージは、日本とさまざまな関わりを持つ諸外国に、それぞれの文化背景を反映した形で伝達され、受容され、改変されていきました。
午前中のワークショップでは、1900年代から1940年代に時間軸を設定し、同時代のフランス・ドイツ・日本で、どのようなサムライ・イメージが形成され、サムライ精神や武士道が喧伝されていたのか、比較します。ヨーロッパにおけるフランスとドイツの歴史、両国と日本との政治的関係が、サムライ・イメージの違いに反映されていることがわかります。
午後の国際シンポジウムでは、ドイツ・フランス・台湾・ロシアの4ヶ国の比較を行います。ケンペルは17世紀末に日本に滞在し、その著『日本誌』は、ヨーロッパ人が日本に興味を持つきっかけの一つとなりました。明治維新前年に開催されたパリ万国博覧会には、日本からも出品しており、浮世絵はジャポニズムを呼び起こすことになります。台湾は日本による植民地時代を、またロシアは日露戦争における敗北を経験し、20世紀における日本との軍事的関係は、ドイツ・フランスとは異なります。それぞれの地域での政治的文化的状況が、サムライ・イメージの形成にどのように反映されているのか、比較史的視座を通じてみえてくるでしょう。
近年のグローバリズムの流行にともない、国際日本学関係のシンポジウムは英語で開催されることが多いですが、次代を担う若い学生や他の専門領域の研究者にも興味をもってもらうために、共通言語を日本語にしました。自由で活発な議論が行えると期待しています。
事前予約不要、参加無料ですので、多くの方々のご参加をお待ちしております。
※当日はレセプションの開催を予定しております。
(レセプションの会場等、詳細についてはシンポジウム後にご案内いたします)
