- ニュース
- 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業キックオフシンポジウム「新しい人文学の地平を求めて―ヨーロッパの学知と東アジアの人文学―」の開催報告を掲載しました。(12/6開催)
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業キックオフシンポジウム「新しい人文学の地平を求めて―ヨーロッパの学知と東アジアの人文学―」の開催報告を掲載しました。(12/6開催)
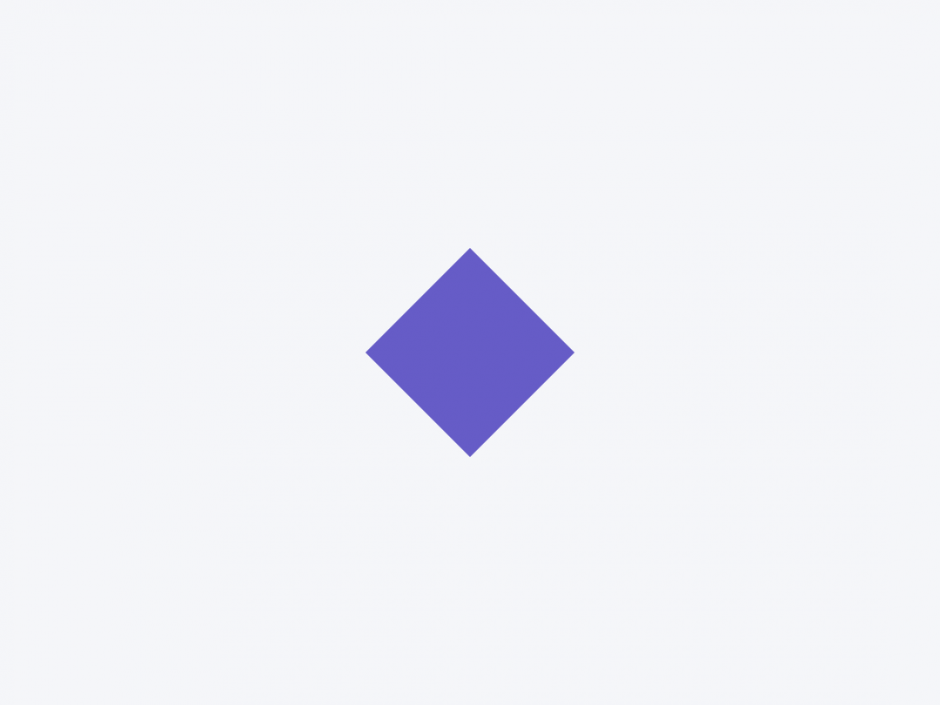
- Posted
- 2015年1月15日(木)
2014年12月6日小野記念講堂において、平成26年度に採択された文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業のキックオフ・シンポジウム『新しい人文学の地平を求めて―ヨーロッパの学知と東アジアの人文学』が行われた。全体の研究プロジェクト名は「近代日本の人文学と東アジア文化圏-東アジアにおける人文学の危機と再生」で、研究代表者は李成市・文学学術院教授、主体となる研究組織は総合人文科学研究センターである。事業期間は平成26年度~30年度。
研究テーマは次の3つに分かれている。
- 近代日本と東アジアに成立した人文学の検証〈代表者・甚野尚志教授〉
- ポストコロニアル時代の人文学、その再構築-21世紀の展開に向けて〈代表者・千野拓政教授〉
- 早稲田大学と東アジア-人文学の再生に向かって-〈代表者・新川登喜男教授〉
シンポジウム推進委員は、学内27名、学外12名(うち外国研究者9名)より構成されており、上記テーマに沿って3つのグループから成る。今回のシンポジウムでは、スタートにふさわしく(1)のグループを中心に報告者が構成され、ヨーロッパの学知をいかに日本と東アジアが受容したかを明らかにし、そこから人文学の今後を見通そうというものであった。
14時に開始し、李成市教授が開会の辞を述べたあと、甚野尚志教授が趣旨説明を行った。その後のプログラムは以下の通りである。
- 報告1 安酸敏眞(北海学園大学教授)
「現在(いま)、あらためて《人文学》を問う」 - 報告2 逸見龍生(新潟大学准教授)
「哲学者(フィロゾーフ)と人文主義者(ユマニスト)
-フランス18世紀『百科全書』における〈ヒストリア〉の概念」 - 報告3 武藤秀太郎(新潟大学准教授)
「日中両国における人文学の概念形成
-「整理国故」と「封建」を中心に」 - コメント1 河野貴美子(早稲田大学教授)
- コメント2 根占献一(学習院女子大学教授)
- 質疑応答
なお、18時30分から大隈会館楠亭において情報交換会を行った。なお、この日出席できない委員からの「コメント・質問」集プリントが配布され、質疑応答において活発な議論が交わされた。特に貝澤哉氏の紙上コメントに対して安酸氏から懇切な回答があって大いに盛り上がり、キックオフにふさわしいシンポジウムとなった。出席者は75名、情報交換会には41名が参加した。
- Tags
- イベント


