- News
- 【開催報告】ゼバスティアン・バルメス氏(チューリッヒ大学)講演会
【開催報告】ゼバスティアン・バルメス氏(チューリッヒ大学)講演会

Dates
カレンダーに追加0724
WED 2024- Place
- 早稲田大学戸山キャンパス33号館第1会議室
- Time
- 16:00-17:30
- Posted
- Mon, 05 Aug 2024
ゼバスティアン・バルメス氏(チューリッヒ大学)は、日本古典文学研究でめざましい活躍を重ねている気鋭の研究者であり、平安から鎌倉時代の文学に関する手堅い文献研究にもとづきながら、ヨーロッパにおける近年のナラトロジーの展開までおさえつつ、日本古典文学研究のあらたな方法を開拓しようとされている。今回は、ヨーロッパ発のナラトロジーの方法によって具体的な研究成果を導くというよりも、日本古典文学の特性に留意しつつナラトロジーを適用した場合に『神道集』の研究がどのような形式をとりうるのか、ということを示そうとする意欲的な講演であった。
まずは、ナラトロジーという学問の起こりから最近までの展開を確認するとともに、日本の物語文学研究におけるナラトロジー援用のあり方が批判的に検証された。その上でバルメス氏は、ジェラール・ジュネットなどのナラトロジーを更新する必要性を強調する。そして、本地垂迹思想によりつつ十四世紀半ばにまとめられた『神道集』の「物語的縁起」を対象として、〈視点〉〈語り手〉〈距離〉といった、ナラトロジーの根本的な概念の見直しを図る。具体的にいうと、〈語り手〉とはそもそも〈視点〉のレヴェルであること、またジュネットの〈距離〉の定義の改訂が必要であることなどを提唱されたのち、『神道集』のテクストに対する具体的な解析がなされることとなった。
こうした講演のあと、日本中世の説話、御伽草子、絵巻等の研究者としてきわめて著名な徳田和夫氏からのコメントがあった。徳田氏は、1970年代から今日にいたるまでの日本における研究のあり方を振り返り、その限界について、またナラトロジーと説話・絵巻などの研究との親和性などについて、幅広い視角から意見を示された。さらに、バルメス氏と徳田氏とのやりとりののち、物語文学研究、日本中世絵画史研究、そして『神道集』研究等々の立場から、活発な質疑がなされた。 本講演によって、日本古典文学研究において最新のナラトロジーをも共有してゆくべきであること、またこれまでのナラトロジーで示されてきた概念の更新の必要性が知らされた。あわせて、『神道集』における注目すべき叙述と向きあうことの愉悦が参加者の間で共有されることとなった。
(陣野英則 記)
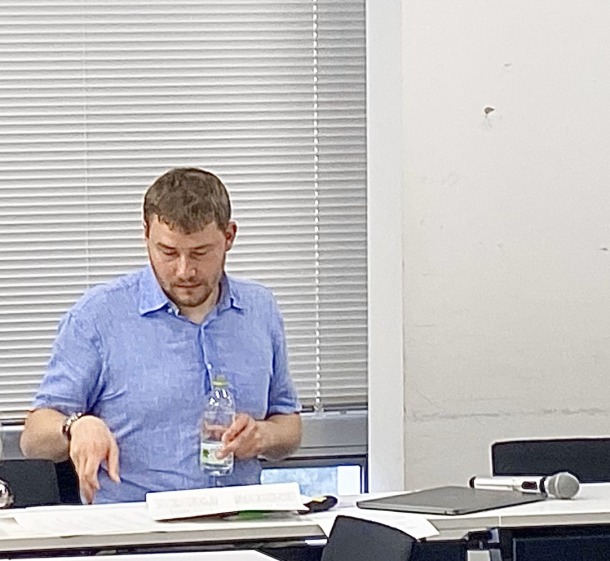
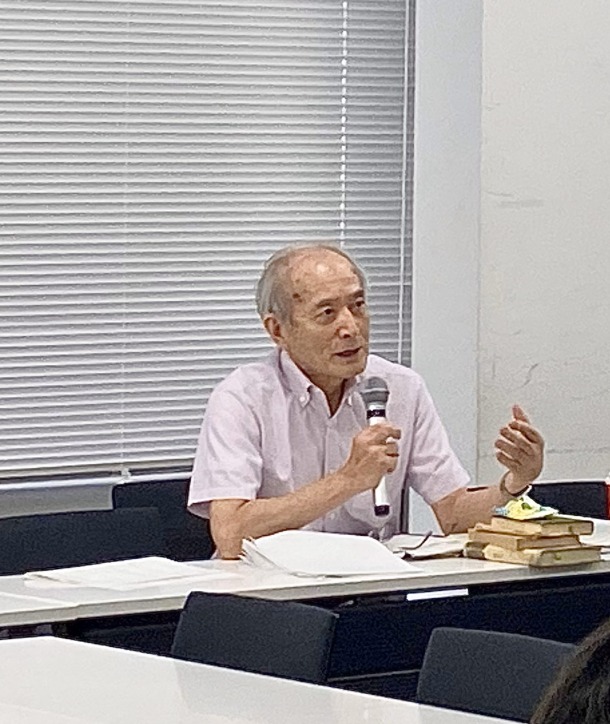

開催詳細
- 講 演 者:ゼバスティアン・バルメス〈Sebastian Balmes〉 (チューリッヒ大学 Senior Research Fellow and Lecturer)
- 講演題目: ナラトロジーと日本中世文学 ――物語論の諸問題と『神道集』の「物語的縁起」を中心に――
- コメント:徳田和夫(学習院女子大学名誉教授)
- 閉会挨拶:河野貴美子(角田柳作記念国際日本学研究所所長、早稲田大学教授)
- 司 会:陣野英則(早稲田大学教授)
- 参加人数:41名 (学内者24名、学外者17名)
- 主 催:早稲田大学総合人文科学研究センター 角田柳作記念国際日本学研究所
