- ニュース
- 【著作紹介】『「おとなの女」の自己教育思想―国立市公民館女性問題学習・保育室活動を中心に』(文学学術院教授 村田晶子)
【著作紹介】『「おとなの女」の自己教育思想―国立市公民館女性問題学習・保育室活動を中心に』(文学学術院教授 村田晶子)
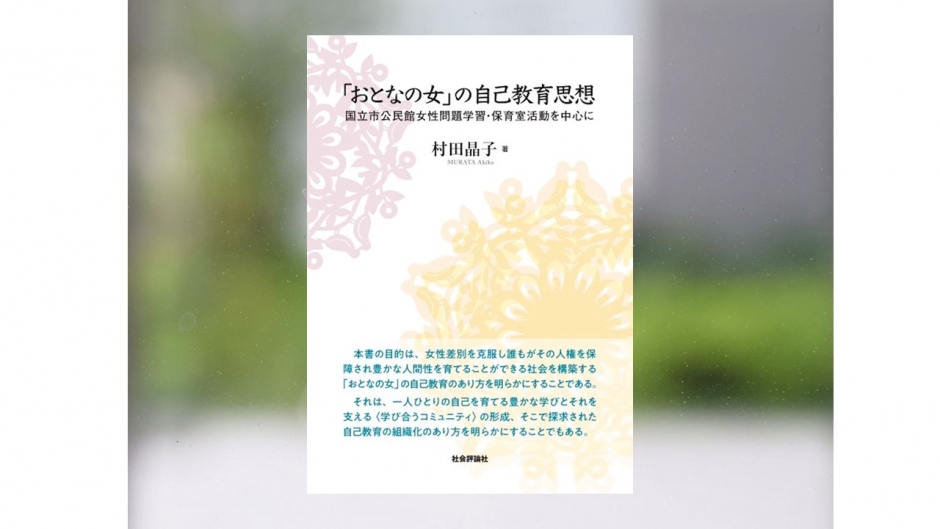
- Posted
- Tue, 18 Jul 2023
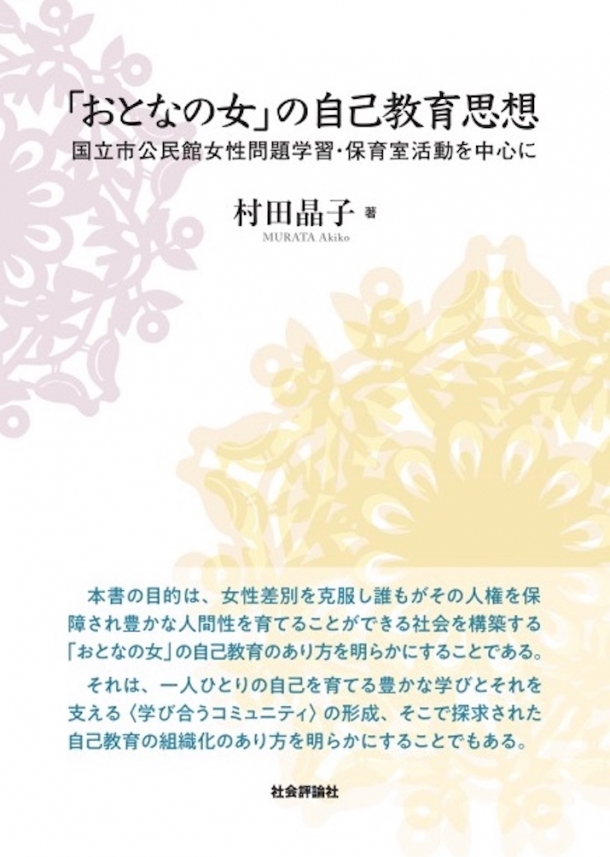
社会評論社、初版 刊行日2021/7/30 判型 A5判 ページ数 527ページ ISBNコードISBN978-4-7845-1152-5
東京の郊外の国立市(くにたちし)公民館において1965年に、日本で初めて託児を伴って性差別を克服する主体の形成に取り組む講座が開設された。以来50年以上継続する学習活動の軌跡を、一次資料をもとに跡づけるとともに、そこで女性たちが生み出した学習の思想を自己教育思想と名づけてとらえようとしたのが本書である。
この学習活動の記録や学習論である『主婦とおんな』(未來社、1973)、『子どもからの自立』(伊藤雅子、未來社、1975)は戦後女性解放の思想史の中で、高い評価を得ているが、そこで描かれている学習論はそれほど着目されずに来てしまった。どのような学習によって、性差別の克服の主体が育つのか、性差別構造の中で育ち差別を内面化している当時者自らが内面に巣食う差別と対峙し、社会を変えていく主体として育つことができるのか。そのときの学習コミュニティはどのようなものであったのか。本書において、市民の膨大な学習記録、そこで描かれた実践と省察を通して明らかにした。
また、このような学習を成り立たせる担当職員の伊藤雅子の働きについても、伊藤自らが著した多くの論考には学習観や女性観、母子関係観が表現されてきたものの、学習論、組織学習をコーディネートする成人学習の職員論としてほとんど明らかにされてこなかったと言わざるをえない。
こうした状況に対して、公民館の呼びかけに始まる学習活動が、それに高い質で呼応する市民の学習実践の展開の中で「おとなの女」の自己教育思想を生みだした。その軌跡をここで読み取っていただきたい。
〈研究内容紹介〉
私は、1980年代半ばに国立市公民館における女性問題学習・保育室活動の学習に出会って以来、性差別と教育の関係を理論的にも実践的にもこの実践研究を通して明らかにしたいと考えてきました。この実践を通して市民による膨大な学習記録が作成されています。それを繰り返し繰り返し読み、市民の学習の中に居させてもらうなかで、性差別を克服する学習のあり方を、実感を伴って学び取ることができたと考えています。
教育は人格の完成を目指しています。が、性差別は人格形成を歪ませ、ありたい自分を成長させることを阻害します。しかし、この実践は「学習」を通して、人間性を取り戻すことができることを証明していると思います。そこでの「学習」とは、学習コミュニティの質的展開の中で営まれ、日本の社会教育が培ってきた共同学習に人権の視点、性差別克服の視点で取り組むことであると言えます。
早稲田大学文学学術院教授
村田 晶子(むらた あきこ)
早稲田大学文学学術院教授。博士(文学)。専門は、社会教育学、教育とジェンダー。性差別と教育・学習の関係について研究。成人女性・育児期の女性の教育・学習実践研究。社会教育職員・対人援助専門職の養成と研修。著書に『女性問題学習の研究』(未來社、2006)。『なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか : 日本と海外の比較から考える』(村田晶子,弓削尚子編、青弓社、2017)。『ジェンダー研究/教育の深化のために : 早稲田からの発信』(小林富久子,村田晶子,弓削尚子編、彩流社、2016)、『復興に女性たちの声を-「3・11」とジェンダー』(編著、早稲田大学出版部、2012)、『ジェンダーのとびらを開こう 自分らしく生きるために』(村田晶子・森脇健介・矢内琴江・弓削尚子、大和書房、2022)
(2023年6月作成)
