- ニュース
- 【著作紹介】『マンガメディア文化論 ―フレームを越えて生きる方法―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)
【著作紹介】『マンガメディア文化論 ―フレームを越えて生きる方法―』(文学学術院教授 鈴木雅雄)
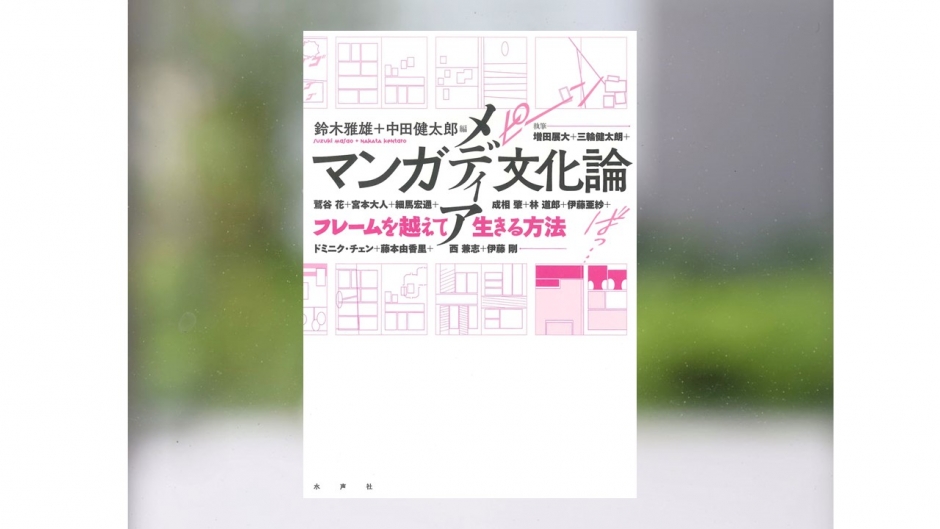
- Posted
- Thu, 22 Jun 2023
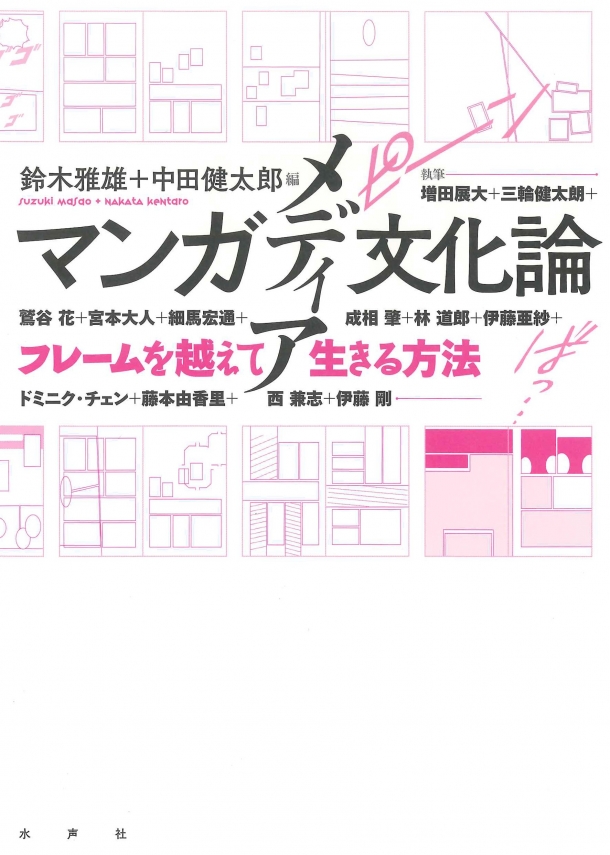
水声社 初版刊行日 2022/4/20 ページ数 480ページ ISBNコード ISBN978-4-8010-0619-5
この10年ほど、早稲田大学戸山キャンパスでマンガに関する連続ワークショップを開催し、それをもとに論文集を作るという作業を、中田健太郎さん(静岡文化芸術大学)と二人で続けてきました。これはその3冊目にあたり、シリーズの完結編となるものです。マンガ研究と視覚芸術研究をクロスさせることを目的とした1冊目、多くのマンガ研究者の協力を得ながら、マンガ表現の原理に関する研究の最前線を紹介しようとした2冊目に続き、今回は表象文化論やメディア論の多様な研究者 も招き、さまざまなメディアとの対比のなかでマンガとは何かを浮かび上がらせようとしています。
きわめて多岐にわたる論文集ですから、一つのテーマで全体を括ることはできませんが、作品そのものというよりも、マンガを読むことが読み手に与える体験とはいかなるものであるかが、歴史的かつ理論的に語られていることは間違いありません。その結果、急速に日常的なものとなった、Web上でマンガを読むという体験に焦点を合わせた論考が複数含まれることにもなりました。マンガではキャラクターがコマというフレームを踏み越えるような事態が頻繁に生じますが、そこには描かれた図像がフレームを越えて機能し、ときには作品というフレームをも越えて私たちの時空間に干渉してくるような、奇妙にも現実的なファンタスムの生まれる余地があるのではないでしょうか。そのようなキャラクターと私たちの関係を思考しようとする意図が、この論集のサブタイトルには込められています。
マンガのページをめくるのをやめられなくなるとき、私たちのなかで何が起きているのか、それを考えるためのヒントや道具をここから見つけ出してほしいと思います。
〈研究内容紹介〉
私自身はフランス文学コースの教員で、シュルレアリスム研究が専門です。たしかに仏文は何でも好きなことができる環境ですが、それにしてもずいぶん専門とかけ離れた本を作るものだと思われるかもしれません。しかしこの10年ほど続けてきた仕事は、私なりに必然性のあるものでした。
シュルレアリスム美術を考えるうえで、近代におけるイメージの運命とはどのようなものだったかという問いを避けることはできません。19世紀以降、表象のシステムが機能不全に陥っていくのに対し、いわゆる大衆的視覚メディア(マンガ、ポスター、絵本など)はファイン・アートとは異なる態度決定をしたのであり、とりわけマンガにおけるフレームとキャラクターの関係にそれが表現されていると、私は考えています。そしてシュルレアリスムは、モダン・アートよりもむしろ大衆的視覚メディアに近い実験だったように思えるのです(ここで議論を展開することはできませんが)。
ともかく私にとって、いつしかマンガを思考することとシュルレアリスムを捉えることは、一つの作業の二つの側面のようなものとなりました。歴史研究と理論研究の両面において、この直感をどのように理解してもらえる形に整理していくか、それが目下の最大の課題といったところです。
早稲田大学文学学術院教授
鈴木 雅雄(すずき まさお)
1962年、東京生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。パリ第7大学博士課程修了(文学博士)。早稲田大学文学学術院教授。シュルレアリスム研究。
著書に、『シュルレアリスム、あるいは痙攣する複数性』(平凡社、2007年)、『ゲラシム・ルカ――ノン=オイディプスの戦略』(水声社、2009年)、『ジゼル・プラシノス――ファム=アンファンの逆説』(水声社、2018年)、『火星人にさよなら』(水声社、2022年)など。訳書に、サルバドール・ダリ『ミレー《晩鐘》の悲劇的神話』(人文書院、2003年)、バンジャマン・ペレ『サンジェルマン大通り一二五番地で』(風濤社、2013年)、ジョルジュ・セバッグ『崇高点』(水声社、2016年)など。編著に、『文化解体の想像力』(共編著、人文書院、2000年)、Faits divers surréalistes (Jean-Michel Place, 2013),『マンガを「見る」という体験』(水声社、2014年)、『声と文学』(共編著、平凡社、2017年)、『マンガ視覚文化論』(共編著、水声社、2017年)、『マンガメディア文化論』(共編著、水声社、2022年)など。
(2023年6月作成)
