活発な交流が生み出す
創造的な学びの場をデザイン
オンライン授業やeラーニングなど、めまぐるしく進化を遂げている学習環境。ICTツールやAIの活用も注目されている中、キャンパスが果たす役割とは、どういったものなのでしょうか。人間科学学術院の尾澤重知教授にお話を聞きました。
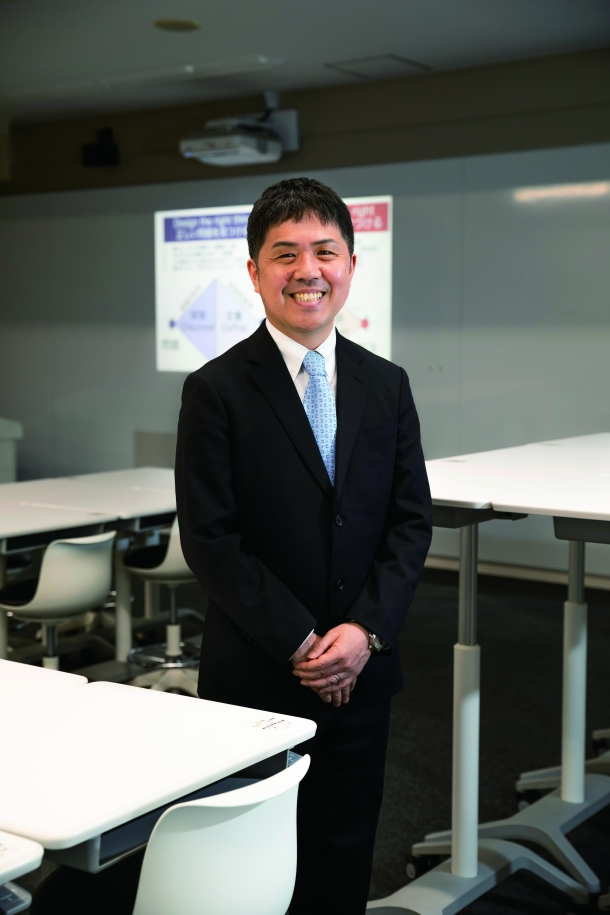
多面的なアプローチでより良い学びの環境を追求
情報・認知科学やICTを活用し、より効果的な教育を目指す教育工学という分野で、人の学びの支援について研究しています。創造性、主体性を育む学びを実現するためには、学習環境のデザインが不可欠と考え、その整備に取り組んできました。ICTツールの活用やそれを使用する教職員のサポートが代表的ですが、言葉では表しにくい雰囲気や「場」のデザインも重要だと考えています。教育機関や企業の優れた指導者に話を聞き、その実践を言語化して、異なる場で活用できるように汎用性を高める取り組みも研究の一部です。
支援というのは積極的なアプローチだけではありません。近年力を入れているのが、学びの妨げとなる認知バイアスを取り除くという考え方です。例えば日本は海外と比べて「文系」「理系」の壁が厚く、さまざまな学問領域を横断的に学ぶ「学際的思考」の育成が遅れています。学生が自分は「文系/理系」だからと未知の領域に挑戦しようとしないことは、広い意味での認知バイアスといえるでしょう。このような認知の偏りを是正する手法の開発が、現在の主な研究課題です。
キャンパスでの積極的な交流が探究的な学習を促進する
私が行う講義では、アクティブラーニングや「探究的な学習」を重視しています。講義の最大の目標は、問いを立てる力を身につけること。これはAIにはできない、人間ならではの活動です。「なぜ空は青いの?」といった素朴な問いも重要ですが、自身の体験に即した、「探究せずにはいられない」主体的な問いを立てられるようになることを目標にしています。
日本の初等・中等教育では、授業中に誰も手を挙げない、教科書で決められた範囲外の質問をしづらいといった、探究を深めにくい雰囲気があり、課題とされています。学習指導要領の改訂などによって改善されつつありますが、大学入学時点では、学生によって授業内での質問や発言への積極性、クリティカルシンキングのスキルにばらつきがあるのが現状です。
そのため、講義内では、段階的にアカデミックな問いを立てる練習を行います。隣の席の学生へ相互にインタビューするなど、簡単なところから問題意識を持って周りのものを観察する訓練を重ねていくのです。特に早稲田大学には多様なバックボーンを持つ学生が集まっているので、議論を通して、ものの見方や考え方の違いに気づきやすく、発見が次の探究の原動力になります。これはキャンパスという、人が集まる場があるからかなうことですし、さらに活発な交流が生まれる場のデザインを追求していきたいと考えています。
その一環で、「CTLT Classroom」と呼ばれるアクティブラーニング用の教室の整備にも関わりました。ICTを活用し、各自のPCのデータをスクリーンに投影できるようにしたり、高さが変えられる机や椅子を設けて自由に動きやすくしたりして、「対話型、問題発見・解決型授業」を推進する教室になっています。使用した教職員からは「学生たちの議論が想像以上に盛り上がって驚いた」と好意的な声をいただきました。
主体的な学びを身につければ将来の可能性がどんどん広がっていく
教育は、個別最適化が重要で、一人ひとりサポートすべき内容が異なります。多くの学生が集まる場で全員に向き合うのはとても難しいですが、学習環境を整えていけば学生同士で自然と学び合ってくれますし、ICTツールも最大限に活用してフォローしています。
サークルやアルバイトなどの課外活動にも、もちろん学びがあるでしょう。ただ、誰かが決めた枠組みの中での活動にとどまる限り、創造性は発揮しにくいものです。一方、一度自分で問いを立てられるようになれば、世界は際限なく、自由に広がっていくことを実感できるはず。学生の皆さんが「自分はこんなものだ」と決めつけて将来への可能性を狭めてしまわないよう、未来に開かれた学びを深められるような環境を構築して、より創造的な学習を支援していきたいです。
PROFILE
尾澤重知(人間科学学術院教授)
1999年慶應義塾大学環境情報学部卒業。2004年北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博士(知識科学)後期課程修了。大分大学高等教育開発センター講師、同准教授等を経て、2010年早稲田大学人間科学学術院准教授、2021年4月より現職。学部における組織的な教育・学修支援、とりわけアカデミックスキルやデータリテラシーの育成、自己点検・評価に関わる活動に参画。
(CAMPUS NOW No.251 2024/04より転載)







