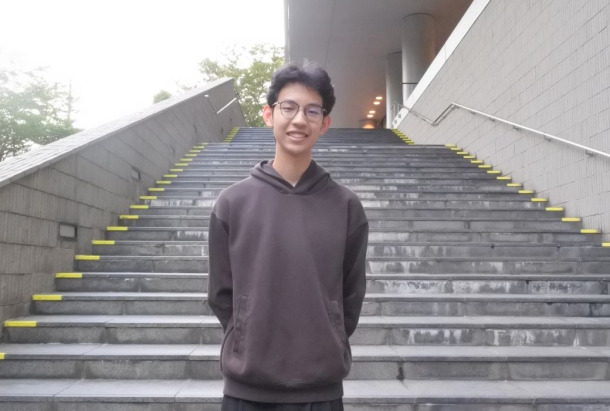
早稲田キャンパス 14号館横階段にて
早稲田から世界へ、世界から早稲田へ。留学を通じて感じたことや、学んだこと、文化の違いで気付いたことなどをリポートする「スタディー・アブロード」。今回は、インドネシアから早稲田へ留学しているダレンさんの体験を紹介します。
個性を大切にすることを学び、人それぞれに深い物語があることを知った
社会科学部 3年 ダレン クスノヲ
私はインドネシア人ですが、生まれてから6歳までは米国で、その後11歳までは中国に住んでいました。高校はインドネシアで卒業し、早稲田大学の英語学位プログラムを知り、国際的な環境で日本語などの新しい言語を学べる最高の場所だと思い、入学を決めました。
早稲田へ来てからは、出会った人たちに感謝しています。多様な文化背景を持つクラスメートや友達から、さまざまなことを日々学んでいます。最初の頃は、学業で成績優秀な人、働くことや結婚についてしっかりとした考えを持っている人など、他人と自分を比べてしまい、自信を失うこともありました。でも、いろいろな人に囲まれるうちに、個性を大切にすることを学んだのです。日本は集団主義のイメージがありますが、よく見ると個人の違いがたくさんあると気付きました。
早稲田で特に好きだった授業は、「都市再生論」です(残念ながら、今は開講されていません)。授業ではフィールドワークで東京の街を歩き、建物がどう設計されているか、なぜこのような用途で使用しているのかを分析します。例えば、2023年に開業した虎ノ門ヒルズを見学して、周辺の経済や階級構造にどんな影響があるのかを議論しました。この経験から、街の建築物と同じように人それぞれにも深い物語があると知りました。これは、この2年間で私が学んだ大切なことの一つです。

2023年、「都市再生論」の授業で日本橋のコレド室町を訪れた時の一枚。筆者は上段右端
日本での思い出はいろいろありますが、初めて訪れた横浜は印象的でした。ずっと訪れてみたいと思っていたのになかなか行く機会に恵まれず、実際に足を運ぶまで実に8カ月近くもかかってしまいました。2024年4月の晴れた日に、大学の友達と山下公園で過ごしたのですが、特に何か特別なことがあったわけではないのに、その時間は平和で心が満たされた思い出になりました。将来どんな進路を選ぶかはまだ分からないですが、大切な人たちと一緒ならどこでも幸せになれると思ったのです。

2024年12月、山下公園を再度訪れました
今まで慣れ親しんだ故郷から何千キロも離れてこのような時間を過ごしたことで、幸せは自分の中にあると気付けました。他人と自分を比べるのをやめてから、日本で過ごす日々は人生で一番充実しています。
~日本に来て驚いたこと~
実は、来日前に日本には何度か来たことがあったので、東京の生活にはすぐ慣れました。でも、一番驚いたのは、大学の友人のおばあさんが住んでいる長崎県の小さな町・島原市を、友人と一緒に訪れた時のことです。日本の田舎に行く機会はあまりなく、まして田舎に数泊するのは初めての経験です。東京は忙しい雰囲気で物事のスピードも速いですが、田舎の人たちのゆったりとした親切さやもてなしには驚きました。
島原市の「スターバックス」に立ち寄った時、東京に比べてすいていたせいか、注文していると店員さんが冗談を言ったり世間話をしてくれたりしました。日本は「静かで人間関係が冷たい」と思われがちですが、そんなことは全くありません。もちろん言葉を覚えるのには時間がかかりますが、話せるようになると出会いの幅がぐっと広がります。
島原市を訪れた時の写真。誰もいない海沿いの駅で(左)。置いてあるバスの運転席に乗ってみました(右)
他に学外で訪れたのは、東京にあるチェスクラブです。チェスを通じて日本人や留学生が仲良くなれるところで、知り合った人と何度か食事にも行きました。正直とても驚いたのは、東京にも新しい友達を作ろうとする人が意外とたくさんいたことです。もしかしたら、これが私の「大人としての初めての経験」なのかもしれません(笑)。大学やサークル以外で積極的に人と関わることは今までなかったので、文化の違いを感じるより、日本の人たちがとてもフレンドリーで開放的なことに感動しました。














