「 “空間”を通じて、全ての個人にふさわしい場所を届けたい」
創造理工学研究科 博士後期課程 3年 田中 大貴(たなか・ひろき)
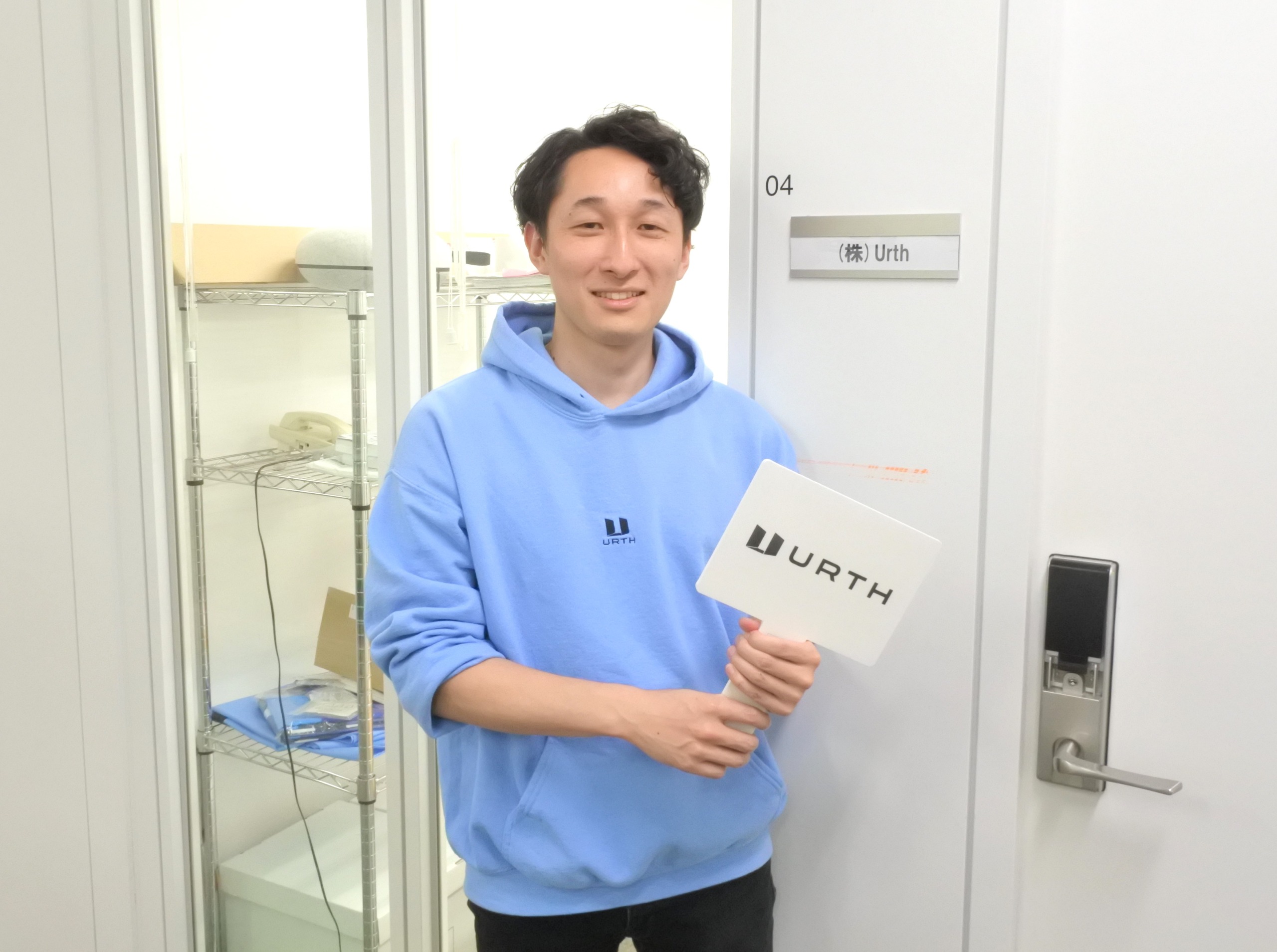
アントレプレナーシップセンター(早稲田キャンパス 19-3号館)株式会社Urthオフィス前にて
博士課程で建築の研究を続ける傍ら、仲間と立ち上げた株式会社Urthで代表取締役CEOを務める田中大貴さん。建築とITを融合させながら、これまでにない空間の形を探求し、メタバース上での建築に挑戦しています。早稲田大学アントレプレナーシップセンターの起業支援制度を活用し、2024年にはシード資金(※)として6,000万円を調達。今やスタートアップの代表取締役として注目を集める存在の田中さんに、起業に至るまでの経緯や原動力、そして早大生へのメッセージを聞きました。
※企業が創業初期に、ビジネスの立ち上げや検証のために支援者や投資家などから調達する資金。
――株式会社「Urth」と、事業内容について教えてください。
私たち「Urth」は、「全ての個人が輝く社会を作る」ことをミッションに掲げています。人にはそれぞれの個性があり、それがちゃんと表現・認知され、「君が輝く場所はここなんじゃないか!」と社会の中で最適に配置されれば、良い社会ができると信じています。そのために、文字や動画では伝え切れないことを、空間を使って表現するお手伝いをしています。
具体的には、建築士が持つ「空間を表現する力」をVRなどの3D空間に生かし、企業の課題を解決する法人向けサービスを展開しています。現実では、一人の建築士が一生で設計できる建物の数は10〜20件ほどですが、国内には約35万人の建築士がいるんです。その力を3D空間でうまく掛け合わせれば、社会に届けられる空間体験の数は何十倍、何百倍にも広げられると考えています。
例えば、採用における企業説明の場面で、工場など「本当は見せたいけれど、機密情報があるから現場を映像で公開できない」という場所も、建築士による3Dモデルで再現すれば、メタバース上で安全かつリアルに体験できます。応募者は実際に中を歩いているかのような感覚を得られ、職場への理解も深まります。私たちがメタバースを選ぶ理由は、物理的な制約を超えて、「伝えたい相手に確実に届けられる」からです。リアルな展示空間を作っても限られた人しか来られませんが、メタバースならURL一つで、誰でも、どこからでもアクセスできるので。
また、現時点ではメタバースを活用した体験を提供していますが、将来的には自身の研究結果も活用し、リアルな世界でも誰もが自分の好きな空間を持てるような仕組みにしていきたいと考えています。
写真左:株式会社Urthのロゴ。社名の由来は「You(U)are the earth」、全ての個人が輝く社会になった状態の地球と、全ての個人との関係を表している
写真右:Urthサービスの一例。障がいのある児童たちが、それぞれの思い描く街を粘土で表現した作品をメタバースで再現した「子ども達が創る、子ども達のためのメタバース」の展示。空間を通じて世界の感じ方を共有することを狙った
――建築や空間デザインに関心を持ったのはいつですか?
中学2年生の時です。もともとはテニス選手になることに憧れていたのですが、プロ選手との実力差を痛感し、「他に何か面白そうな仕事はないかな」と漠然と考えるようになったんです。そんな時にテレビで見たのが、リフォーム番組『大改造!! 劇的ビフォーアフター』(テレビ朝日系列)でした。
リフォームの依頼者が、一流建築士の匠(たくみ)によって生まれ変わった空間を目の当たりにし、感動のあまり泣いている姿を見て、「空間を変えることで人をハッピーにできるって、すてきな仕事だな」と強く感じました。それをきっかけに、建築士を目指すようになったんです。せっかく働くなら、人を喜ばせる仕事がしたいと思っていた自分にぴったりだ、という直感もありました。その思いを胸に、建築で有名な早稲田大学創造理工学部に入学しました。

取材中の田中さん。株式会社Urthオフィス内にて
――起業のきっかけは何ですか?
大学2年生の春学期、特に都会ではリアルな建築をする場所が物理的に減ってきていることから、何か新たな視点が必要だと考え、建築学科以外の早大生とも関わってみたいと思ったんです。そこで、商学部のオープン科目「ビジネスアイデア・デザイン(BID)」を履修しました。BIDはビジネスの立ち上げ方を学ぶ授業で、初回に「人の困りごとを解決するアイデアを100個挙げよう」という課題が出されました。私は“空間デザイン”という建築的な視点からアプローチし100個のアイデアを出しましたが、同じグループの政治経済学部や商学部の学生たちは30個ほど。彼らはビジネスモデルの視点から課題を捉えており、そのアプローチの違いがアイデアの数に表れたのかもしれません。このギャップには強い衝撃を受け、「自分が学んでいる建築の考え方って、他の領域にも使えるんじゃないか?」と気付いたんです。
せっかくアイデアが浮かんだなら、実際に形にしてみたいと思って。高校の同級生たちやBIDで出会った早稲田の友人も含めて4人で、プロダクトを作り始めました。当時所属していたサークルで、東京都内のテニスコートの空き状況を一括で検索できる予約システムを開発するなど、日常の困りごとを見つけてプロダクトを作っていましたね。

株式会社Urthの立ち上げメンバーとの一枚。仲間とのカジュアルな活動が、早稲田大学の支援を受けて会社組織へと発展していったという
――そこから、どのようにして起業に至りましたか?
起業家育成を目的とした講義を履修していた大学3年生の時に、研究ベースを事業化へとつなげる早稲田大学の企業支援プログラム「WASEDA-EDGE ギャップファンド・プロジェクト」に挑戦しました。結婚式を挙げるカップルと作詞・作曲をする芸大生をつないでオリジナル曲を作り、式場での演奏やCD化までを行うオンライン契約システムを提案したら、最高評価をいただき、150万円の寄付支援を受けられることに。そこで思い切って、起業することを決めました。ただ、始めて1カ月後にコロナ・パンデミックとなり、取り引き先の結婚式場が次々と閉鎖してうまくいかなかったので、翌年4月に以前から興味のあったメタバース事業に挑戦し、今につながっています。
写真左:「WASEDA-EDGE ギャップファンド・プロジェクト」で活動したメンバーとの一枚
写真右:株式会社Urthの役員。田中さんは10年先の会社の行方を見据えて、大学で研究を続けている。創業直後は、他のメンバーにはあえて別の会社で社会経験を積んでもらい、現在はその経験をチームに生かしてもらっているそう
――最後に、これから何かに挑戦しようとしている早大生に向けて、メッセージをお願いします。
何かに挑戦する段階で大事なのは、自分が心からそれを面白いと思えているかどうか。例えば、そのことが頭から離れず、シャワーを浴びているときにもふと考えてしまうのなら、ぜひ実行に移して一生懸命取り組んでみてほしいです。私の場合は、空間を表現の手段にすることに、自分の時間を投資していければと考えています。
一方で、「やりたいことが見つからない」と悩む学生も多いと思います。そんなときは、ふらっと外に出てみたり、ただ部屋でぼーっとしてみたり、自分を少し客観的に見つめてみて、自分が何にわくわくするのかを知ることから始めてみてください。例えば、「誰かが目の前で喜んでいる姿を見るとうれしい」という気持ちに気付いたら、あとはその気持ちをどう形にするか手段を考える。とにかく見つけることを「本気」でやってみて、自分の中にある「欲望」をきちんと深掘りすることだと思います。
第902回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
文化構想学部 3年 西村 凪紗
【プロフィール】

起業家教育の一環である海外武者修行プログラムで訪れたイスラエルにて。現地の起業家に自社の取り組みを説明するなど、積極的な交流を行ったそう
東京都生まれ。広島県修道高等学校卒業。転勤の多い家庭環境の下、東京都・高知県・広島県と各地を移り住んだため、お酒の席では土佐弁と広島弁が混ざる話し方になるそう。中学生から続けている趣味のテニスは、大学でもサークル活動で継続。好きなワセメシは「ひまわり」と「油そば専門店麺爺」。油そばは、白味にポン酢をかけるのがお気に入りの食べ方だとか。












