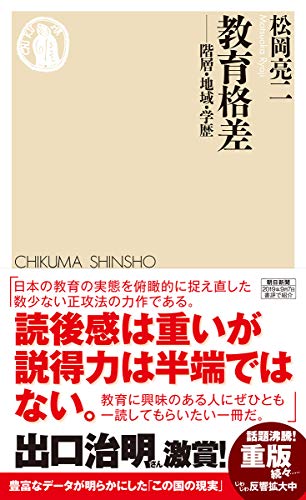「自分のコンフォートゾーンから、一歩出る勇気を持ってほしい」
国際教養学部 3年 小島 慶久(こじま・よしひさ)
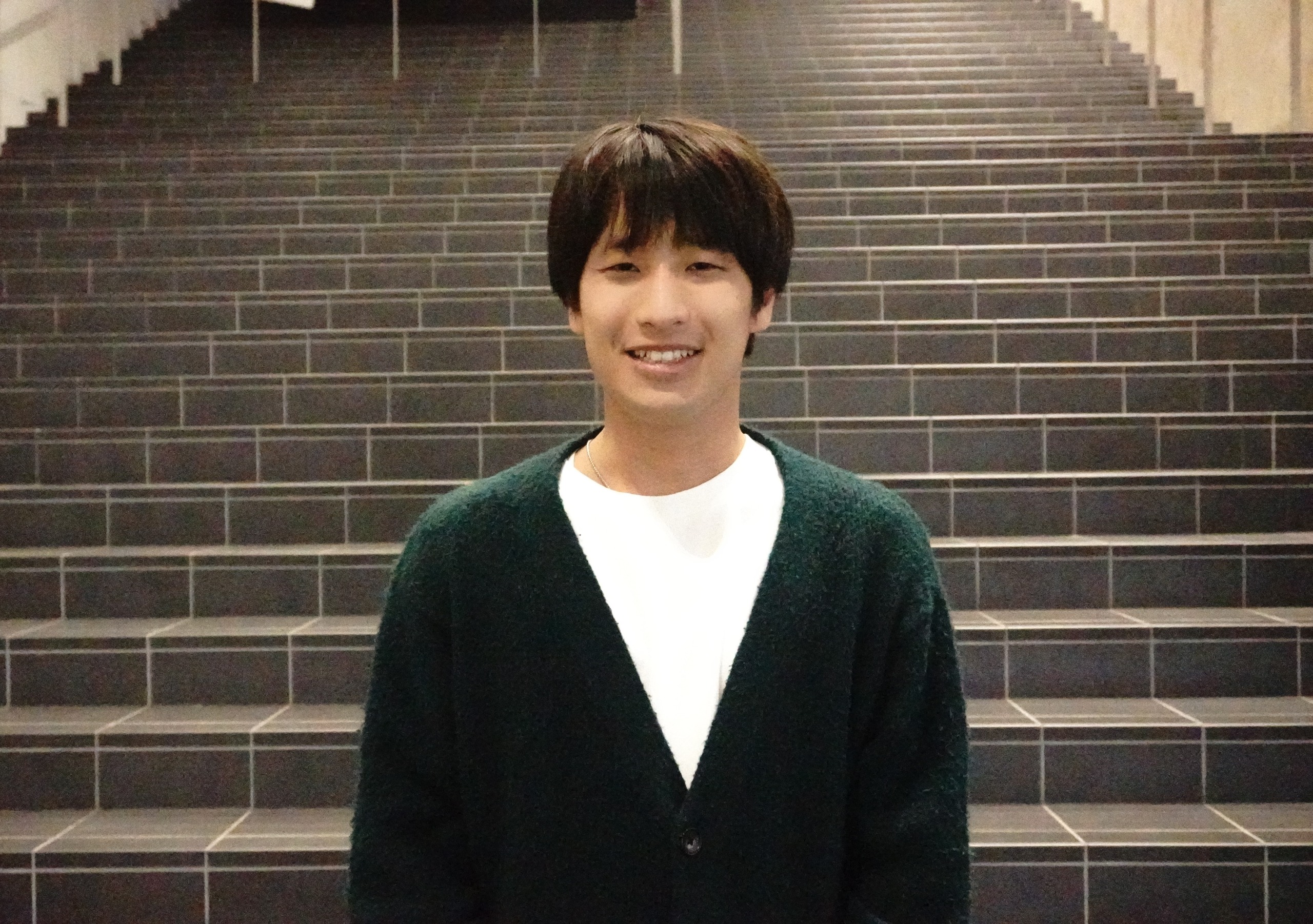
早稲田キャンパス 11号館にて
経済的な理由で塾に通えない小中学生を対象に、自身が所属する「BORDER FREE」(WAVOC登録サークル)で学習支援を行っている小島さん。近年の大学の受験方式で増えている総合型選抜入試(学校内で学習面以外での経験や学びを重視する入試)では、家庭の経済状況や環境によって生じる経験格差に課題を感じたことから、高校生がカフェの運営を通じて社会経験を積める場「ハイスクールカフェ」をメンバーと共に立ち上げました。そんな小島さんに、このプロジェクトを行った背景や今後の展望について聞きました。
――はじめに、「ハイスクールカフェ」について教えてください。
高校生が実際にカフェを運営する実践型のプロジェクトです。主にSNSを通じて計10名の高校生を募集し、都内のレストランを営業時間外にお借りして開催しました。2チームに分かれて各4回ずつの売上を競い合い、カフェの売り上げは「BORDER FREE」に寄付する形をとっています。
高校生たちは、当日の接客や調理といった現場の業務だけでなく、オリジナルメニューの開発や広報活動、収益予測など、企画から運営までを2024年9月から4カ月かけて自分たちで進めました。単なる経営体験にとどまらず、実社会で求められるようなスキルをしっかりと身に付けられる学びの場になっています。僕と「BORDER FREE」のメンバーを中心として、場所を提供してくれるレストラン探しや企画当日までのミーティングを通じた高校生のフォローを行いました。

ハイスクールカフェ当日の様子。新宿区の『BISTRO Carrot』を借りて、にぎやかに営業! 小島さんは高校生の当日運営をサポートしました
――なぜ「ハイスクールカフェ」を立ち上げようと思ったのですか?
このプロジェクトが生まれた背景には、早稲田大学をはじめ、大学全体の受験方式で総合型・学校推薦型選抜が増えているという現状があります。そのうちの一つである総合型選抜では、例えば「留学で海外の学校に貢献した」「国際数学オリンピックに出場した」など、恵まれた環境にいないと得ることが難しい経歴が評価されているように感じられたんです。最近では総合型選抜に特化した専門塾も増えており、お金をかけるほど有利な立場に立てる状況が進んでいると思います。そこで、各家庭の経済力に左右されず、高校生が主体的に取り組める体験を提供したいと考え、「ハイスクールカフェ」を立ち上げました。
――そもそも「教育格差」に興味を持ったきっかけや、大学で「BORDER FREE」に入ろうと思ったのはなぜですか?
きっかけは、大学受験後の春休みに読んだ、早稲田大学の元准教授である松岡亮二さんの『教育格差』という本でした。教員を目指していたものの、それまで教育格差の存在を意識したことはなかったので、本を読んだ時は「何だこれ!」と衝撃を受けましたね。
僕は中高一貫の私立学校に通い、特に困ることなく大学受験もさせてもらえたので、教育環境に恵まれていたと感じています。その一方で、同じような機会を持てない人もたくさんいるという現実を知って、「自分にも何かアプローチできることがあるんじゃないか」と考えるようになりました。この考えは、フランス語の「ノブレス・オブリージュ」(恵まれた立場にある者の責任)にも近いものがあり、教育系のサークルを調べている時に見つけた「BORDER FREE」の理念と重なると感じたため、参加を決めました。
写真左:教育格差に目を向けるきっかけになった『教育格差』松岡亮二(筑摩書房)
写真右:「BORDER FREE」の活動の一つ、「わせだ教室」。「基礎から楽しく学べる」をモットーに、小中学生を対象にした集団授業を行っている
――実際に「ハイスクールカフェ」を運営してみてどうでしたか?
参加者からの反響はかなり良かったですね。「新しい自分の側面に気付いた」「学校ではできない経験を積めた」といった感想に加え、「ビジネスにおける0から1を作っていく流れを体験できた」というフィードバックをもらえました。全く知らなかったメンバーと協力しながら一つの成果物を作り上げ、社会に関わるという高校生活ではあまりない経験ができたことを、特に貴重だったと感じる参加者もいたようです。
写真左:企画を練っている高校生たち。経営体験は初めてなので、マネジメント戦略を小島さんたち大学生がアドバイスした
写真右:高校生たちとの事前ミーティングの様子。価格設定で結論が出ず、大学生から手厳しいフィードバックが飛び交う一幕も
一方で、われわれの広報力がまだまだ足りないと痛感しました。高校生たちも必要性を感じていたからこそ参加してくれたと思いますが、本来のターゲットである経済的理由で挑戦を諦めざるを得ない高校生たちはもっといると思うので、まだ十分に情報が届けられていないと感じていて。今後は、SNSを使った広報力の向上やプロジェクトの規模拡大を通じて、より多くの高校生にリーチできるようにしたいと考えています。
また、「カフェ」という形態はあくまで手段なので、今後は別の形式でも経営体験を通じて、より多くの高校生が主体性を持ち、新しい自分を発見できるような機会を提供し続けたいと思っています。
――「教育格差」について大学生ができることは何だと思いますか?
「教育格差」の存在を知り、問題を認識することだと思います。早稲田大学のような私立大学に通える環境があることは、決して当たり前ではありません。「そもそも自分がなぜ大学に通えているのか?」を問い掛けてみてください。自分の置かれている状況を客観視することが、社会の現状を知る第一歩だと考えます。
また、僕が大学で出会った人達を見ていると、「ここでいいや」と自分のコンフォートゾーンから抜け出せていない学生が多いように感じます。未来を担う私たちが社会を少しずつ変えていくためにも、ちょっと踏み出して新しいことを知ろうとする勇気が、今こそ必要とされているはずです。
――最後に、今後の目標をお願いします。
「BORDER FREE」としては、2032年を目途に子どもが社会人になるまで継続的に学習をサポートできる仕組みを、全国規模で作ろうとしています。学生が運営しているからこそ、より多くの人に共感してもらえるのでは、と考えているので、東京以外でも活動を展開して、日本各地で「教育格差」の是正につなげたいという目標があります。
僕自身は、大学卒業後に民間企業への就職を経て、小中学校の教員になりたいと思っています。小学校時代の恩師がホテルマンの経験がある方で、授業が楽しいか毎回アンケートを取るなど、子どもファーストな先生でした。教育以外の経験があるからこそ厚みのある指導ができると感じ、自分もまずは別の業界で経験を積みたいと考えています。そして、いつか恩師を超える存在になりたいです。
第896回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
文化構想学部 3年 西村 凪紗
【プロフィール】

『フォーカス』にも登場した「BORDER FREE」のメンバー石井陽斗さん(左から2人目。商学部・2025年3月卒業)と卒業式で。右端が小島さん
神奈川県出身。桐光学園高等学校卒業。好きなワセメシは「油そば専門武蔵野アブラ學会」。1年生の時からお店のブラックカード(計50回来店した人に贈呈される特典)を保有し、食べたいときには1日2回訪れることもあるほどの熱狂ぶりで、サークルメンバーにも布教中。映画『スター・ウォーズ』が好きで、幼稚園の頃から字幕付きの英語で鑑賞しており、それが現在の英語力にもつながっていると語る。