
社会問題ってなんだか敷居が高い…そう思う早大生も多いかもしれません。新コーナー「教えて! わせだ論客」では、社会が抱える特定の問題に着目し、4人の教員からそれをひもとくヒントを教えてもらいます。
2023年度のテーマは「平和をどう守る?」。ロシアによるウクライナ侵攻などで世界情勢が不安定になる中で、あらためて平和とは何かを考えます。2人目のゲストは国際政治現象を科学的に論じる、多湖淳教授(政治経済学術院)です。テーマへの回答などをお話しいただいた前編に引き続き、後編ではご専門や現在行っている研究内容、早大生へのメッセージなどを伺いました。
多湖先生、これからの国際社会で生き抜くには、どんな力が必要ですか?
イデオロギー的な意味で「イズム」にばかりとらわれてしまうと、主張・主義ばかりで客観的な議論にならないケースがあることを認識し、意見を述べる際はデータでエビデンスを示すことが大切です。
感覚や感情で語らず、データに基づいた意見を述べることが重要
多湖先生のご専門「国際政治現象の計量分析」について詳しくお聞かせください。
戦争や紛争をデータで分析して、可視化する研究です。戦争が起こるきっかけ、終わるパターンなどをデータで可視化できれば、戦争を止める方法が見えてくる可能性があります。
例えば、過去のデータを分析すると戦争は近隣国の間で起こる確率が高いということが分かります。遠い国と戦争する国は、相対的に珍しいことも統計データを見れば分かります。
他にも1980年代に「民主的平和論」がはやったのですが、だからといって民主化を進めれば平和が生まれるわけでもないということも近年のデータ分析で明らかになりました。「民主的平和論」とは、民主主義国家同士では情報の透明性が高いので、戦争は起こりにくいという「常識」からも分かる話で、これはジェームズ・フィアロンの「合理的戦争原因論」(前編参照)からも妥当に思えます。しかし、選挙のある民主主義国家では、政治家が人気取りのために、愛国心をあおる危機を自ら作りがちなので、しかもそれは民主化過程では顕著な冒険主義に出る誘引が高まり、統計的に有意に高いリスク要因になると分かってきています。結果的に民主主義を志向する社会でも特に独裁体制からの移行期には戦争が起きやすいのです。

戦争と平和を巡る科学的分析の基盤データセットを作ったのは、私の師匠にあたるミシガン大学のJ・デーヴィッド・シンガーという国際政治学者です。「戦争の相関研究( Correlates of War )」プロジェクトとして知られるデータベースで、今も多くの研究がこのデータに準拠して戦争や武力化した紛争を数え、それを巡るさまざまな情報を集約しています。
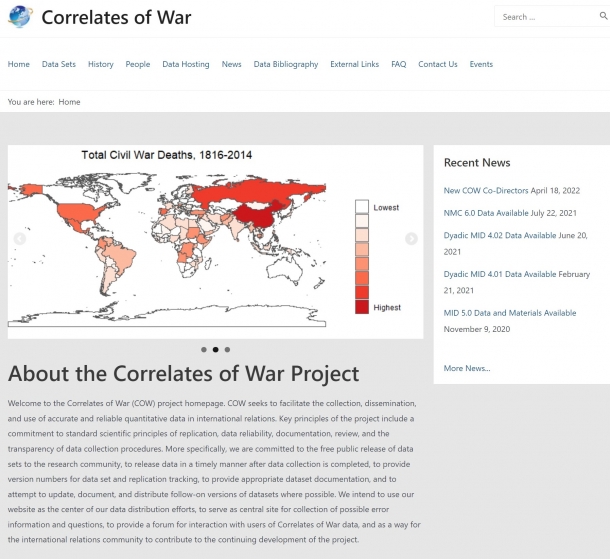
Correlates of War のWebサイト画面( https://correlatesofwar.org/ より)
具体的にどのような研究に携わっていますか?
2013年頃までは、いわゆる回帰分析を用いて、武力行使が単独または多角的に行われるかの分析をしたり、有志連合・同盟を巡るデータ分析をしたりしていました。米国の武力行使に関して研究した内容は、ランド研究所(※)の報告書でも何度も引用されていて、政策インパクトもあるなと感じています。逆に英語で書いているそういった研究は日本ではほとんど参照されない悲しさはありますが。
(※)米国で有力な安全保障政策シンクタンク。
現在は回帰分析よりもより実験手法に重きを置いて、国家間の戦争に関するさまざまな研究をしています。例えば、領土紛争で2国間がどれだけ譲ることができるか、さらに譲歩をしても政治家がどれだけ支持率を下げずにいられるかといった事例もデータで可視化できます。政治家が体面を保つことを「フェースセービング」というのですが、どうしたら「フェースセービング」しつつ戦争状態から撤退できるかを世論調査に実験を組み込んで分析しています。
世論調査ベースの研究としては他にも、「核兵器を持ったり、使ったりしてはいけないと思っている国民は安定的にどのくらいいるか」といったことも調査しています。日本のあるNPO団体が国内で実施した調査では、核保有を肯定する割合は9%から多くても10数%という結果だったのですが、調べてみると匿名性の低い調査方法だったことが判明。あらためて私の研究室でインターネットを使った匿名性の高いアンケートを行ったところ、20〜33%まで核肯定派の比率は上がりました。
世界で唯一の被爆国である日本においても30%近い国民が核保有を肯定的に考えているだろうということが、データ分析から見えたように、客観的なデータを正しく得ることはとても大切です。そして、感覚や感情で語らず、データに基づいた意見を述べることが重要なのです。
早稲田大学の学生は、「Qualtrics(クアルトリクス)」というオンラインのアンケート作成・分析ツールを誰でも無料で使うことができます。自身の研究などでこうした環境をフル活用してもらいたいですね。
平和について、研究者は科学に基づく処方箋を出せる
現在は、早稲田大学でDPPSというプロジェクトを主宰していらっしゃるようですね。
現在私が中心となって、「多湖・DPPS研究拠点構築プロジェクト」を進めています。DPPSは、「Dual Positive Peace Science」の略で、「安全保障を軸にした科学的国際政治研究者のアジア太平洋地域研究拠点の構築」を目的としています。
現在のアジア太平洋地域は、「戦争と平和」でいうと、戦争に近づいているという懸念を私は強く持っています。これに対して、研究者は科学に基づく処方箋を出せると考えています。そのためにもアジア太平洋地域の研究者がネットワークを作って研究に取り組める枠組みが必要だと考えています。世界中から学生が集まって議論が繰り広げられている早稲田大学は、まさにこの研究の拠点にふさわしいと思っています。
写真左:香港大学でのシンポジウムにて北海道大学 小浜祥子准教授と(2019年)
写真右:ベルギー・ブリュッセルにて、紛争研究を専門にする各国の研究者たちとの定期的な研究会(2014年)
今後、学生と一緒に進めたい調査やデータ分析はありますか?
現在は、アジア太平洋の国々における「不満」の研究を進めています。日本、中国、台湾、ベトナムなどを対象に、インターネットを使った世論調査を行い、どうしたら相手を敵と思わない状況を形成できるのかを考えていきたく、さらにデータで可視化したいと思っています。危機感をあおられた各国の国民が不安な気持ちを抱えるのは当然です。しかし、どこかで軍拡を抑制し、軍縮に進まないと社会は破綻してしまいます。
先ほどの「フェースセービング」にも通じますが、国民に不満を抱かせずに軍縮する方法を見いだせれば、現在のアジア太平洋地域において大きな意味があることです。
多湖先生の紹介動画。「多湖・DPPS研究拠点構築プロジェクト」の説明も
最後に、これからの国際社会を生き抜く学生たちにメッセージをお願いします。
従来の国際政治学は、リアリズム、リベラリズムといった「イズム」を通して議論する作法が主流でした。しかし、「イズム」にばかりとらわれてしまうと主義・主張ばかりで客観的な議論にならないケースもあります。意見を述べる際も演繹(えんえき)的にデータでエビデンスを示すことで、全く質の違う議論になります。
「平和をどう守るか」という議論も例外ではありません。科学的データに基づいたロジカルな議論を深めていくことが、国際政治学においても不可欠だと思います。

多湖 淳(たご・あつし)
政治経済学術院教授。博士(学術)東京大学。専門分野は国際政治学。主たる関心は米国外交、同盟・有志連合、計量手法で、国際政治現象を巡る計量分析、特に近年は量的テキスト分析やサーベイ実験の手法を用いて活動している。
公式サイト:https://a-tago.github.io/
取材・文:丸茂 健一
撮影:深堀 雄介
画像デザイン:内田 涼
▼前編はこちら!










