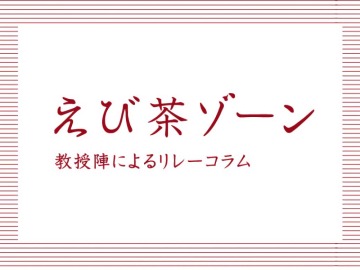
2022年11月1日から京都で開催された国際シンポジウムに参加した。対面で実施されるのは3年ぶりで、一昨年、昨年はオンライン開催であった。参加してみて、やはり対面はいいと再確認した。行く前の「ワクワク感」がある。会場での「空気の共有感」が違う。懐かしい人にも会えるし、お土産の交換もできる。参加者の中には「帰りたくない」と訴える者もいた。
コロナ禍の3年間で私に植え付けられたものの中で最たるものは、オンライン会議への嫌悪感である。特に、海外とのミーティングにおいてそれは甚だしい。オンライン会議は手軽にでき、対面のように移動の時間や交通費を必要としないため、感染拡大が始まった2020年には特にもてはやされた。しかし、現在はオンライン疲れを感じている方が多いのではないだろうか?
オンライン会議では、対面にはない「嫌な疲れ」を感じる。特にそれが私にとって母語ではない英語であればなおさらである。対面であれば英語が堪能でなくても、身ぶり手ぶりや表情などあらゆる手段を駆使してコミュニケーションを行える。隣の仲間に話を振ることもできる。オンラインでは、基本会話は1対1であり、表情しか分からない。相手がマスクをしていれば表情すら分からない。隣同士でコソコソ話をするざわざわ感もない。コミュニケーションの「豊かさ」がないのである。
この3年間のコロナ禍で、私たちは多くのものを失った。赤ちゃんや子どもたちはマスク越しの会話の中でどう育つのだろう? 失った豊かなコミュニケーションを、私たちはアフターコロナにおいて取り戻すことはできるのだろうか?
(TH)
第1143回








