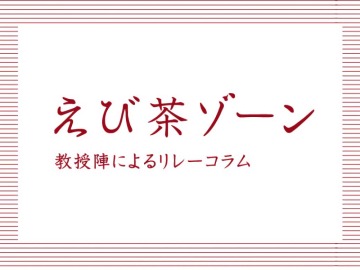
自然、文化、社会などについて学ぶため、対象とする地域に赴いて調査することをフィールドワークという。フィールドワークでは実際に現地に赴くからこそ知り得る貴重な情報を取得できるため、今や卒業研究などにそれを取り入れている学生も多いことだろう。
ところで、フィールドワークの経験がある学生の中で、「調査される側」のことを考えたことがある人はどれほどいるだろうか? 私は日本のあるへき地で数十年継続してフィールドワークを行ってきた。現地には家族のように付き合ってくれる友人・知人も大勢できた。彼らが言う。
「この地域には特徴的な自然や文化があるためか、研究者や学生がひっきりなしにやって来る。彼らから毎回同じ場所への案内を頼まれ、同じような質問をされ、そしてわずか数日滞在して帰って行く。彼らはたいてい来るのは一度きりで、その後研究成果を知らせてくれることはまれ。われわれは学問の題材として消費されているだけなのか」
調査者にとってフィールドワークは「非日常」である。普段とは異なる情景や風習に触れることができるため、たとえ短期の現地滞在でさえ心躍る貴重な体験となる。「非日常」の高揚からか、あるいは学問は高尚だというおごりからか、現地の方々に多少無理を言っても許されると勘違いする者もいるかもしれない。フィールドワークは、現地の方々からすれば「日常」に踏み込まれ、時にそれをかき乱されるやっかいな存在にすぎないということを、調査者は今一度自覚すべきだろう。調査地を「へき地」、現地の知人を「家族」などと安易に、一方的に表現してしまう筆者の自戒も込めて。
(K.K.)
第1139回








