「学生参画/スチューデント・ジョブ」スタッフの横顔
キャンパスで学びながら、大学の価値向上につながる活動に参画したり、働いたりする学生たち。このように、大学で重要な役割を担っている「学生参画/スチューデント・ジョブ」にはどのような学生が、どのように携わっているのか、彼らの横顔を紹介します。今回は、「早稲田を知る」「早稲田スポーツを学ぶ」(いずれも早稲田大学校友会支援講座)で授業事務補助者として働く、文化構想学部4年の吉澤拓真さんと、日本語教育研究センターの日本語授業ボランティアに携わる、法学部4年のバシューツカヤ エレーナさんです。それぞれの活動から2人が感じたこと、考えていることを紹介します。
▼「早稲田を知る」「早稲田スポーツを学ぶ」授業事務補助者
▼日本語授業ボランティア
「早稲田を知る」「早稲田スポーツを学ぶ」授業事務補助者
文化構想学部 4年 吉澤 拓真(よしざわ・たくま)

Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつから関わっていますか? また、きっかけや動機を教えてください。
1年生の頃からSJC(学生参画・ジョブセンター)の学生スタッフとして、学生生活課厚生デスクに勤務しているのですが、ある日、職員の方から、「早稲田愛に溢(あふ)れた先生が、早稲田愛に溢れた学生を探している」と、この講座の授業事務補助者募集について案内がありました。「そんな学生は自分しかいない!」と応募を決意。その後、コーディネーターの葛西順一先生(スポーツ科学学術院教授)と打ち合わせをし、2021年4月から授業事務補助者として勤務を始めました。
Q. どのような活動をしていますか?
2021年度春学期の「早稲田を知る1、2」、秋学期の「早稲田スポーツを学ぶ1、2」の計4科目において、授業事務補助者として勤務しました。授業実施期間中は週に1度、事務所で出席管理の作業補助をしました。コロナ禍で通常とは異なる対応を迫られる場面がありましたが、先生や職員と相談しながら状況に合わせた対応をしました。また、春学期には大隈記念講堂と早稲田キャンパス10号館にて、それぞれ田中愛治総長、佐賀県の山口祥義(よしのり)知事による2回の対面授業が行われましたが、その際は会場の設営や出席カード配付、マイクの管理を行いました。
Q. 活動を通して感じたことを教えてください。
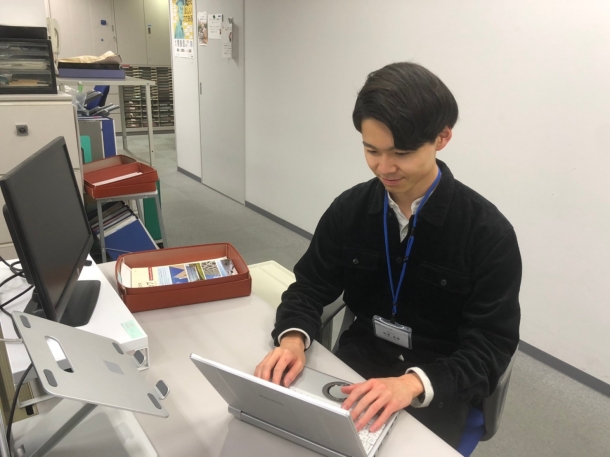
事務所にて出席管理をしている様子
早稲田大学草創期の功労者や、早稲田スポーツの舵(かじ)を握ってきた数々のアスリートの思想・信条・活動に触れ、これまで漠然としていた「早稲田が好き」という自分の気持ちに、より確かさと奥行き、それに温かさが加わりました。毎週200人を超える履修者の出欠確認などには骨が折れましたが、同じ講義でもおのおのが違った立場で早稲田との関わりを見いだし、それを自分の言葉で力の限り表現する在り方にぐっときました。コロナ禍で、肩を組んで校歌を歌うことが難しい中、履修者の言葉からは「私は早稲田の一員としてここにいるんだ!」という熱い叫びが感じられました。
Q. 活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。
就活生となり、この講座の授業事務補助者からは離れますが、引き続きSJC学生スタッフとして学生生活課で勤務する中で、確固たる早稲田愛を発揮していきたいです。特に、校友(卒業生)の方が窓口に来られた際は、話が盛り上がること間違いないでしょう。

早稲田キャンパスにある會津八一記念博物館にて。早稲田の歴史、功労者にまつわるミュージアムにも積極的に足を運ぶようになりました
授業期間中の1週間の過ごし方
日本語授業ボランティア
法学部 4年 バシューツカヤ エレーナ

撮影:SJC学生スタッフ(政治経済学部 4年 山本 皓大)
Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつ関わりましたか? また、きっかけや動機を教えてください。
2021年4月下旬からです。私は小学生のときに日本へ来たのですが、日本語を学ぶ中で難しいと感じることがたくさんありました。そこで、同じような思いをしている学生の力になりたいとボランティアに応募しました。また、短時間でも参加できる点も魅力的に感じた理由の一つです。
Q. どのような活動をしましたか?
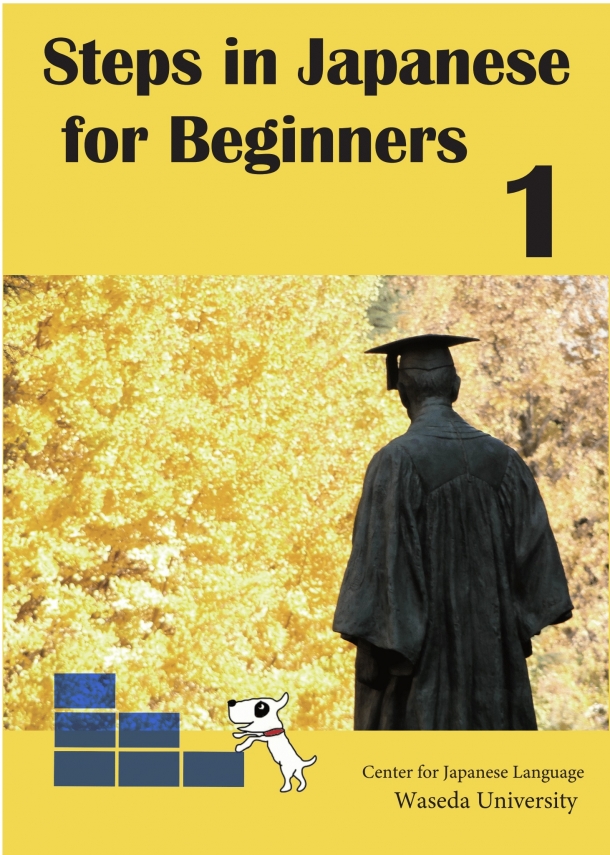
参加した授業で使用した教科書
2021年度秋学期は、金曜1限にオンラインで行われる日本語授業に参加し、ボランティアとして先生の補助をしました。この授業は早稲田大学の日本語教育研究センターが留学生向けに提供しているもので、プレゼンテーションと授業内での意見交換、授業の感想課題を通して日本語能力を高めることを目的としています。その中でボランティアに課せられる役割は、ブレイクアウトルームで留学生の話し相手となること、プレゼンテーションや感想課題などのフィードバックをすること、授業についていけない学生や質問がある学生にチャットなどで対応することです。一番難しかったのは、スピーキングアクティビティへのフィードバックです。ただ間違いを指摘するだけでなく、その理由を分かりやすく説明するのに苦戦しました。
Q. 活動を通して感じたことを教えてください。
このオンライン授業に参加して良かったと感じることの一つ目は、学生から「日本語を話す際に少し自信を持てるようになった」とコメントをもらったことです。この授業では、ブレイクアウトルームを使った少人数での話し合いやプレゼンテーションなど、自分の考えを日本語で話す機会がたくさんあります。最初は緊張していたものの、何度も言葉を発するうちに文法の間違いを気にせずに話そうと思えるようになったという学生の話を聞き、話し相手になって良かったと思いました。
二つ目は、世界中の参加者と話ができたことです。私が参加した授業では、中国や韓国、グアム、ドイツなどから16人の学生が参加していました。他の国の人々と話すことで母国語とは違う表現やフレーズを知るだけでなく、異文化間でのコミュニケーションの仕方を学ぶことができました。
授業の中で、「外国語を学ぶことは母国語を理解するのに役立つだろう」と話していた学生がいましたが、私もそう思いました。言語を学ぶ上で、一つの言語だけを扱うと言語間の比較ができないため、ものの見方を狭めてしまいますが、私自身、他の国を知ることで、自分の言語を客観的に見て理解できるようになりました。
また、何よりも先生がとても陽気な方で、授業を始める際には日本に関連した面白いビデオを共有したり、最近人気の話題を話したりと、積極的に授業を盛り上げてくださり、このオンライン授業にボランティアとして参加することができて良かったと感じています。
Q. 活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。
他の言語を話すことは脳の活性化や多文化理解の促進に加えて、気分転換にもなります。言語を変え、新しい視点を増やすことによって、異なるものの見方を見つけることができることを、ある学生は「新しい窓」と表現していました。授業に参加する中で私もそのような窓が本当に存在しているのではないかと感じました。外国語が話せれば、母国語だけで生活していた時と比べて、一気に世界を広げることができるからです。特定の言語の世界を理解するために、その文化にも触れていきたいと思っています。

オンライン授業に参加しているときの様子










