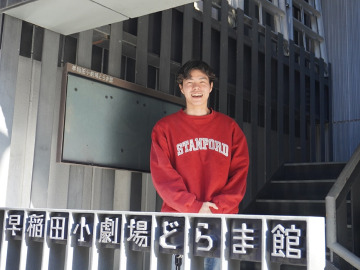この原稿を執筆しているのは2021年8月9日、東京2020オリンピックが終わった翌日である。これからパラリンピックはあるけれども、とにかくほっとしたというのが正直な感想だ。早稲田大学ゆかりの方も含め日本人選手の健闘が目立ったけれども、私はこのオリンピックに対して複雑と言うほかない思いを抱いている。
開催までは、このパンデミックの下でオリンピックを開催するなんて狂気の沙汰だと思っていた。このオリンピックによって、病気のために亡くなったり、後遺症で苦しんだりする人は増えるだろう。競技なんか見るのもいやだと本気で思っていた。だが、いざ大会が始まってみると、競技から目が離せなくなった。選手の真剣な佇(たたず)まいに引きつけられると、さまざまな懸念がきれいさっぱりどこかに消えてしまっていた。しかし、この高揚は感染の爆発的拡大というニュースによって不安のどん底まで突き落とされる。この不安をかき消すためにすがるような思いで再び、競技や競技についての報道をつい食い入るように見つめてしまう。東京2020オリンピックの17日間は、そういう毎日だった。
自分自身が当事者とならない限り、全てはどこか他人事なのだ。そこにいたのは、どこまでも自分勝手な覚束(おぼつか)ない千鳥足の「自分」だった。何をしたらよいのか、正直何一つ分からない。マスク、手洗い、三密回避という言葉は知っている。だが、競技をする選手、それに見入る自分、病に倒れる人々、心配するその家族、懸命の治療をする医療従事者の方々、これらが一つにつながる連帯――そんなきれいごとはまったく存在しなかったと思う。オリンピックは終わったけれど、この曖昧さ、自分勝手さ、何をしてよいか分からぬ戸惑いは続いている。たぶん私(たち?)はそこから逃れることはできない。
(K・M)
第1106回