2025年夏、発行部数35万部を超えた小説『近畿地方のある場所について』背筋(KADOKAWA)が映画化。他にも2021年には『変な家』雨穴(飛鳥新社)、2022年には『かわいそ笑』梨(イースト・プレス)といった書籍や、YouTubeチャンネル『フェイクドキュメンタリー「Q」』が話題を集めるなど、今、ホラーブームが巻き起こっています。実話怪談(※1)の語り手として活躍する吉田悠軌さんによると、これらのコンテンツには「共通する特徴がある」そうです。
(※1)実際に起きた不思議な体験を取材し、構成された怪談。

『近畿地方のある場所について』(KADOKAWA)。主人公のライター(背筋)が、近畿地方のある場所にまつわる怪談を集めるうちに、恐ろしい事実が浮かび上がる

吉田 悠軌(よしだ・ゆうき)
1980年東京都生まれ。2003年早稲田大学第一文学部卒業後、ライター・編集者として活動を開始。怪談の収集・調査を行いながら、同人誌『怪処』を自主制作するなど、オカルトや怪談の研究をライフワークとする。
“ホラーブーム”とはよく耳にしますが、ホラーっていつの時代もはやっていませんか? 人間ってなぜかホラーが好きですよね。
おっしゃる通り、むしろ全くホラーがない時代というのは、おそらく人類史の中でもないでしょう。ただしホラーにもさまざまな種類があり、時代によって注目されるジャンルが入れ替わります。スティーブン・キング(※2)のような独創的かつ重厚な世界観のホラーが流行する時代もあれば、実話怪談のようなリアリティーを求める時代もある。フェイクドキュメンタリー自体も実は新しいものではなく、1980年代には確立されていました。その中でのホラー作品として、映画『邪願霊』は先駆的存在です。
(※2)1947年生まれの米国の作家。『キャリー』(1974年)『シャイニング』(1977年)『ファイアスターター』(1980年)『IT』(1986年)『ミザリー』(1987年)など多数の作品を発表し、「ホラー時代の教祖」とも呼ばれる。
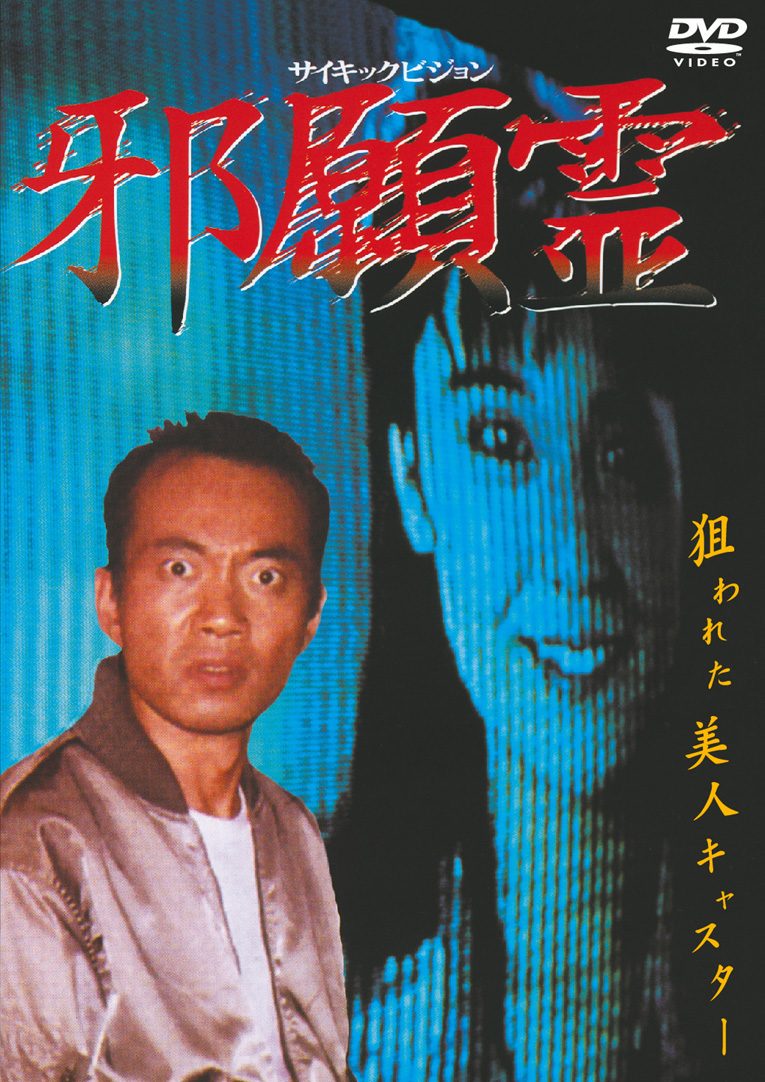
『邪願霊』各配信サービスで配信中(C)1988コスモオフィス。株式会社彩プロ(1988年)制作の日本映画。アイドルのプロモーション撮影中に不可解な事故が続出、テレビ局の取材班は真相究明に乗り出すが、カメラに写ったのは恐ろしい亡霊の姿だったというストーリー。吉田さんお勧めの作品
あえて「本当」ではなく、「本当っぽいもの」を楽しむことには、どのような意味があるのでしょうか。実話怪談では満たされない何かがあるのでしょうか?
「実際にあったことでないと楽しめない」という感覚がある一方で、「実際にあったことのように見える作り物だからこそ、安心して楽しめる」という感覚もあるのでしょう。さらに、実社会において「リアルかフェイクか」という区別が難しくなってきた現代の状況も、ブームに少なからず影響を与えているはずです。
SNSの影響は大きいですよね。さまざまな人の声を集められるようになった今、情報もリアルとフェイクが混ざり合っている。
物事の見え方も、人によってバラバラです。立場を変えることで、リアルとフェイクが逆転することもある。リアルとフェイクの境界線が曖昧になった今だからこそ、その絶妙な組み合わせが、人気を集めるのでしょう。









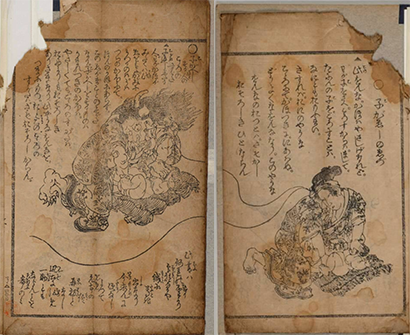




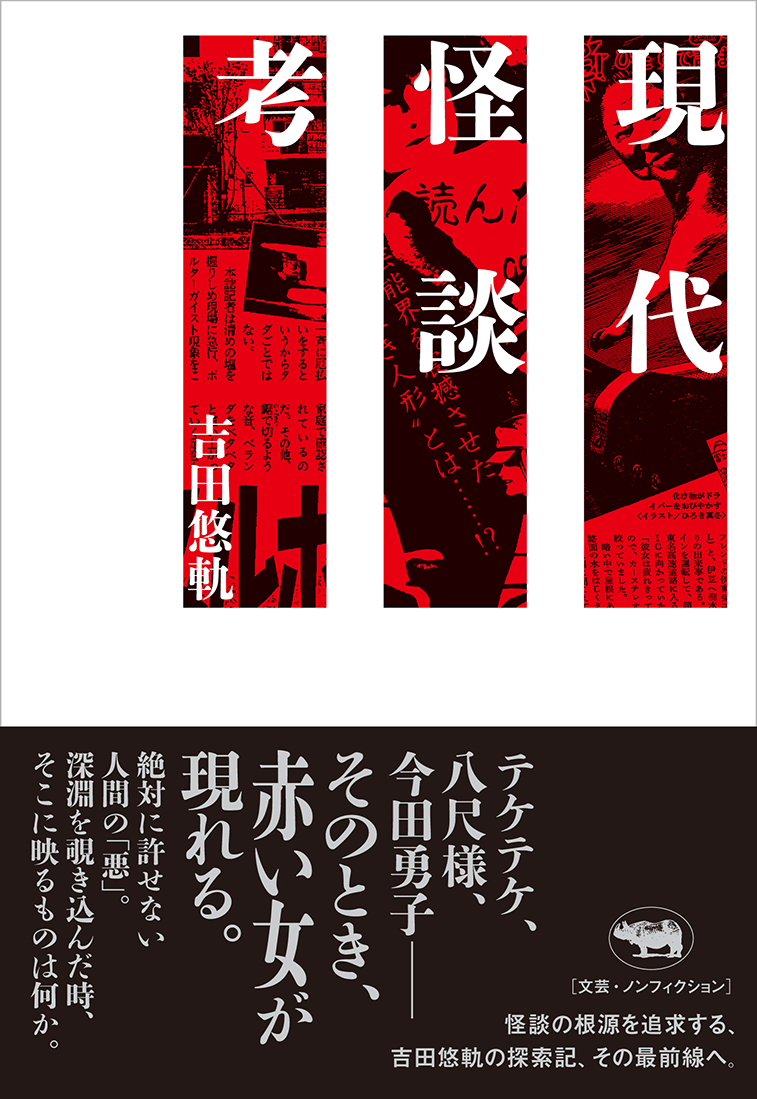
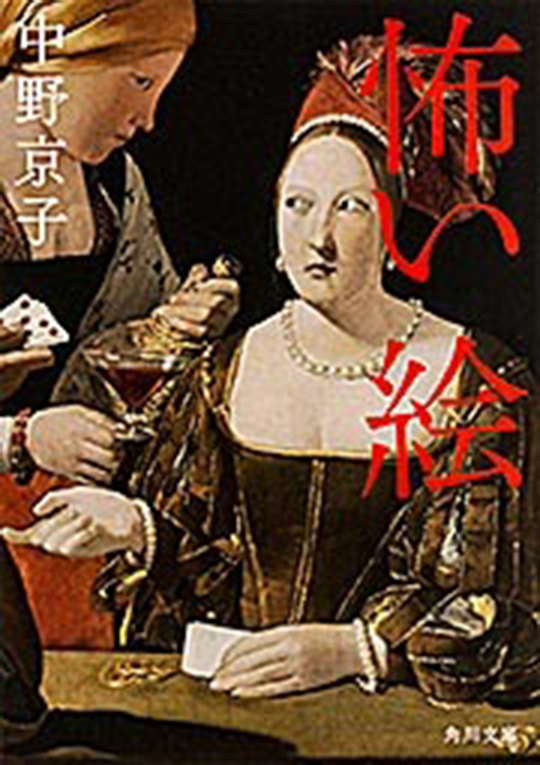







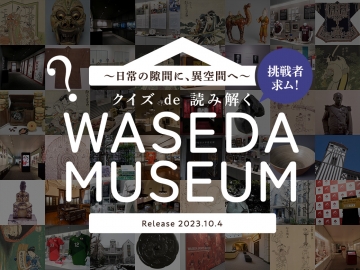
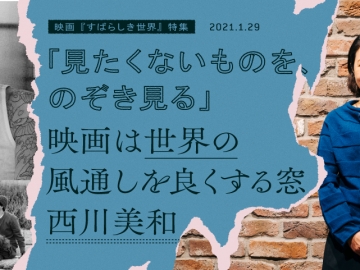


近年注目されているのは、ホラーの中でも「フェイクドキュメンタリー」というジャンルです。私が専門とする実話怪談とは異なり、その名の通り架空の出来事をドキュメンタリー形式で語る演出手法で、新聞の記事やビデオテープ、インターネットの投稿といった「架空の資料」を基に物語を構成していきます。根本は創作であるにもかかわらず、いざドキュメンタリー形式で語られると、受け手は「本当にあったのではないか」と感じてしまう。多くの創作ホラーでは得られない“リアルな手触り”が、ブームの中心にあるのでしょう。