
皆さんはボランティアを経験したことはありますか?「ボランティアって気になるけど、参加するきっかけが分からない」「災害現場のボランティアに未経験者が行くと、かえって邪魔になるのでは?」など、ためらっている人も少なくないのではないでしょうか。
早稲田大学には、早大生のボランティアを支援する平山郁夫記念ボランティアセンター(以下、WAVOC)があります。WAVOCは、本学の名誉博士である平山郁夫氏の国際的社会貢献の精神を継承し、ボランティア活動を通して地域社会・国際社会に貢献することを目的として設立されました。環境保全、教育支援、災害復興支援など、さまざまな分野のボランティア活動の参加募集を随時発信しています。今回は、WAVOCのボランティア活動に参加したことがある学生3人に、その活動内容と、ボランティアへの向き合い方について話を聞きました。
INDEX
▼高尾の森づくりスタディツアー
「大好きな自然を守るボランティアに初挑戦」
▼障がいのある子どもとスポーツをしよう
「子どもの成長を支える教員になるため、教育支援ボランティアにフォーカス」
▼能登半島地震災害復興支援ボランティア
「実際に被災地に赴き、災害に正面から向き合い続ける」
高尾の森づくりスタディツアー
「大好きな自然を守るボランティアに初挑戦」
商学部 2年 鈴木 論平 (すずき・ろんぺい)
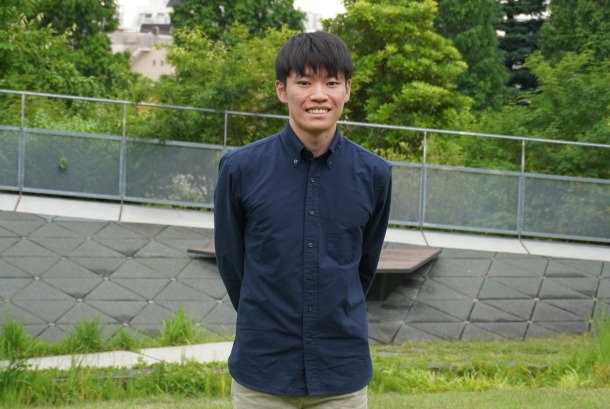
戸山キャンパス 戸山の丘にて
――「高尾の森づくりスタディツアー」に参加したきっかけは何ですか?
元々ボランティアに興味があったので、1年生のときにNPO法人が運営する中野区のゴミ拾い活動に参加していました。そのうち、ゴミ拾いだけでなくさまざまな社会貢献をしたいと思うようになり、WAVOCのボランティア活動に注目したんです。学外で探すよりも学生が参加しやすい敷居の低さや、他の早大生も活動する安心さがありました。
高尾の森づくりスタディツアーに参加したきっかけは、身近に大きな森林公園があり河川敷にいろんな生き物がすむ自然豊かな地域で育ったこともあり、自然に触れるボランティアをしたい気持ちがあったからです。このスタディツアーは年に何度か開催されており、私は2024年4月に参加しました。
――どのような活動内容か教えてください。
東京都にある高尾のこげさわの森で、森林の成長を助けるために樹木の一部を切り落とし、育成中の木々に日光が程よく当たるよう間伐する作業です。のこぎりや斧、ヘルメットなど必要な道具は準備されているので、こちらは山で作業することを考慮した服装と登山用の靴で参加すれば大丈夫でした。また、インストラクターの方から木の切り倒し方の指導を受けられるので、斧を初めて持つ自分でも安心して作業することができました。倒した木は枝を取り丸太の状態にするのですが、これを登山ルートの整備に利用するそうです。今までは、人の手を特に加えなくても自然は保たれるのではないかと考えていましたが、実は多くの人の管理によって森林が守られていることを肌で感じることができました。
写真左:こげさわの森の奥を進んだ道の険しい場所で間伐をしたそう
写真右:間伐に使用する「ヨキ」(斧)、「ノコ」(のこぎり)などの道具類
驚いたことは、インストラクターのうち一人の校友の方が、学生の頃、WAVOCの高尾の森づくりスタディツアーに参加しており、社会人になってからもインストラクターとして携わっていらっしゃったことです。このお話を聞き、自分も将来似たようなボランティアへの関わり方ができないかと考えるようになりました。
このような出会いや気付きは、普段の学生生活ではなかなか得られることはない、ボランティアならではの貴重な経験だと思います。
――今後、ボランティアにどのように携わりたいですか?
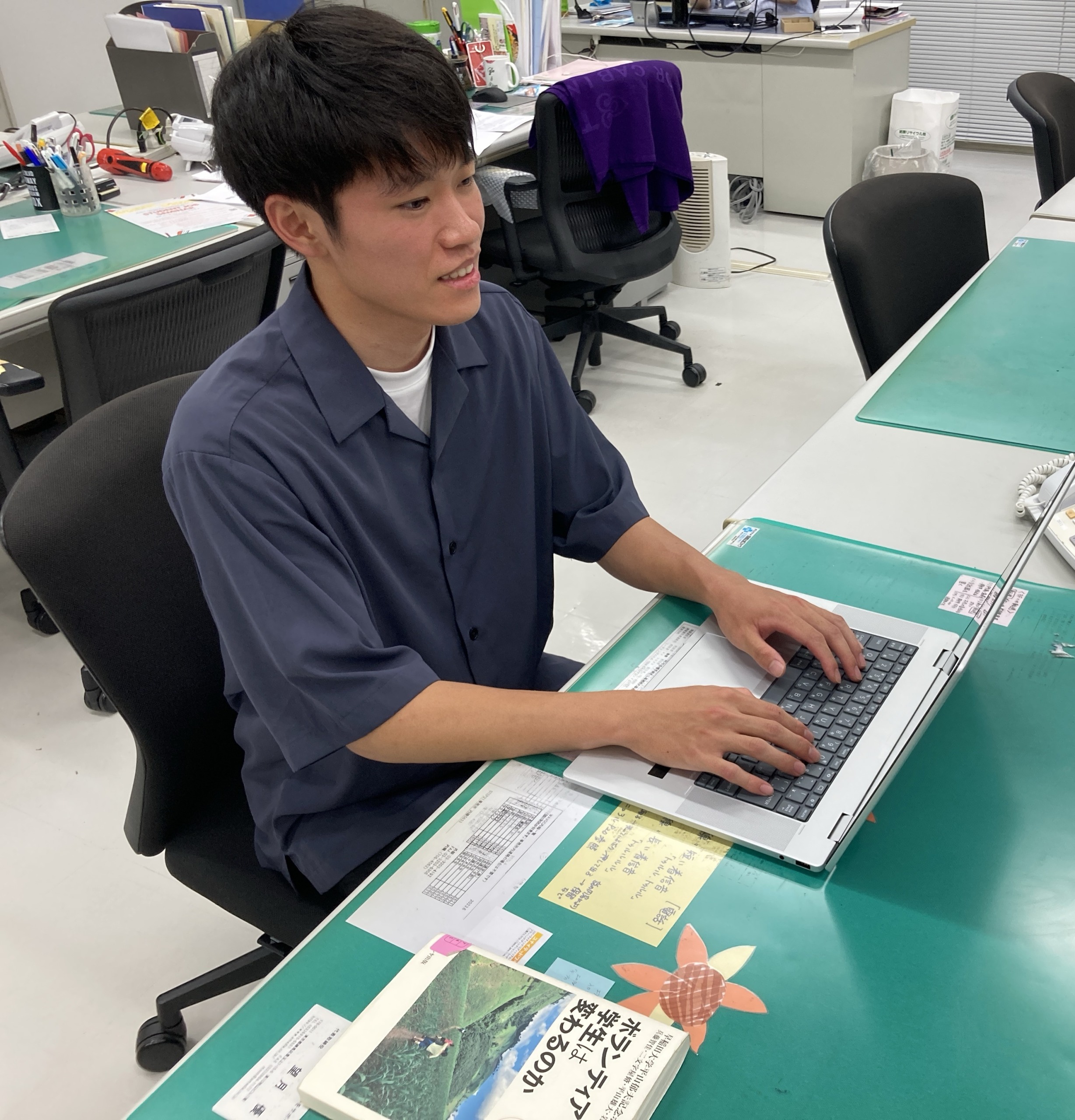
WAVOC学生スタッフとして、ボランティアの企画づくりをする鈴木さん
これからもボランティアを続けたいという思いからWAVOCの学生リーダーに応募し、2024年6月から務めています。学生リーダーの大きな仕事は、WAVOCのボランティア活動を企画することです。現在は自然を守るボランティアの企画づくりに力を入れており、WAVOCの職員の方に企画書をチェックしていただきながら、勉強しているところです。また、学生リーダーの仕事とは別に、今後は災害支援ボランティアにも参加したいと考えています。
高尾の森づくりスタディツアーのインストラクターの方々のように、ボランティアは本業とは別の形でできる社会貢献なので、卒業後も仕事と両立できるボランティアを見つけて、積極的に関わりたいと思っています。
障がいのある子どもとスポーツをしよう
「子どもの成長を支える教員になるため、教育支援ボランティアにフォーカス」
教育学部 2年 為我井 遥 (ためがい・はるか)

早稲田キャンパス99号館2階WAVOC事務所にて
――「障がいのある子どもとスポーツをしよう」に参加したきっかけは何ですか?
私は将来子どもたちの教育支援に携わりたいと思っているのですが、そのきっかけは、小学校5、6年生のときの担任の先生との出会いです。私たち生徒にいつも寄り添ってくださっていたことがとても印象的で、私も子どもの成長を支えられる先生になりたいと思い、高校生のときは学童ボランティアに携わっていました。
大学生になってからもボランティアは続けたいと思っていたので、早稲田大学のボランティア情報が届くWAVOCのメールニュースに登録していたんです。そこで、大学で受講している特別支援教育関係の講義以外にも実際に子どもたちと接する機会を得たいと思い、2024年3月に「障がいのある子どもとスポーツをしよう」に参加しました。
――どのような活動内容か教えてください。

サッカースクールでの試合前の様子。中央が為我井さん
子どもたちの練習に付き添い、サッカースクールの運営をサポートすることが活動目的です。最初に私たち早大生と子どもでペアを組んでボールを使ったウオーミングアップをし、そのあとグループに分かれて試合を行いました。スポーツを通じて子どもたちと仲を深めることができ、とても楽しい活動でした。
子どもたちとは、言葉で伝えるよりもジェスチャーなど体を使って接することで、サッカーを楽しんでもらう環境づくりをしました。体をフル活用したコミュニケーションを通して、相手に分かりやすく伝えることの難しさを実感しましたね。
――現在、どのようにボランティアに携わっていますか?
1年生のときからWAVOC学生リーダーも務めており、これまで5つのボランティア活動を企画し、実施してきました。例えば、「おもちゃ図書館ボランティア」は、中央区のこばとおもちゃのとしょかんのご協力で、子どもたちとおもちゃで遊ぶ企画を実施しました。これまでのボランティアでは小学生と接することが多かったのですが、ここではより年齢が低い子どもたちがメインで、言葉でコミュニケーションをするよりもおもちゃを使ってお互いが楽しく遊ぶことを重視しました。
また、「新宿子ども会 KIDS」(公認サークル)では幹事長を務めています。特別支援学級に通う子どもたちと触れ合うことが活動目的で、毎週土曜日に戸山公園近くの集会室を借りて、一緒に外で遊んだり、工作をしたりしています。子どもたちに喜ばれそうな遊びや工作を事前に考え、活動後は子どもたちの様子を共有する反省会をしています。
写真左:おもちゃ図書館ボランティアで、子どもたちが触るおもちゃを開館前に除菌しているところ。左が為我井さん
写真右:新宿子ども会 KIDSの活動で、子どもたちと一緒に借り物競争をしている場面
他にも、英語を使ったボランティアをしたいという要望に対して、留学生と英会話をしながらゴミ拾いをすることで国際交流できる企画や、ハンディキャップのある方たちと買い物や料理をしながら触れ合う企画を開催しました。
――今後、ボランティアにどのように携わりたいですか?
私はWAVOC学生リーダーとしてボランティア活動を企画する立場なので、教育支援に限らず、多くの人が参加したいと思えるさまざまな分野のボランティアを提供していきたいです。
大学では特別支援学校の教員免許を取るための勉強をしていますが、WAVOCのボランティア活動では、子どもに対する声掛けや接し方をどのようにすれば良いかなど、実体験を通して理解を深めることができました。教育支援ボランティアでは将来につながる気づきが多く得られるので、これからもたくさん経験を積んでいきたいと思っています。
能登半島地震災害復興支援ボランティア
「実際に被災地に赴き、災害に正面から向き合い続ける」
法学部 3年 齋藤 美里 (さいとう・みり)

戸山キャンパスにて
――「能登半島地震災害復興支援ボランティア」に参加したきっかけは何ですか?
2023年8月に母方の実家である秋田市に帰省した際、同年7月の豪雨災害の影響で閉店を余儀なくされ、活気が失われてしまった商店街の姿にショックを受けました。それがきっかけで大好きな秋田の力になりたいと思い、同年9月のWAVOCの「秋田市災害復興支援ボランティア」に参加したことで、「私にもできることがあるんだ」と実感したんです。その後、同年10月の「いわき市災害復興支援ボランティア」にも参加し、災害で困っている人たちの助けになるのであれば、少しでも多く参加しようと考えるようになり、2024年3月から行われている「能登半島地震災害復興支援ボランティア」にも積極的に関わるようになりました。
災害支援ボランティアは未経験でしたが、WAVOCは交通費の補助や作業に使う備品の貸し出しがあることから、学外のボランティアに比べて一人でも参加しやすいと思い、一歩踏み出したんです。
――どのような活動内容か教えてください。
能登半島地震災害復興支援ボランティアは何度か募集がかけられており、私は、2024年3月にいずれも石川県の志賀町で、5、6月に珠洲市での活動に参加しました。志賀町では、家の周りの倒壊したブロック塀などのがれきの撤去が主な作業でした。
写真左:志賀町災害ボランティアセンターで作業の説明を聞いた後、他のボランティアの方々とチームを組んで災害現場に向かったそう
写真右:志賀町でがれきの撤去をしている様子。手前が齋藤さん
珠洲市では、被災により捨てなければならなくなった家具や布団などの家財、いわゆる災害ゴミの運び出しを行いました。作業方法や危険区域の判断については、全国各地から来た経験豊富なボランティアの方にご指導いただけたので、初めての私でも安心して作業に従事できたと思います。
災害ゴミとして家財を廃棄するかどうかは基本的に被災された依頼者の判断によるのですが、例えば、親戚の子どもたちが遊びに来るから楽しみに用意していたという布団や、依頼者のお孫さんが描いた絵があるふすまなどを、災害ゴミとして処理しなければならないことに胸が詰まる思いでした。それでも、依頼者の方から温かい感謝の言葉を頂いたことは、次の活動につながる原動力となりました。
この活動に参加する前は、被害状況をニュースで見てつらさを感じても受け取るだけの立場でしたが、実際に被災地に赴き、大地震で破壊された街並みや、復興を目指して必死に活動するボランティアの皆さんの姿を目の当たりにしたことで、災害に対する自分の向き合い方が大きく変わりましたね。
――現在、ボランティアにはどのように携わっていますか?
私はボランティアサークルや外部のボランティア活動には所属していませんが、WAVOCの災害支援ボランティアへの参加を機に、これまで自分のために費やしていた時間を、誰かを助けるためにも使おうと考えるようになりました。現在(2024年6月下旬)、能登半島地震災害復興支援ボランティアは第8便に応募しているところで、今後も募集がある限り積極的に参加していきたいと考えています。
――今後、ボランティアにどのように携わりたいですか?

災害支援の活動について熱心に話す齋藤さん。学外では、横浜市のNPO法人が主催する能登半島地震の災害ボランティアにも応募しているそう
災害支援ボランティアに参加する上で自分の中で課題としているのは、被災者の方との関わり方です。能登半島地震災害復興支援ボランティアで、能登出身のボランティアのメンバーが被災者の方と能登の特産品のお話をする場面に居合わせたのですが、地元が誇るものの話題に触れたことで、被災者の方が初めて笑顔を見せてくれたことが強く印象に残っています。そのとき、自分も能登についていろんなことを知っていればよかったと後悔したのを覚えています。
また、被災者の方が何を求めているのか、私たちのやり方が被災者の方のやりたいことを奪ってしまわないかを考えることも、今後の課題として捉えています。今まで作業してきた中で、私が助けになると思ったことが、逆に嫌な思いをさせてしまったのではないかと感じる場面もあったので、今後は気持ちをくみ取ることができるよう心掛けながら活動していきたいです。
大学卒業後も災害支援のボランティアは続けたいです。ボランティアへの参加で休暇が取れる制度を設けている会社があるそうなのでチェックしていますし、少しでも時間があれば、より多くの活動に参加したいと思っています。
WAVOC職員より早大生の皆さんへ
WAVOCは、早稲田大学の社会貢献活動推進役として、自然環境保護、障がい者支援、スポーツ、地域活性、農業、防災など多様なボランティア活動を展開しています。学生リーダーと教職員が引率するので、ボランティア未経験でも心配ありません。また、単発で参加できる活動を中心に、中長期間で取り組むプロジェクトや宿泊を伴うスタディツアーを含むさまざまな形態を用意しているので、自分のスケジュールに合わせて参加できます。自然災害による被災地での復興支援ボランティアにも積極的に取り組んでいるので、ぜひ早大生の皆さんの力を貸してください!
平山郁夫記念ボランティアセンター(WAVOC)
【場所】早稲田キャンパス 99号館 2、3階
【事務所窓口開室時間】平日9:00~17:00 ※土日祝日は閉室
【電話】03-3203-4192(平日9:00~17:00)
【E-mail】[email protected]
【現在募集中の活動】https://www.waseda.jp/inst/wavoc/news/?tag=participate
【WAVOC支援サークル一覧】https://www.waseda.jp/inst/wavoc/project/circle/
【次回フォーカス予告】7月15日(月)公開「パリ五輪」














