大学で確実に身に付けたい
アカデミック・ライティング力を磨こう
レポートや論文などの課題が出ると、「書くことが苦手」「何を書いたらいいか分からない」と悩んでいませんか?文章作成技能を学び、使用する経験を積み重ねることで、文章作成力は確実なものとなります。早稲田大学では「学術的文章の作成」授業やライティング・センターで、そうした力を身に付けることができます。大いに利用しましょう。
監修:ライティング・センター教員スタッフ
アカデミック・ライティングとは?
アカデミック・ライティングとは、学術的文章や学術的文章を書く技術を指します。学術的文章とは、授業レポート、卒業論文、修士論文、博士論文、投稿論文などです。つまり、大学・大学院で課される文章はアカデミック・ライティングの特徴やルールに沿っていなければなりません。アカデミック・ライティングの特徴は、二つあります。
第一の特徴は「分かりやすい文章」です。学術的文章では、専門的な内容を論じたり、まだ〈答え〉が発見されていない〈問い〉について論じたりします。時に、非常に複雑な概念や専門用語を用いて論を展開します。どのような内容であっても読者に伝わらなければ文章の意味がありません。そのために、書き手は思考(考え)を整理する必要があります。
第二の特徴は「科学的な文章」です。アカデミック・ライティングでは主張を裏付ける根拠の提示が求められます。この点が中学校や高校で書いてきた文章と大きく異なる点です。主張を裏付ける根拠とは、先行研究、文献やデータなどさまざまです。
このように、アカデミック・ライティングは、書き手の主張を読み手が客観的に検証するために必要です。アカデミック・ライティングの特徴を踏まえて書くことを心掛けましょう。
参考文献:佐渡島紗織・吉野亜矢子(2008)『これから研究を書くひとのためのガイドブック―ライティングの挑戦15週間』ひつじ書房。
レポート・論文作成上の注意点
学術的文章では「剽窃(ひょうせつ)」(=知的窃盗)が禁じられています。「剽窃」とは、他者が書いた意見や発見を、自分の意見や発見のように見せ掛けて示すことです。つまり「剽窃」は〈他者の知的所有権を侵害する行為〉なのです。他者の意見や発見を使う場合、引用・出典を参考文献リストで示しましょう。
アカデミック・ライティングで心掛けたい6つのポイント
○一文一義
一文に一つの事柄を書きます。丁寧に一文一文を積み重ねると緻密な文章になります。
○語句
「語句」の意味範囲を意識して使うと、読み手に正確な情報が伝わります。また、専門用語は定義して使いましょう。
○構成
学術的文章は「序論・本論・結論」という構成になっています。序論で本文章の目的を示し、本論でその論証を行います。結論では本論を再度まとめます。
○〈問い〉と〈答え〉
学術的文章では、〈問い〉(=何を論じるのか)と〈答え〉が必要です。どこに〈問い〉と〈答え〉が書いてあるか、〈問い〉と〈答え〉が呼応しているか、確認しましょう。
○パラグラフ・ライティング
パラグラフは[中心になる一文(トピック・センテンス)+それを支える情報が書かれた文]で構成されています。パラグラフを積み重ねていくことで緻密な文章になります。
○主張と根拠
まず、その文章の主張が端的に分かるように書きます。次に、その主張について論証していきます。論証には根拠が必要です。客観的で適切な根拠を示せていますか。確認しましょう。
引用の基本的な作法
①他者の言と自分の言を「」で区別する。
②著者名/発行年/書名/ページ数(どの部分を使用したか)を、 引用した本文中に示す。
③本文の後に、引用した文献の情報を「参考文献リスト」として一覧で 示す。[参考文献リストの書き方の例]著者名(発行年)『書名』出版社
引用の方法は大きく分けて2種類あります。他者の一文やキーワードを使う〈要約引用〉と、他者の論を3行以上使う〈ブロック引用〉です。どちらの場合も他者の言と自分の言を区別できるように示します。また引用部の後に、上記の②の情報を示します。分野によって慣習が異なります。自分で調べたり、ライティング・センターで確認したりしましょう。
ライティング・センターを活用しよう
早稲田大学ライティング・センターは、2004年の創設以来、自立した書き手の育成を支援してきました。本センターを支える理念は、①ライティングを「過程」において指導する、②「領域を横断」して指導する、③文章を直すだけでなく「書き手を育てる」、の3点です。学術に関する英語・日本語文章であれば、分野にかかわらず、構想段階から検討します。ライティング・センターは、早稲田大学の学生・教員であれば、誰でも無料で、何度でも利用できます。1回のセッションは45分で、文章指導の訓練を受けたチューターが個別に対応します。書き手自身が、文章の改善方法を決定できるよう、対話を通して一人一人のライティング段階に合わせた支援を行います。
「書く」というのは誰にとっても大変なもの。一人で悩まないで、やる気が出ないときこそライティング・センターに来てみてください。話しているうちに、何かアイデアが生まれるかも!
セッションの種類
▲英語の文章→英語で検討(EE)
▲英語の文章→日本語で検討(EJ)
▲日本語の文章→日本語で検討(JJ)
▲日本語の文章→日本語教育の専門家と日本語で検討(JS :日本語初級者の留学生対象)
▲日本語の文章→英語で検討(JE)
サポートできる文章
▲授業のレポート
▲プレゼンテーション原稿
▲留学志望書
▲卒業論文
▲修士論文
▲博士論文
▲投稿論文など学術的な文章全般
※就職関連の文章は、ライティング・センターでは扱っていません。キャリアセンターにご相談ください。
体験リポート: プレゼン原稿を見てもらいました
「自分で気付く、自信がつく」
創造理工学部4年 大野研究室所属
舘野(たての)ひとみ
今回初めてライティング・センターを利用しましたが、想像以上に有意義な45分間を過ごせたと感じています。ライティング・センターを利用したことで、一般 的なプレゼン・スキルとともに、自分のプレゼン原稿の改善点を客観的に考える力も身に付きました。実際にチューターの大森さんは、プレゼンについて多くの 有益なアドバイスをしてくださっただけではなく、たくさんの質問を通じて私の枯渇していたアイデアを掘り起こしてくださいました。ライティング・センター に行けば、皆さん一人一人の要望を最大限にかなえる形で、原稿を仕上げることができると思います。皆さんもぜひセッションに参加してみてください!

①Waseda-netポータルで予約
①Waseda-netポータルで予約
卒論準備のプレゼン原稿を見てもらうため、ライティング・センターに予約を入れる。Waseda-netポータルにログイン→左メニュー「授業」「個別指導予約」→実施箇所のプルダウンより「早稲田大学ライティング・センター」をクリック。「詳細項目」で、日本語で対話しながら日本語文章を検討するセッションを申し込む。
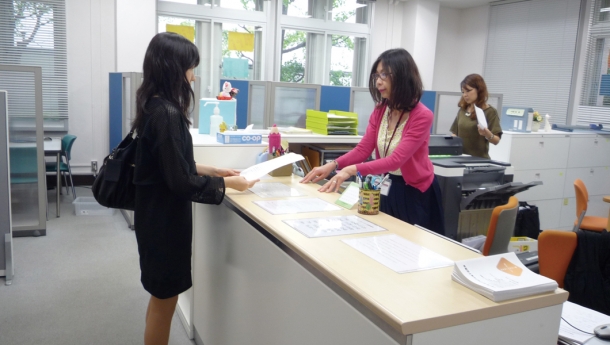
②ライティング・センターを訪ねる
②ライティング・センターを訪ねる
予約した日時にライティング・センターへ。受付で利用申請書を記入し、紹介されたチューターと個別ブースでセッション開始!

③セッションを受ける
③セッションを受ける
チューターは日本語教育が専門の大森優さん。まずは、今日のセッションの目標を確認する。次に自分で原稿を音読。その後大森さんからの質問や指摘に答えるうちに、文章の問題点や修正法に自ら気付き、自分の考えが整理されてくる。あっという間に45分終了。

④原稿を仕上げ発表する
④プレゼン原稿を仕上げ発表する
セッションを踏まえてプレゼン原稿を修正し、完成させた。そしてついに、所属する経営システム工学科・大野髙裕研究室の卒論ゼミで発表。セッション以前に先生からいただいたスライドの読みづらさに関するご指摘はなくなり、無事に発表を終えることができた。
■ライティング・センター
03-3204-9052
[email protected]
早稲田キャンパス 7号館 1階(2014年秋、新3号館2階に移転予定)
西早稲田キャンパス 60号館 2階201号室
TWInsキャンパス 50号館 2階02C502室
所沢キャンパス 図書館(グループ学習コーナー)








