
商学学術院 教授 江澤 雅彦(えざわ・まさひこ)
早稲田大学商学部卒業、同大学院商学研究科博士課程単位取得退学。2001年博士(商学)早稲田大学。専門は生命保険論。著書に、『生命保険会社による情報開示』(成文堂)など。
日本の医療を支えている国民皆保険制度。満足いく社会生活を送るために、最低限の知識を身に付けておきたい。
生命保険といっても、学生諸君にとっては、まだ縁遠い感じがするだろう。卒業後、大半の学生諸君は就職し、一般の事業会社などから給与を受け取って生活する。そうした中で、諸君が生命保険(あるいは生命保険会社が提供する商品・サービス)に対して持つニーズは、大きく2つに分けられる。
第1のニーズは、何らかの理由で、毎月受け取っている給与を受け取れなくなってしまう場合に生ずる。「収入途絶に対するニーズ」である。病気やけがによって休職・退職を余儀なくされれば、従前の生活を維持することは難しい。その際、公的な保障としては厚生年金保険から「障害年金」を受け取ることができる。ただ、「健康で文化的な最低限度の生活」を目標とする以上、社会保障の一つとしての当該年金で、「不満のない」生活を続けることは難しい。そうした場合に備えて、民間の生命保険会社を通じて「就業不能保険」などに加入する必要があるであろう。
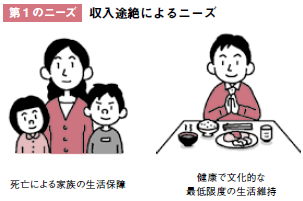
また、病気やけがなどにより死亡する可能性もないとはいえない。死亡する年齢や、その際の家族の状況にもよるが、遺された配偶者や就学中の子どもが、家計の主たる担い手の死亡による「収入途絶」により、生活困窮に陥る場合もある。そうした事態を避けるために、死亡保障のための生命保険に加入することも必要であろう。
第2のニーズは、病気やけがによる「想定外費用の補填に対するニーズ」である。わが国の公的医療保険は、先進諸国と比べてもかなり整備されていて、われわれが自己負担すべき金額は一定程度に限られている。厚生労働省のホームページを参照して、「高額療養費制度」について、ぜひ情報入手してもらいたい。ただ、例えば入院時に個室を希望すれば、相当額の差額ベッド料が請求され、入院時の諸雑費、退院後の通院費・交通費など、種々の出費もかなりの額に上ることが予想される。そうしたことを想定して、民間生保会社が提供する各種医療保険の加入を検討する必要も生ずる。
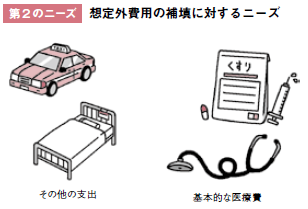
「いろいろなものがあって、分かりにくい」と評される生命保険だが、「収入途絶」「想定外費用の補填」という2つのニーズに着目して、将来、保険会社と保険商品を選択してもらいたい。
(『新鐘』No.81掲載記事より)
※記事の内容、教員の職位などは取材当時のものです。








