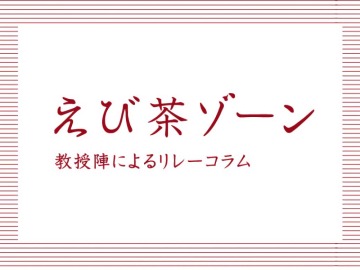
自然の中を歩き回ることが趣味である。
自分の専門分野である経済学は、日常生活への滲出(しんしゅつ)性が非常に強い学問である。経済学の方法は、およそ人間が関わる全ての現象に適用可能なものであり、近所のスーパーの特売品から通勤電車でお年寄りに席を譲る高校生まで、ありとあらゆるものが経済学の練習問題に見えてくる。これは大変よろしくない。
何がよろしくないかって、それが人間の全てではないからである。それでも、数十年にわたる自己訓練により経済学的思考に特化してしまった脳内の回路が、目に映る全てのものに対する利己的動機と制約条件を自動運転で探り始めてしまう。消費期限が近い商品を安く仕入れて特価品として売ることで話題を集める広告戦略。どこかで自分を見ているかもしれない知り合いに向けてのアピール活動。このような視野しか持てないことは、自分の人生を貧しくする。
そういうわけで週末には野山に出る。樹間を通り抜ける初夏の空気、足裏に届く土の感触には、自己の生命を、生命だけを喜ぶ生き物たちの気配が満ちている。山頂から麓をはるかに見下ろし、そこからさらに蒼穹(そうきゅう)をふり仰ぐことで、われわれがまるで自分たちの全てのように思い込んでいる「人間社会」が無数の虚構からなる作り物であることを改めて悟る。そうやって脳内回路の通電を止める。疑似世界に順応し過ぎてしまった経済学者の眼を抉(えぐ)り、宇宙の隅で歓喜しながら生きている野生動物の眼を回復させるのである。
それから、ゆるゆると山を下りる。下りながら、明日の講義について考え始める。
(H.T.)
第1130回








