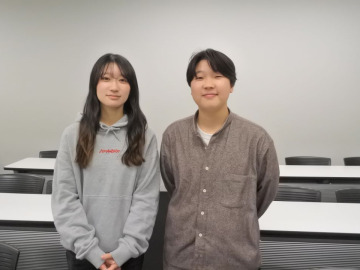映画『ボヘミアン・ラプソディ』がバカ売れで、バラエティ番組のBGMもよく聴くと、みんなクイーン。中学の時、クイーンを隠れて聴いてた自分を思い出すと、隔世の感がある。どうして隠れていたのか。自分が中学の時、洋楽を聴く中学生はプログレやグラムロックを聴くもんだった。つまりELPやイエス、ピンクフロイド、キング・クリムゾンにデヴィッド・ボウイ。そんな中、クイーンはある意味、あだ花だった。ガリガリの体に、ボーカル、フレディーのお世辞にも美男子とは言えない風貌、不恰好な長髪、メイク。その異形(いぎょう)のものが驚異のソプラノボイス。
これは当時のロックの枠組みからするとカッコワル過ぎた。男子はみんな無視した。クイーンに反応したのは、異形なもの、想定外の世界を受け容れる少数の女子だった。女子の一般的感性を逸脱し続ける日本の女子(現代ならカワイイを発見した女子)が、クイーンを熱狂的に支持したのだ。女子の前で、自分は小さくなっていた。
クイーンもクイーン・ファンもカッコワルかった。思ったように事の運ばないもどかしさは、勝手に脚が震える『変身』のザムザのようだ。しかしカッコワルイは、既存の価値観に対する亀裂だ。それは外に広がる外部の受容器になる。外部とは、コントロールできる機械・都市の外部で、譬喩(ひゆ)的に田舎と感じられ、外部を伴うことは田舎くさい、田舎い、たしゃいが転じてダサいとなった。つまりカッコワルイを突き抜けて外部を受け容れるものは、「ダサカッコワルイ」として生成される。さて、早稲田に期待されるのってこれじゃないのか。
(YPG)
第1045回