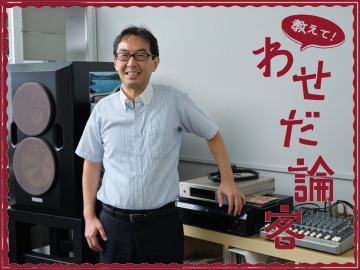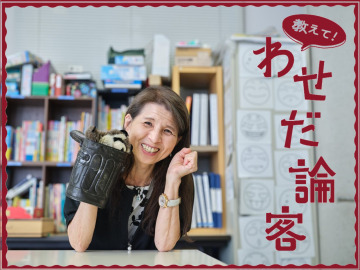健康・医療領域にもデジタル化の波が押し寄せる昨今。テクノロジーの発展とともに、最先端技術の社会実装における法の重要性は無視できないものになっています。
2024年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「健康とは何か?」。複数の専門家の視点から、健康について考えます。今回のゲストは、「先端科学技術と法」を専門とする肥塚肇雄教授(法学学術院)です。遠隔診療をはじめとする先進医療の法的課題に詳しい肥塚教授に、デジタル社会における健康領域の法のあり方と今後の可能性を伺いました。
健康・医療分野のデジタル化が進むことで、法分野にはどんな影響が生じるのでしょうか?
人とテクノロジーが融合していく「Society 5.0」時代の波は健康・医療分野にも押し寄せ、法のあり方や解釈も変わっていくと予測されます。一方で、「正義と衡平(※1)」という法の理念が不可欠であることには変わりません。むしろデジタル化する社会の設計においては、法的素養を備えた人材の存在がより重要になってくると考えます。
(※1)「公平」は人々に対して同一待遇を施すことである一方、「衡平」は人々の違いを前提として、目的を達するため、その違いに応じた異なる待遇を施すこと
INDEX
▼先端科学技術の発達によって新たな法の課題が生まれる
▼医療アクセスを改善する「オンライン診療」がもたらすメリット
▼Society 5.0の時代にも不可欠な「正義と衡平」という法の理念
先端科学技術の発達によって新たな法の課題が生まれる
肥塚先生の現在の研究テーマについて教えてください。
専門は「先端科学技術と法」で、ニューリスクと保険法を軸にして、メタバース空間やMaaS(Mobility as a Service)、自動運転、先進医療といった先端科学技術が社会受容性を高めるために必要な法整備について研究しています。健康増進・医療介護に関する分野では、オンライン診療やiPS細胞を活用した臓器移植まで幅広く扱っています。
新たな科学技術を開発し社会に実装していく際に課題となるのは、技術的な問題だけではありません。倫理的、法的、社会的な課題も含めてクリアしていく必要があり、これらの課題は、それぞれの頭文字(Ethical, Legal and Social Issues)をとって「ELSI(エルシー)」と呼ばれています。私の立場としては法的課題の整理をすることは当然なのですが、最終的には社会的課題、いうならば社会受容性の視点が非常に重要だと考えています。社会受容性が低いままでは、先端科学技術を社会に実装することはできません。
例えば、交通の利便性に欠ける離島などの地域にドローンで医薬品を配送するシステムを想定してみましょう。この取り組みは技術的に実現可能であっても、航空法や電波法などの規制への対応やリスク対応の整備ができていなければ導入には至りません。万が一、事故が起きたときにはどのように対応し、賠償問題を解決するのか、そこまで見据えた法整備をしなければ人々の理解を得ることは難しく、新たな技術を社会に浸透させていくことはできないのです。

先端科学技術の発達によって、法のあり方はどう変化していくと考えられますか?
政府は日本が目指すべき未来社会の姿として「Society 5.0」を掲げています。これは「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」として提唱された概念です。
このサイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)の融合は、司法制度にも大きな影響を及ぼします。そもそも近代私法は、人と物を分けることを出発点としてきました。権利の主体は「人」であり、われわれ自然人と法人のみでした。しかし、「人」と「物」が融合することは、近代私法は想定していないのです。

Society 5.0が目指すスマートシティのイメージ
例えば、スウェーデンでは、マイクロチップを手に埋め込み、ドアのセキュリティーの解錠や電車のチケットとして利用する取り組みが広まりつつあります。今後はIoT(※2)の発展で、これまで以上にさまざまなモノがインターネットに接続されます。体重計の機能を備えた洗面所、睡眠管理ができるベッドなど、自宅で健康管理ができるスマートホームも一般化していくでしょう。疾患予防や病院のような検査機能が実装された住宅に暮らすことで、私たちの身体もインターネットに接続され“Internet of Human”という新しい領域が開かれる可能性があります。これによって、自分たちの身体がデジタルテクノロジーと融合し、法分野では従来とは異なる新たな視点や規定が求められると予測されます。
(※2)Internet of Thingsの略。 モノがインターネットにつながる仕組みのこと
健康・医療分野においてはいかがでしょうか? 法の観点で変化を感じる部分があれば教えてください。
身近なところでは、保険会社のあり方が変革を迫られています。自動車に設置した端末機からドライバーの運転状態(事故リスク)を評価し保険料に反映させるテレマティクス自動車保険のように、生命保険の分野においても、昨今は保険金の支払額を抑えるために、データの活用によって健康意識を高め、いかに疾病リスクを防ぐかが競争のポイントになっていると感じますね。実際に、1日に歩いた歩数や燃焼したカロリーの量をモニタリングすることで、疾病リスクそのものを減らす健康増進型医療保険が登場しています。自ら計測した歩数や健康診断の結果によりポイントがたまる保険商品もあります。たまったポイントは、保険料の割引などに活用できる仕組みです。
テクノロジーの進歩でビッグデータを収集できるようになった現代では、従来なら予想がつかなかった個々の疾病リスクが可視化されています。リスクの個別化によって集団のリスクの同質性が形骸化すれば、従来の保険契約のあり方では立ち行かなくなってしまうことが懸念されます。将来的には、それぞれのリスクに応じた適切な保険料の算定が一般化するとともに、ビジネスモデルの変化に伴う法整備も必要になってきます。

医療アクセスを改善する「オンライン診療」がもたらすメリット
健康・医療分野について、肥塚先生が特に注目しているトピックは何でしょうか?
私は早稲田に赴任する前は香川大学に勤務しておりましたが、そこで特に力を入れてきたテーマの一つに「遠隔医療」があります。県内の離島へ医薬品を配送するドローンの実証実験などに参加していたのですが、特に地域の皆さんが協力して設立したコンソーシアムにも参加させていただき、国交省のスマートアイランド推進実証調査を通して勉強する機会に恵まれました。この実験は、オンライン診療を想定した空中・水中ドローンの社会実装化を目指して実施されたもので、私はオンライン診療やドローンでの医療品配送における法的知見を考える機会をいただきました。
写真左:空中ドローン。モバイル心電計や医薬品など計5kgまで搭載でき、時速50kmで飛行が可能。離着陸ポイントには気象ライブシステムが設置され、安全に飛行できる環境がリアルタイムに判断することができる
写真右:長さ2m、幅1mほどの船型の水上ドローン。50kgまで荷物を搭載できるため、医薬品の他、日用品も運べる
有人離島の多い香川県は医療先進県といわれており、全国に先駆けて遠隔医療を取り入れてきた自治体です。この立役者は原量宏先生(香川大学名誉教授、日本遠隔医療学会名誉会長)です。1970年代から、オンラインでの周産期医療を可能にする遠隔胎児モニター、iCTG(分娩(ぶんべん)監視装置)を構想・開発され、テレビ会議システムを活用したオンライン診療も実装化されました。併せて、K-MIX(かがわ医療情報ネットワーク)と呼ばれるEHR(Erectric Health Record)も構築され、香川県の医療機関のカルテの共有化を可能とするシステムを作りあげました。
離島に住む妊娠中の方が定期検診を受けに高松までフェリーで行く不便さを解消し、かつ島民の方々の医療アクセスを恒常化する試みであり、地域完結型医療を目指すものです。とりわけ、香川県の周産期死亡率(※3)は1970年代では全国でワースト5に入っていたのですが、今は常に全国でベスト5には入っている「赤ちゃん安心県」です。この医療アクセスの改善は、外出に慎重にならざるを得なかったコロナ・パンデミックでも再評価されました。
(※3)年間の1,000出産に対する周産期死亡(妊娠満22週以後の死産+早期新生児死亡)の比率
国民皆保険制度でそれぞれが保険料を払っている以上、「衡平」の観点からは、医療アクセスの地域格差はあってはならない問題です。オンライン診療の推進は、この地域格差の解消にもつながります。
今後のオンライン診療の可能性についてお聞かせください。
日本でなかなかオンライン診療が普及しない背景には、対面診療と比べて、触診・打診・聴診などが実施できないことから診療報酬点数が低くなることに加え、病院が新しい設備やシステムの導入に保守的であるのが大きいように思います。さらなる拡充のためには、制度の再検討とデジタル環境の整備が求められます。一方で、オンライン診療と相性の良い疾患や診察としては、例えば問診が中心となる高血圧症や糖尿病などの慢性疾患が挙げられます。
オンライン診療の普及で特に期待しているのは、海外での長期滞在におけるメリットです。もし慢性疾患を抱えている人が海外駐在員になった場合、自分や家族のかかりつけ医のもとを離れて現地の医師に診てもらうのは大きな負担になります。特に自分や家族が精神的な疾患を抱えている場合は、言語も文化も異なる環境での受診は非常に不安でしょう。その点、海外でも引き続き同じ医師に診てもらえれば安心して生活を送ることができます。
しかし、その場合、海外に向けたオンライン診療に適用される法律は日本のものか海外のものかが問題になります。海外のある国にいる被保険者(患者)が日本にいる医師のオンライン診療を受けるとき、日本の公的医療保険(国民健康保険および健康保険など)は、被保険者(患者)になる資格を有する者であれば適用されると解釈することが一案です。しかし、その国ではその診療が法律に抵触するかもしれません。これについては、日本の医師はセカンドオピニオンを提供しているという整理をすれば、問題ないようにも思います。
また、将来的には、医師の免許については日本と諸外国との間で相互にクロス・ライセンス(Cross-licensing)制度の門戸を開けば、海外に向けたオンライン診療に弾みがつきそうです。あと、オンライン診療による処方箋をどうするかは大きな課題ですね。このように、海外に向けたオンライン診療は日本のかかりつけ医の診察を受けられるという点で有効でも、解決すべき法的課題がいろいろありそうです。
Society 5.0の時代にも不可欠な「正義と衡平」という法の理念
法分野で肥塚先生が感じている社会課題があれば教えてください。
高度経済成長期の日本は、インフラ整備や工業化による急激な経済成長で戦後復興を遂げました。当時、インフラを整備し工業化を進めていく設計図となったのが、法令でした。法令の制定は経済成長の礎だったわけです。また、司法権は、インフラを整備し国全体の豊かさを実現していく過程の中で、犠牲になる虞(おそれ)があった少数派の人権や利益を守る存在として重要な役割を果たしてきました。
それに対し、現代社会においては、社会のデジタル化が推し進められている通り、求められるのはインフラ整備や工業化ではなく、デジタル世界の設計と拡充です。そのメタバース空間やWebサービスを設計しているのは誰かといえば、必ずしも法的素養を持っている方々ではなく多くは理工系の方々です。

デジタル社会における「正義と衡平」のイメージ
昨今は、巨大IT企業が絶大な力を持つようになっています。そうした巨大企業で働く人たちがけん引するデジタル領域の設計においても、法的素養を備えた人材が必要だと私は考えています。デジタル社会においても誰かの権利を脅かすことなく多様性のある社会を実現するためには、「正義と衡平」という法の理念が不可欠です。
最後に、早大生に向けてメッセージをお願いします。
これから到来する「Society 5.0」の時代においても、「正義と衡平」の理念のもとで社会を設計していく視点の重要性は変わらないと思います。デジタル領域に興味がある学生には、人文系科目はもちろんのこと、法学の基礎をしっかりと学んだ上で、情報理工系の学びも深め、デジタル世界の「正義と衡平」に適った設計図を描いてもらいたいですね。
また法学を学ぶ皆さんには、さまざまな側面から法の役割を考えてもらえたらうれしいです。法曹を目指すことはもちろん素晴らしいことですし、法曹になる以外の素晴らしい進路もあります。どんな進路を選んでも、人文系の科目もしっかり学んで、法が果たすべき役割は何かを常に自問自答しながら社会と向き合ってほしいです。
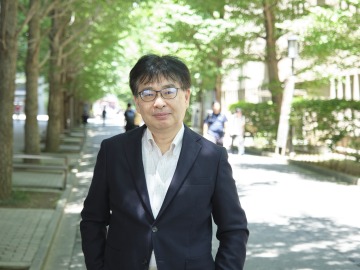
肥塚 肇雄(こえづか・ただお)
法学学術院教授。博士(法学)。2022年4月に法学部に開設された「先端科学技術と法コース」所属。専門は先端科学技術と法、リスクと法、交通と法、賠償と法、メタバースと法。先進医療や自動運転に係る授業の他、2023年秋学期から開講した、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社寄附講座「メタバースと法」も担当。先端科学技術の社会受容性を高めるための法のあり方について研究に取り組んでいる。
取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)
撮影:石垣 星児
画像デザイン:内田 涼