敬語コミュニケーション論【GEC設置科目】
大学院日本語教育研究科 修士課程 2年 桒田 晶(くわた・あきら)

蒲谷宏先生(左)、桒田さん(右)
突然ですが、皆さんは日ごろ敬語をどのような場面で、どのように使用していますか? また、私たちは敬語の使用を通じ、どのような人間関係を目指しているのでしょうか。
私たちは、日ごろ多くの場面で敬語を使います。大学では学生から先生へ、ビジネスシーンでは部下から上司へ。これらは、上位者に対して敬意を表すために敬語が用いられています。しかし、実際には先生から学生へ、上司から部下へ、従来敬語が使用されてきたシチュエーションとは逆の方向に敬語を使うこともあります。
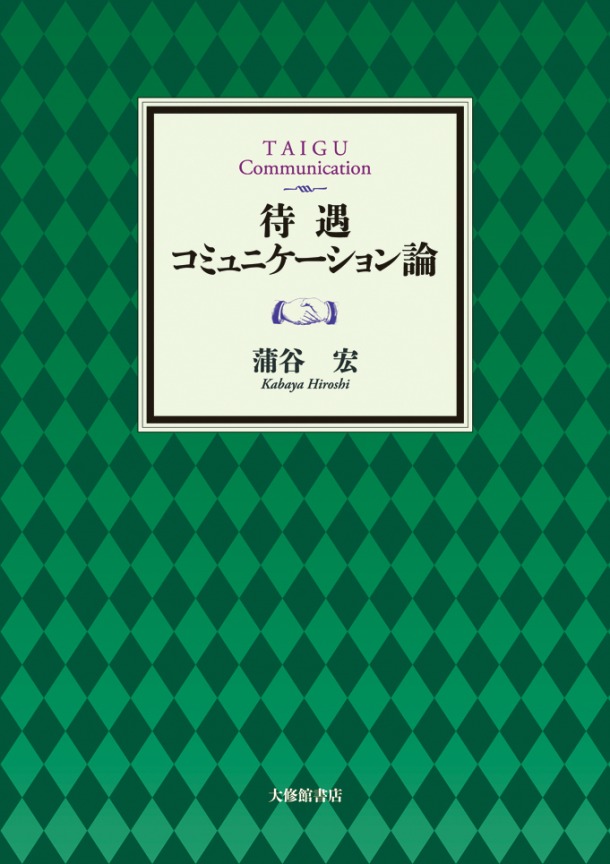
テキストとして使用する『待遇コミュニケーション論』蒲谷宏著(大修館書店)
敬語とは、敬意を表す語である、と私たちは学習してきました。その中でも尊敬語・謙譲語は、目下の者が目上の者へと使う表現とされてきました。しかし、現実はこのように単純な区分で分けることはできません。私たちは毎日、自分より上か下かを検討することなく、また場合によっては自分より下であることが明らかになっていても、尊敬語・謙譲語・丁寧語を駆使し人間関係を構築しています。
蒲谷宏先生(国際学術院日本語教育研究科教授)による「敬語コミュニケーション論」では、「敬語コミュニケーション」および「敬意コミュニケーション」について講義やディスカッションを通して考えることができます。オープン科目のためどの学部の学生も履修でき、留学生も多く履修しています。多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり、講義中に提示されるシチュエーション別の検討課題に沿ったディスカッションを交えつつ、敬語への学びを深めています。

グループごとに分かれてのディスカッションを中心に授業が行われます
最後に、冒頭の問いに対して一つの視点をお伝えできればと思います。なぜ、私たちは敬語を使うのか。この授業では、敬語の使用条件は相手の立場が自分より上か下かだけで決まるのではなく、敬語使用者である私たち自身の意識に目を向けてこの問題を捉えることを学びました。「いつ敬語を使うべきなのか」は、私たちが敬語の使用を通してどのような人間関係を築きたいのか、どのように思われたいのかを表現しているとも捉えることができるのです。








