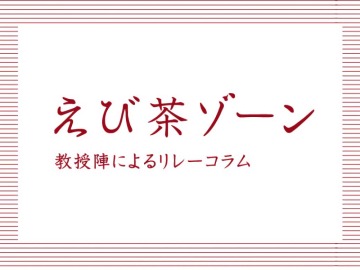
最近レポートの剽窃(ひょうせつ)を多く目にするようになった。インターネット上の記事をそのまま切り貼りして、出どころを示さずに提出されたものが多い。剽窃であるという確認が取れた場合は、試験における不正行為と見なされて、停学処分が言い渡され、その学期中に履修した科目の成績が全て無効になるという大変厳しい処分が科されることもある。
これだけ厳しい処分が科されるにも関わらず、剽窃レポートが後を絶たない理由はよく分からない。フランスの社会学者デュルケームが「犯罪は社会にとって正常なものである」と述べていたように、一定数の不正行為があることは大学が正常に動いているということの証しなのかもしれない。ただ、それで済ます訳にもいかないので、私の授業では、不正行為で単位を得ても自分の成長は得られないこと、不正行為による成功体験を身に付けてしまうと、今後責任ある立場に就いたときに痛い目に遭うことなどを説明している。
デュルケームの言葉には続きがあり、「一定数の犯罪があることが正常であるだけでなく、それがきちんと罰せられることも正常なのだ」ということである。スポーツと同じく、ルールをきちんと適用して個々のプレーヤーが最高のパフォーマンスを発揮できるようにしなければならない。また、剽窃は学生だけでなく、われわれ大学教員の中にも見られ、時折ニュースになっている。こうした「良き反面教師」として生きるのもありかもしれないが、私はこれからも教壇から剽窃の不毛さを説いていきたい。
(YI)
第1161回








