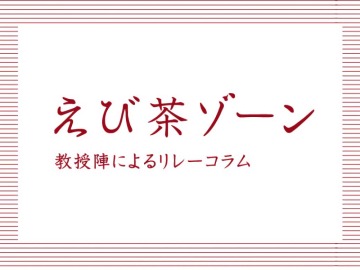
目指されるべき普遍的価値の存在が自明のものでなくなった今日、多様な価値を認める前提がとられながら、実は一元的な価値が押し付けられる、という矛盾に満ちた事態が大学を巡っても生じている。政府が目下大学に最も期待しているところは、日本経済の競争力を高めるイノベーションをどれだけ生み出せるかだ。この観点から事業規模を年3%成長させる見込みのある大学を選別して、国際卓越研究大学に指定し、年間数100億の助成をする。
多元的な価値のうち何を普遍的なものとして選択するかという、思考の手続きを踏みながら議論しなければならない困難な問題が、恐らくその困難性故に、数の問題に置き換えられ、数の論理が多様性を奪うという矛盾(蓮實重彦『大学の倫理』2003年、東大出版会)が、年3%の事業規模成長や、上位10%論文1,000本以上、民間負担経費合計額などという数値化された卓越大学申請要件に端的に表現されている。1位2位を争う競争は、当然に一律の基準に照らして競争参加者を評価することを前提とする。基準が複数存在すると比較ができないからだ。
昔の中国の皇帝は、画家や陶芸家の品などを、一品、二品、三品という呼び方で格付けするほか、その等級には入らず品評は下せないけれど、いいと思われるものは「絶品」とか「逸品」とか「別品」として認めた。これらは非主流ではあるけれど、時を経るとどちらが1位か分からなくなる。他律的に一律に設定された時流のモノサシで測られて1位になるのは野暮(やぼ)、それよりも個性を発揮し時流を超えて輝く別品の粋を目指しませんか?
(N/B)
第1160回





